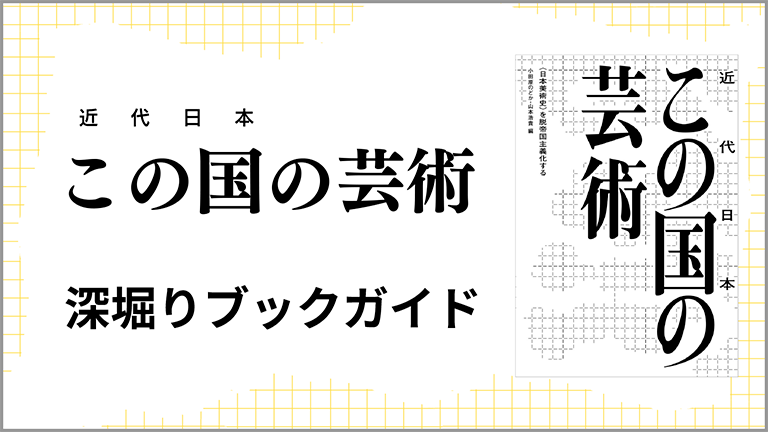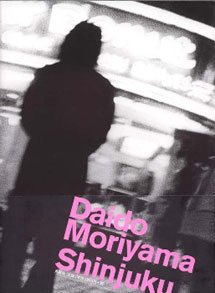夜、カメラを手に、歌舞伎町から区役所通りへ、そして大久保通りを新大久保駅へと歩いていくとき、 ぼくはときおり背すじがスッと寒くなる思いがする。とくに何が起きたというわけでもないのに、どこかでひるむ自分を感覚する。 新宿の裏町が確実に陰悪化しつつあることが肌で分かる。ネオンやイルミネーションのもとで、路地裏の暗がりのなかで、人々は影の存在となって蠢いて映る。 ぼくが手にする小さなカメラの視線に、それら影となった人々の、昆虫のように敏感な反応が電流となって伝わってくる。 緊張感でぼくの身体の細胞が少しざわつき、辺りの空気がザラリとひと荒れして知覚される。そこはかとなく暴力的なアトモスフィアに身をつつまれながら うろつき廻っていると、ひるむ気持にあらがうように、カメラマンであれば、やはり新宿を撮るほかはないとぼくは自分に言い聞かせる。 なぜならば、ここはほかならぬ新宿であり、大いなる場末なのだから。
新宿を写してきたこの二年余りの間に、ぼくはずいぶんいろんな人から、なぜ新宿なのですか? と訊かれてきた。新宿は、いまだにぼくの目に、大いなる場末、したたかな悪所として映って見えている。東京という大都市を構成する他の幾多の街が、戦後五十年余りの時間のグラデーションをすっとばして、見る見る白くサニタリーな風景となり果てているのに比して、新宿はいまだに原色の、さまざまな時間の痕跡を内包している。東京に居て、路上でカメラを持つ者にとって、これほど現代の神話に充ち充ちたパンドラの匣を見すごして、他に目を移すことなどは、とうていできない相談だ。
森山大道