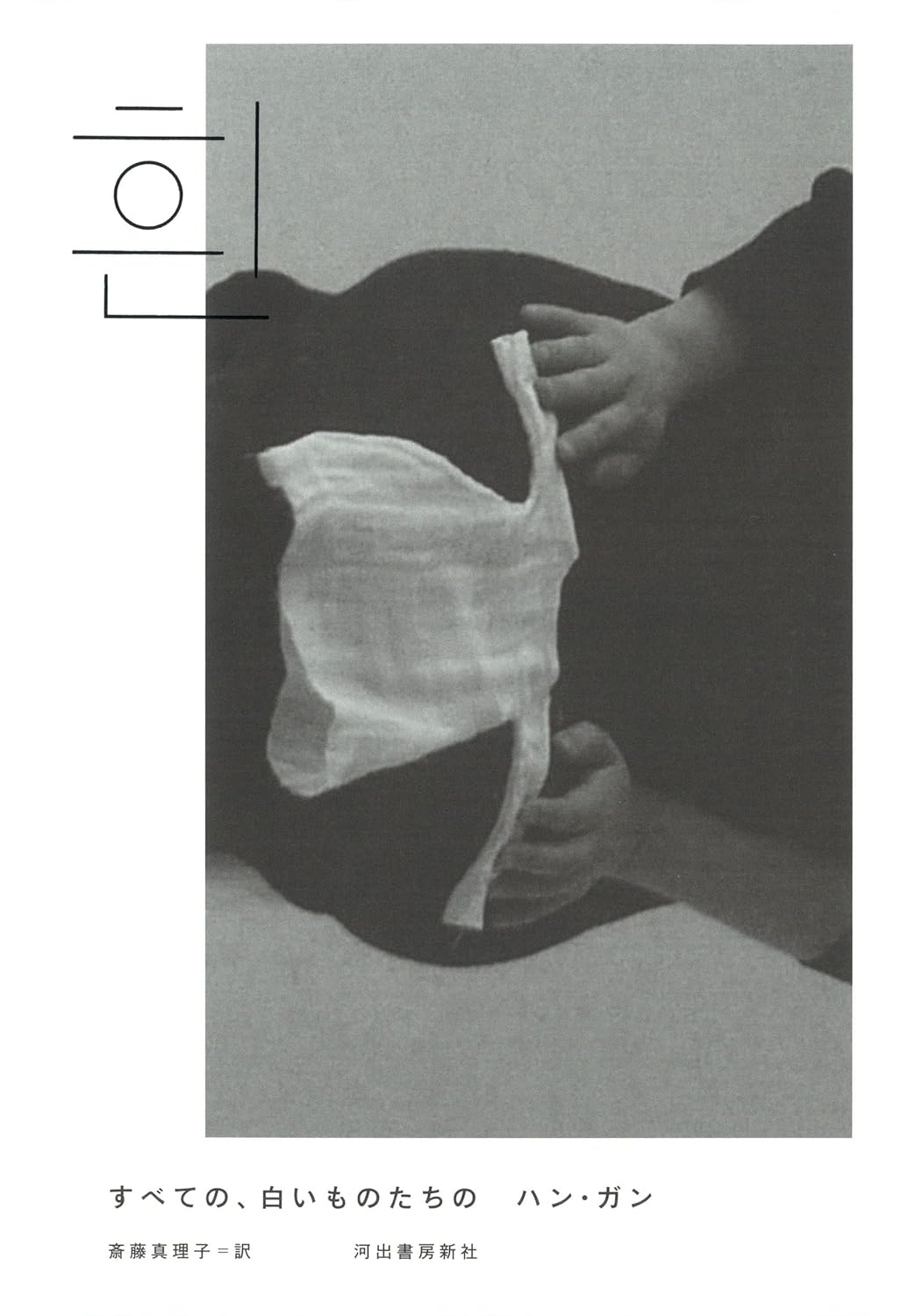2023年11月、書籍『この国(近代日本)の芸術:〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』が完成しました。
2022年7月に小田原のどかと山本浩貴による対談記事を掲載し(https://getsuyosha.jp/20220711-2/ )、同年12月14日には小田原・山本の第一稿公開しました(https://getsuyosha.jp/20221214-2/)。ウェブサイトでの第一稿の掲載、そして本書寄稿者によるオンライン連続講義の開催など、制作のプロセスを公開しながら、書籍化を進めてきました。講義や第一稿に寄せていただいた感想により、寄稿者の執筆内容に変化があっただけではなく、新たな共同研究や翻訳プロジェクトが立ち上がるなどの展開もありました(https://www.odawaranodoka.com/teikou)。
ここでは、『この国(近代日本)の芸術:〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』の刊行を記念し、寄稿者・編集協力者の方々に、本書に合わせて読むべき3冊を挙げていただきました。ぜひ『この国(近代日本)の芸術:〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』とともに読んでいただければ幸いです。
当初、『この国(近代日本)の芸術:〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』は書籍の刊行をもって完了する予定のプロジェクトでした。しかし、本書刊行の契機となった飯山由貴《In-Mates》の上映中止事件は解決してはおらず、その背景にある問題はいっそう深刻化しています。だからこそ、本書から始まった新たな共同研究や翻訳プロジェクトを通じ、引き続き、「〈日本美術史〉の脱帝国主義化」という視点から、「この国(近代日本)の芸術」を問い続けていきたいと思います。
本書制作のプロセスに関わっていただいたみなさんに、心からお礼申し上げます。
2023年12月16日 小田原のどか・山本浩貴
マユンキキ
GALANG 01&02(2022)
インタビューの中で触れていた、田村かのこさんと参加しているパワーハウスギャランの本です。 これまでギャランのメンバーで話し合ってきた内容が文字起こしされたものも読めます。 それぞれが抱えさせられている問題が見えてくるものです。ただし、私と田村さんのところ以外はほぼ英語です。
https://shop.powerhouse.com.au/products/galang-01-02
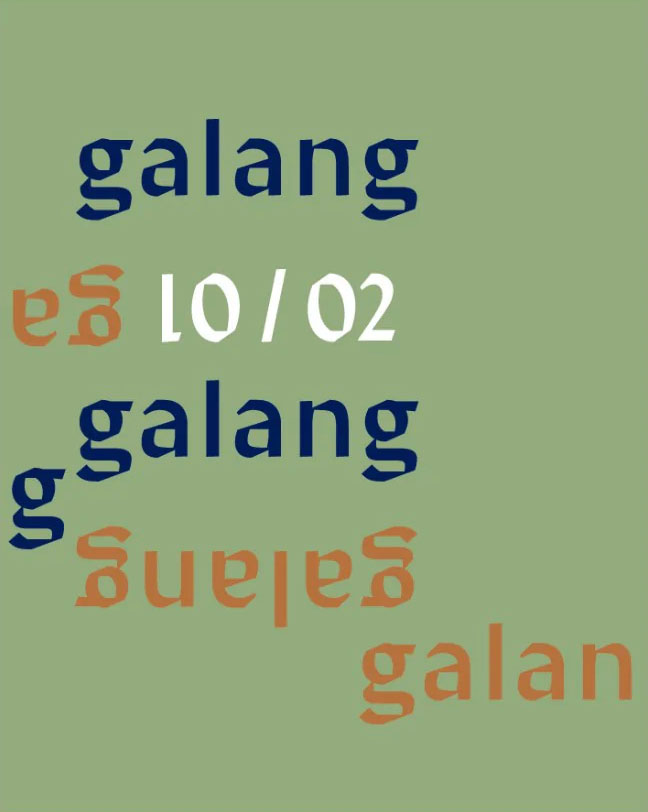
石原真衣『アイヌから見た北海道150年』(北海道大学出版会、2021年)
アイヌが自らの言葉で北海道150年について書いた本。アイヌといっても一枚岩で、みんなが同じ意見ではないというのが見えてくる。
インタビューではなく、それぞれが書いたという点もとても重要だと思っています。

反トランス差別ブックレット編集部『われらはすでに共にある: 反トランス差別ブックレット』(現代書館、2023年)
2022年に出された反トランス差別ZINEの増補版。こちらもそれぞれが、それぞれの言葉で語っている。読むたびに苦しくなるが、一人一人の言葉を丁寧に読み、そしてそれについて考えていく必要があると思わされる一冊。

千葉 慶
Stuart Hall. Encoding and Decoding in the Television Discourse ,1980
いわずと知れたメディア社会学の古典的論文です。内容はテレビ研究ですが、ある表象が「読まれる」過程は決して一方向ではないということ、「読む」ことによる抵抗もありうるということを教えてくれます。英語ですが、University of BirminghamのホームページからPDFでダウンロード可能。
千葉慶『アマテラスと天皇』(吉川弘文館、2011年)
拙著で申し訳ないのですが、類書がないので。今回の論文は一つのモニュメントについてでしたが、「象徴」天皇制全体に対象を広げて、いかにその巨大かつ入り組んだシステムに飲み込まれない主体でいつづけることが可能なのかを考察した一冊です。

丸山眞男『増補版 現代政治の思想と行動』(未來社、1964年)
近代天皇制研究の超古典「超国家主義の論理と心理」が収録されています。90年代以降さまざまな批判を受けていますが、今改めて読むと天皇制の問題の核をがっちり摑んでいて、やはりスゴイ。未読の方は是非。

穂積利明
Jonathan D. Katz, Hide/Seek: Difference and Desire in American Portraiture, Smithsonian Books, 2010
ジョナサン・カッツは米国におけるLGBTQ+アート研究の第一人者。単著は2023年12月に刊行される予定だが、本共著も、肖像画という一分野内ではありながら、アメリカ美術史における隠れた同性愛性を露わにしたという意味で意義ある一冊である。カッツは、19世紀後半に「同性愛者」が定義され、法的に成文化されたにもかかわらず、実際には、セクシュアリティの問題は常に流動的であり、描写行為に関心を持つアーティストたちによって絶えず再定義され続けてきた、と論じている。同性愛性自体が社会の中で揺れ動いていること、すなわち社会によって都合よく名付けられてきたこと、また美術はその抵抗を担ったことを教えてくれる。

菅野優香『クィア・シネマ 世界と時間に別の仕方で存在するために』(フィルムアート社、2023年)
LGBTQ+はあらゆる分野で周縁化されているが、映画・映像も例外ではない。この本は映画における同性愛性がどのように隠され、また現れているかをアメリカ映画・日本映画の中にたどり、芸術がどのように規範を脱することができるかという可能性を実例的に示した著作である。映画分野が「クィア・シネマ」と堂々と呼べるのは、ルビー・リッチが「New Queer Cinema」(1992)をいう論文を書いたことでそこから訴求的に「クィア・シネマ」が発見/発明されたとの認識を著者は持っており、「もし『クィア・シネマ』が疑問文であるとしたなら、その疑問はクィアにもシネマにも向けられる」といる。『この国(近代日本)の芸術』中で展開した私の考えとも問題意識が共通している。

北丸雄二『愛と友情と差別とLGBTQ+―― 言葉で闘うアメリカの記録と内在する私たちの正体』(人々舎、2021年)
90年代をニューヨークでジャーナリストとして過ごし、LGBTQ+がそう呼ばれる以前から脱周縁化を目指して戦ってきた米国の「ゲイムーブメント」を肌で体験してきた著者のLGBTQ+についての体験・知見の集大成と言える一冊。著者の集大成であると同時に、日本におけるLGBTQ+当事者の実績としても集大成と言えるのではなかろうか。とりわけ、映画を多く分析しているのだが、クィア・シネマ研究のアカデミックな方法とは別の、社会的・政治的側面が現れ、まさにLGBTQ+やクィアはこの社会で「生きている(ヴァルネラブルな)存在」なのだということを教えてくれる。美術を見る目にも大いに参考になる。

加藤弘子
佐藤道信『美術のアイデンティティー――誰のために、何のために』(吉川弘文館、2007年)
美術は誰のため、何のためにつくられ、どこに向かうのか。「美術のアイデンティティー」という視点から、近現代を経て、21世紀に入った美術の「現在」とその史的位置を探り、考察はその基底にある「人間のアイデンティティー」へと向かいます。制度論としては『〈日本美術〉誕生―近代日本の「ことば」と戦略』(講談社選書メチエ92、1996年)と『明治国家と近代美術―美の政治学』(吉川弘文館、1999年)が代表作かもしれませんが、本書には著者の人柄が滲み出ているので推薦します。研究室がなくなった筆者を引き受けてくれた恩師の著書で、当時は「宇宙と美術」「美術と異界」といった演習のテーマに驚き、先生は何を考えているのだろうと不思議に思っていました。
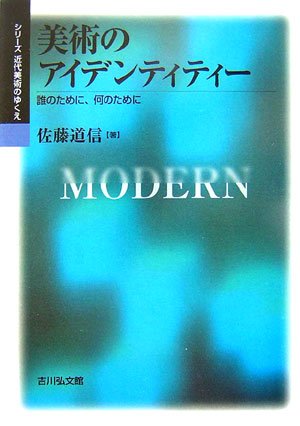
アマルティア・セン『アイデンティティと暴力――運命は幻想である』(大門毅監訳,東郷えりか訳、勁草書房、2011年)
近年、〈日本美術〉の素晴らしさを自身のアイデンティティに結び付け、「日本人であることを誇りに思う」と述べる学生の受講コメントが目につきます。著者のアマルティア・センは、こうしたアイデンティティの単眼的な捉え方に警鐘を鳴らした経済学者です。サミュエル・ハンチントンは『文明の衝突』で世界を9つに分類し、孤立した「日本文明」まで想定しましたが、対するセンは「現代の世界における紛争のおもな原因は、人は宗教や文化にもとづいてのみ分類できると仮定することにある」と、紛争を助長しかねないハンチントンの説を批判します。1人の人間が帰属するアイデンティティは複数あり、与えられたものではなく、自らが理性的に選択できる。戦争が続く今も、必読の書です。
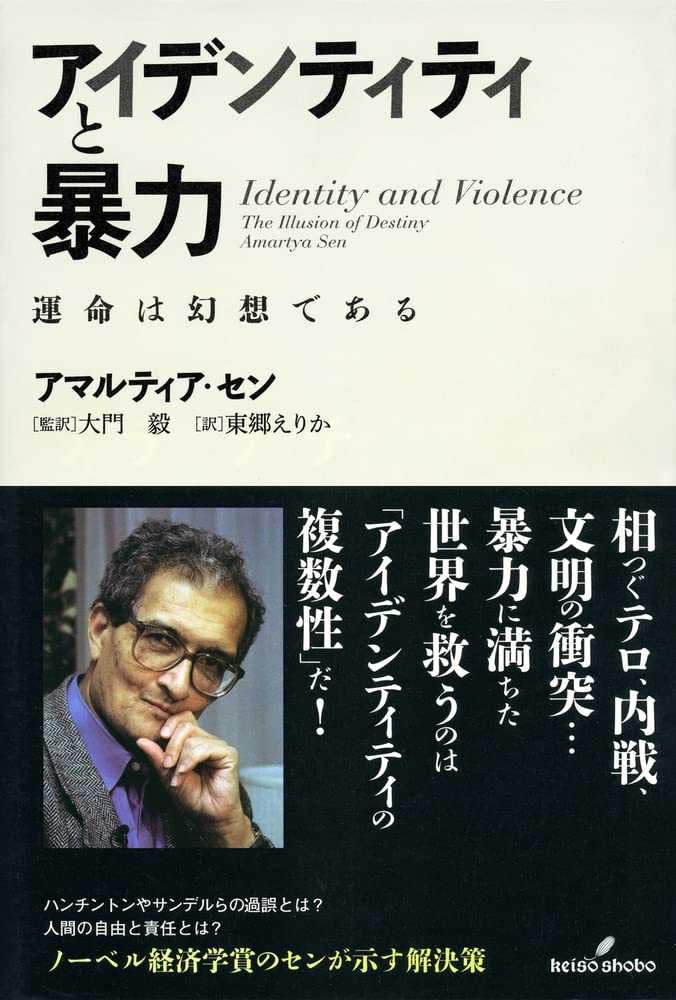
「〈特集〉 日本研究の道しるべ ――必読の100冊」『日本研究』第57集 2018年3月
https://nichibun.repo.nii.ac.jp/search?page=1&size=100&sort=custom_sort&search_type=2&q=988
国際日本文化研究センターの定期刊行物の特集で、日本研究に関わる研究書や入門書などを、分野ごとに解説したものです。書籍ではありませんが、他分野の状況や課題を共有する必要を感じているため、推薦します。「はじめに」に「今、人文科学を含めた学問の諸分野で、閉塞状況を打破する処方箋の一つとして、「学際化」の必要性が声高に唱えられている」とありますが、日本学術会議が1994年に「日本の学術研究教育の課題―国際化・学際化・開かれた大学」をまとめてから約四半世紀たちます。なお、人文科学の諸問題に関して、同センターの共同研究「人文諸学の科学史的研究」の成果をまとめた井上章一編『学問をしばるもの』(思文閣出版 2017年)があります。

北原 恵
西川祐子『古都の占領――生活史からみる京都 1945-1952』(平凡社、2017年)
私が『この国の芸術』で試みた対象と分析方法は、一見、西川の『古都の占領』とかけ離れているように見えるかもしれない。しかし、「占領期」は「戦後」なのか、と問いかけ、戦争が続いていたとする西川の「占領」に対する認識は、拙論にも通底するものである。西川は自身の記憶の検証からは始めて膨大な行政文書や資料を分析し、占領下の京都を生きた80人への聞き取り調査から、その生活を浮かび上がらせた。たとえば、米軍が京都で起こした事故に対する補償の切実な訴えを記録した行政文書からは、犠牲者たちへの暴力と生活を読み解くだけでなく、さらに事故現場を地図に書き入れて、占領軍の動線を可視化していく。それらの新しい手法や問いには、学ぶことがとても多い。日本の占領が、ことあるごとに「よい占領」として持ち出される世界情勢の中で、「よい占領などない」と言い切る西川の基本的視点は、重要である。
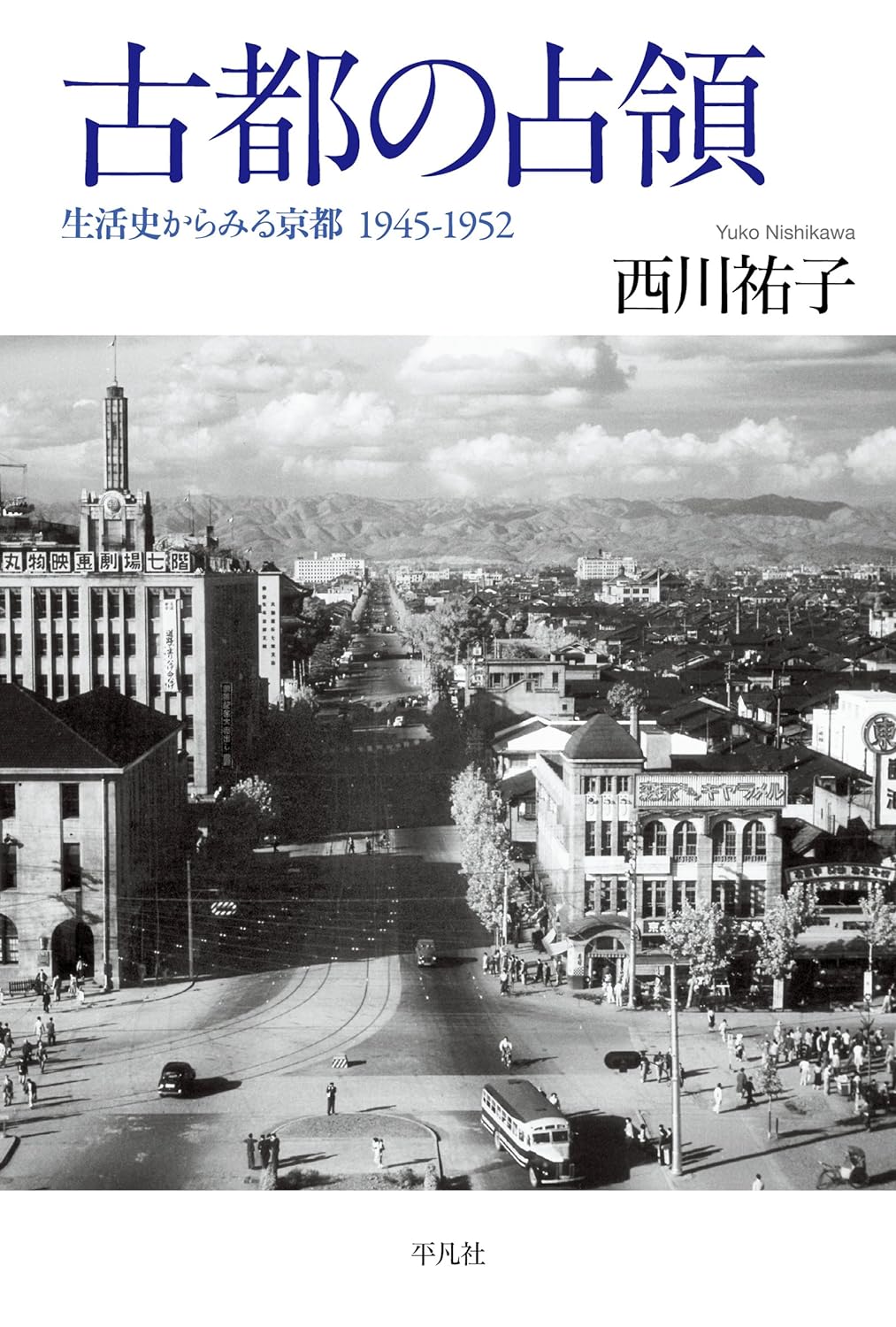
吉見俊哉『カルチュラル・ターン、文化の政治学へ』(人文書院、2003年)
天皇制と視覚イメージについては、戦後早くから卓抜な分析を行ってきた鶴見良行や、フーコーの権力論を参照したT.フジタニ、明治天皇の真影の歴史を書いた多木浩二、さらに従来の研究が天皇や男性皇族に偏るとして、皇后の表象分析を試みた若桑みどりなど、数多の研究が重ねられてきた。同書のなかの「メディア天皇制とカルチュラル・スタディーズの射程」は、「近代天皇制を、ネーションワイドなメディア・テクノロジーに媒介され、天皇の身体に焦点化されるヘゲモニックな言説の受容/消費のシステムとして把握し直す」ことを提起した。吉見の言うように、天皇制は、戦前期の一時的な国家機構にすぎないわけでも、「日本文化」の深層構造として実体的に存在しているわけでもないのである。
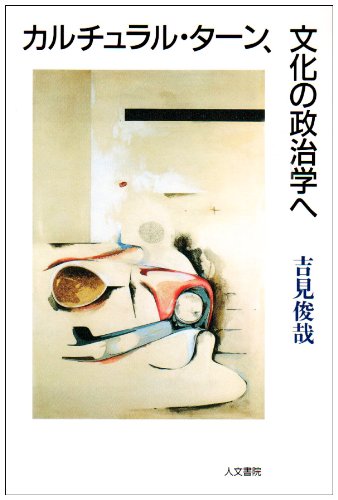
Judith Williamson, Decording Advertisements, 1978.ジュディス・ウィリアムスン『広告の記号論I・II』(山崎カヲル・三神弘子訳、柘植書房、1985年)
御前会議の絵画については、先行研究の乏しい領域なので、最後の1冊を何にするか、悩んだ。当初はグリゼルダ・ポロックの書籍を取り上げようと思ったのだが、ほかにも推薦する人はいるだろうからやめた。そこで古い本だが、英国の文化理論研究者のジュディス・ウィリアムスン『広告の記号論』を紹介することにする。これは私が視覚表象の面白さと政治性に魅了され始めた頃、ビジュアル分析の仕方やその意味について具体的に教えてくれた一冊である。彼女は言う――センセーショナルな広告の放つ「メッセージ」に目を奪われるのではなく、また、広告をその背後にひかえている「メッセージ」を伝えるための透明な媒体にすぎないと考えるのでもなく、その広告を受け入れることが、そこに含まれたイデオロギーや社会習慣を受け入れることであり、それらの再生産に参加することだということ。では、「広告」を絵画や美術に置き換えてみると、どうなるか。
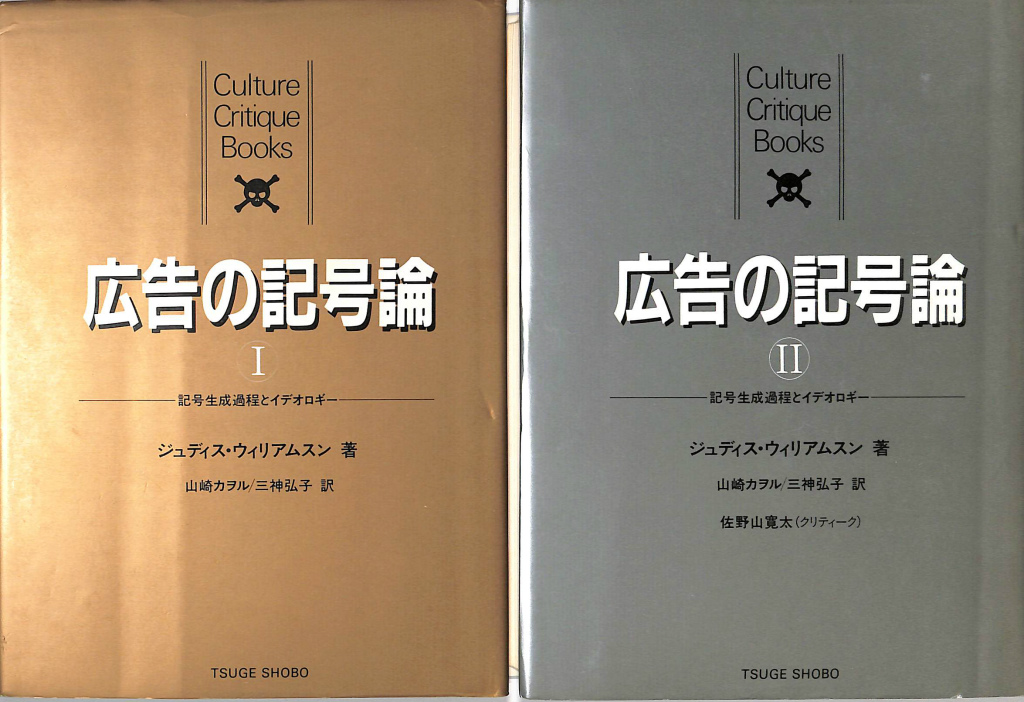
琴 仙姫
金 東椿『朝鮮戦争の社会史――避難・占領・虐殺』(金 美恵訳、平凡社、2008年)
朝鮮戦争について学ぶ際の必読書。教科書の歴史よりずっとおぞましい殺し合いがなされていたことなど、他の本では触れられなかったことが書かれている。
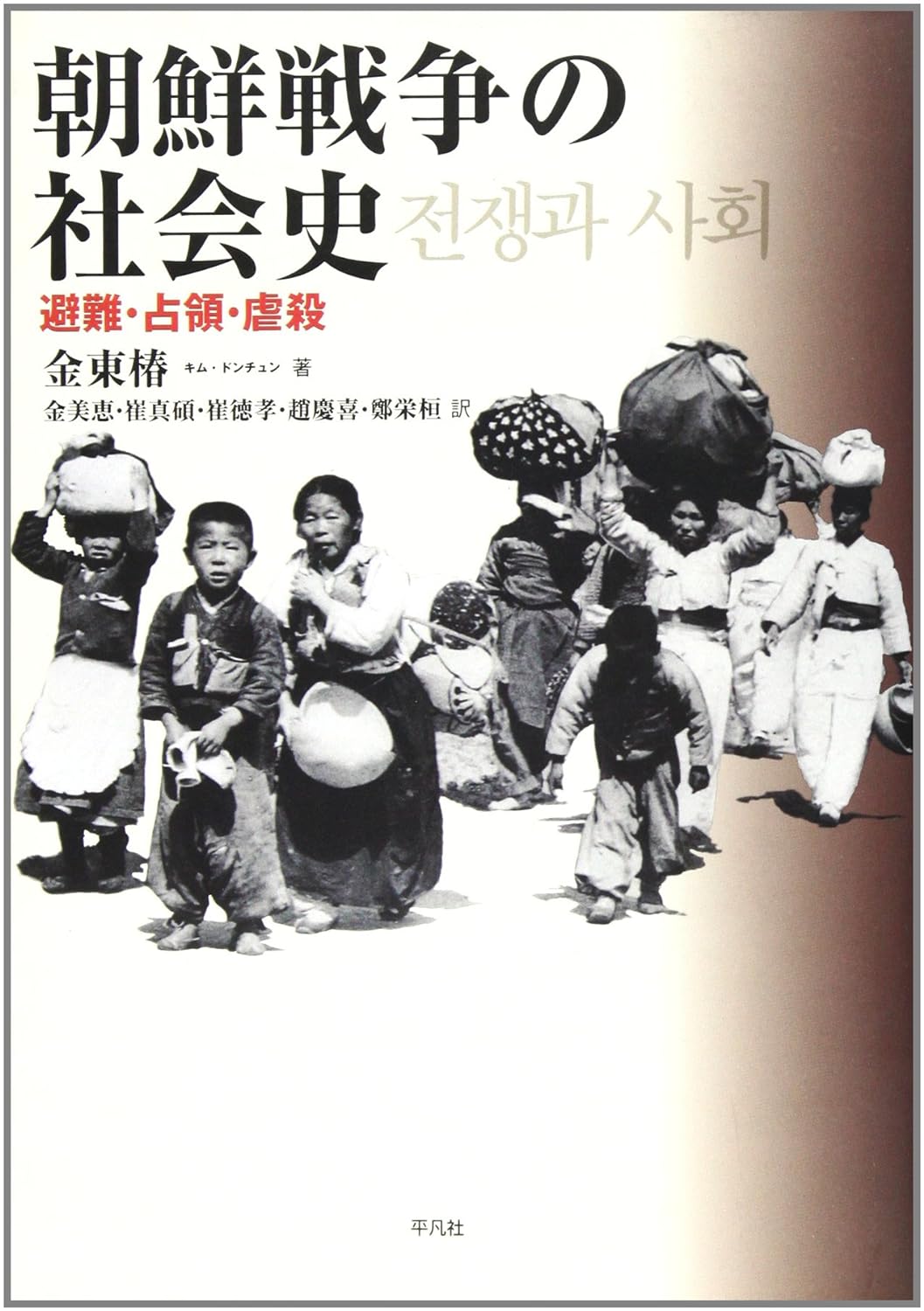
Patrick Williams , Laura Chrisman. Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader , Columbia University Press, (1994)
アメリカの修士課程でポストコロニアル・セオリー に出会った時に持ち歩きながら読んでいた本。様々なポストコロニアル論の重要な論文が収録されている。フランツファノンやサイードの文章を読んだときの衝撃と興奮が記憶に残っている。ポストコロニアル論を学んで見たい人々の入門書としておすすめできる本。
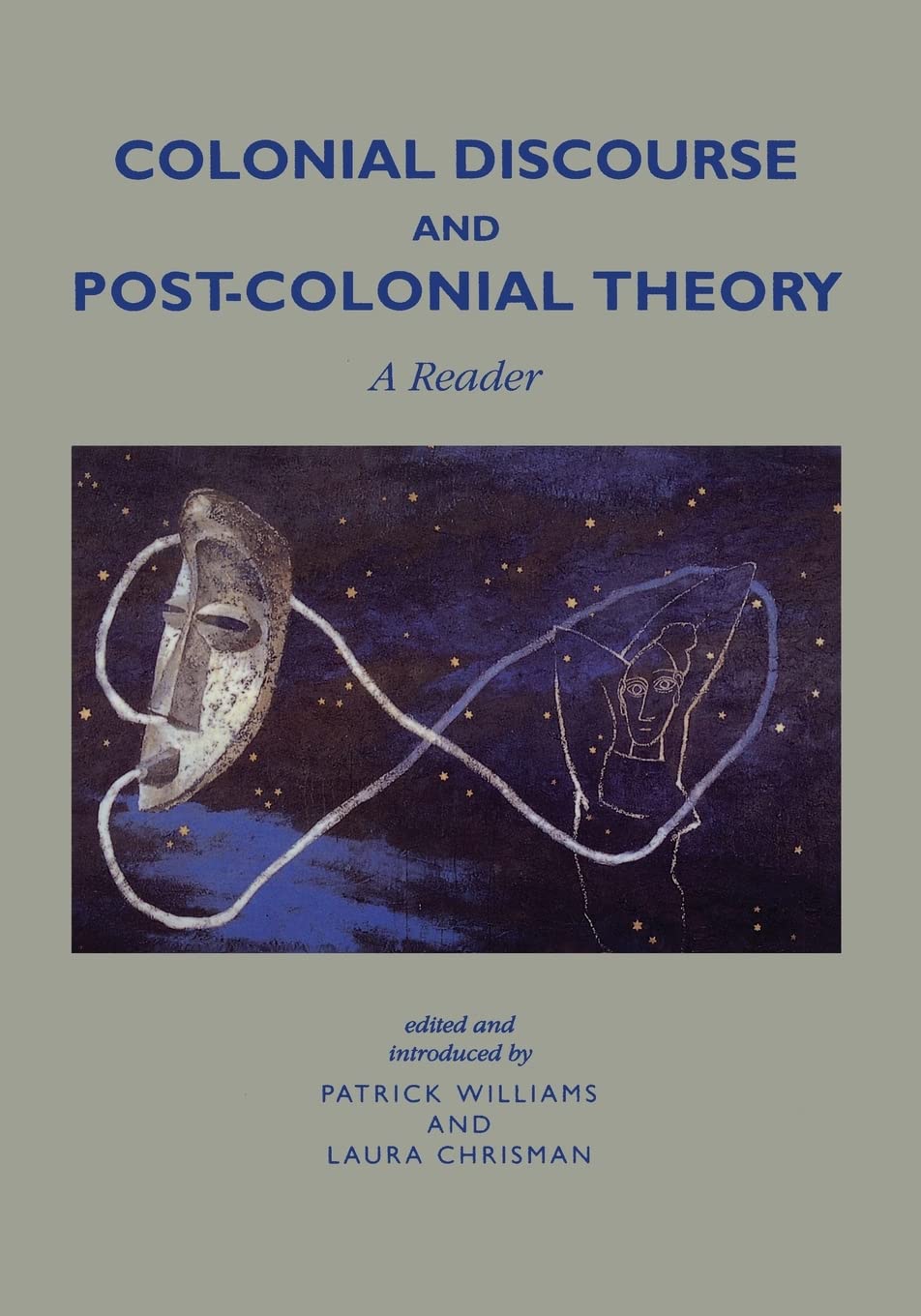
Abdulrazak Gurnah, Paradise
ポストコロニアル論でよく批判的に取り上げられる Joseph Conradの小説 Heart of Darknessに描かれているヨーロッパからの入植者からの単一的な視点ではなく、当時のアフリカの人々の生活が一人の少年の人生を辿ることで描かれている。衝撃的な読書体験。
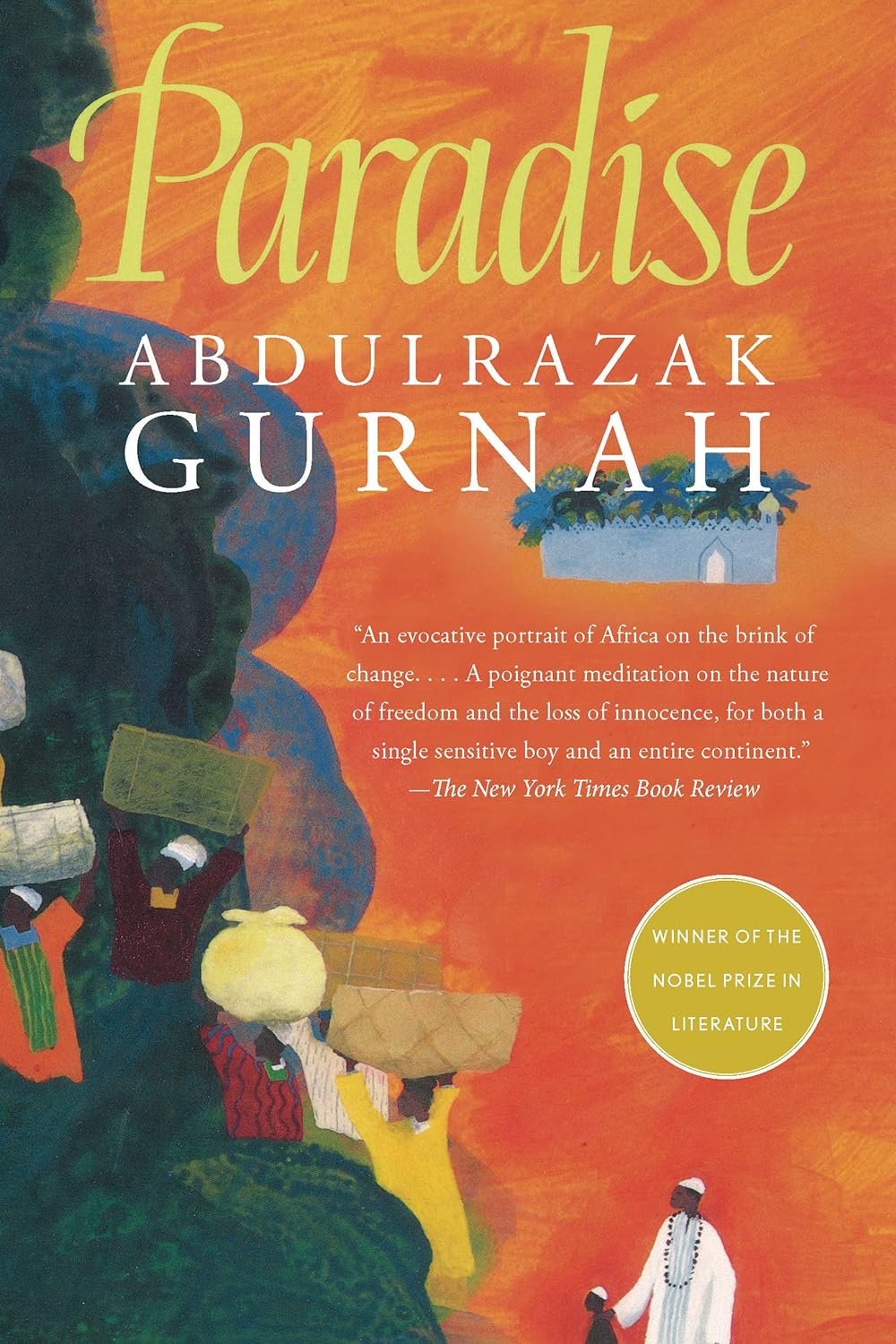
吉良智子
加納実紀代『新装版 女たちの〈銃後〉 増補新版』(インパクト出版会、2020/初版1987年)
に刊行された後、1995年、そして2020年と三度増補をして出版されている本書は、アジア太平洋戦争期の日本女性たちが実は戦争を支持し支えていたことをインタビューや日記の分析などを通して読み手に伝えます。教科書に出てくる戦争に翻弄される女性たちというイメージが覆されます。
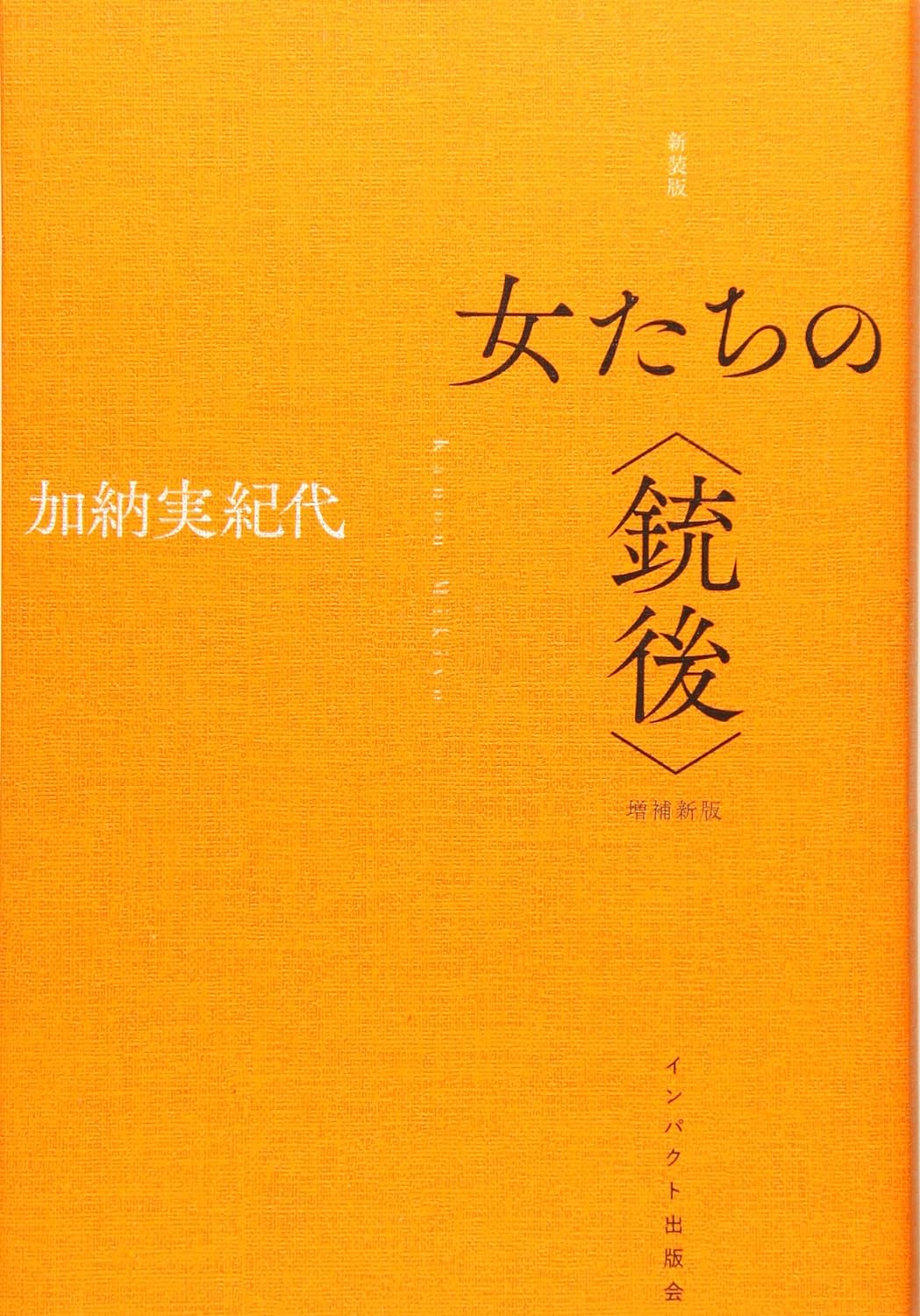
若桑みどり『戦争がつくる女性像――第二次世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』 (ちくま学芸文庫、 2000/初版1995年)
に刊行された書籍の文庫版。第二次世界大戦期の『主婦之友』の表紙絵や口絵を分析し、女性に求められた役割が母性にあったことを解き明かしています。私が博士論文の執筆でくじけそうになったときに、何度も読み返しました。

『千野香織著作集』(千野香織著作集編集委員会編、ブリュッケ、2010年)
日本におけるジェンダー美術史の先駆者にひとりだった著者の論文集。論文は年代順に並べられていて著者の関心の変化や思考の広がりがわかります。まずは目次を見て興味があるところから読んでほしいです。誰にでもわかりやすい表現でジェンダーやフェミニズムの視点から論じようとした著者から私たちへの希望のメッセージがつまっています。

小金沢 智
山下裕二『日本美術の20世紀』(晶文社、2003 年)
日本美術史における作家・作品の価値の変転をめぐる一冊。まえがきの「私自身が日本美術に注ぐ視線も、日々変化している。他の人だって、そうだと思う。問題なのは、その変化を認めない、認めたくない、というメンタリティーなのだ」(36頁)という言葉は、刊行当時(学生時代)に読んで20年が経った今だからこそ、突きつけられる重みがあると感じています。
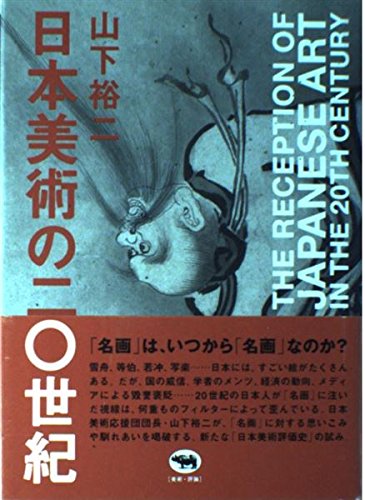
『東北画は可能か?』(監修:三瀬夏之介 ・鴻崎正武、美術出版社、2022 年)
2009 年から2022 年の活動をまとめた「東北画は可能か?」作品集。私は各セクションおよび各作品の解説を書い ているのですが、特に注目していただきたいのが学生の頃から関わっているメンバー3名(渡辺綾、石原葉、富永和 輝)による座談会。活動に参加する中での実体験に基づく言葉の数々は、大学という教育現場を母体として行われて いる「東北画は可能か?」のなまなましい実態の一側面を伝えるものでもあります。

『「たえて日本画のなかりせば:上野恩賜公園篇」記録集』(パラレルモダンワークショップ、2022 年)
2021 年6月5日、パラレルモダンワークショップの18組20名が上野恩賜公園各所にて行った「たえて日本画のなかりせば:上野恩賜公園篇」記録集です。当日のアクションについてのそれぞれの書き下ろしテキスト、記録写真(鈴木一成、西澤諭志、吉江淳)を、デザイナーの丸山晶崇さんが各作家の活動のタイムラインに沿ってレイアウト。巻末には私の解題もあり、本プロジェクトの全貌をドキュメントしています。手製本による限定300 冊。

小泉明郎
原武史『完本 皇居前広場』(文春学藝ライブラリー、2014年)
今日神聖な雰囲気がありますが、かつてカップルが夜に消えていく場所だったというのは衝撃です。

デーヴ・グロスマン『戦争における「人殺し」の心理学』(安原和見訳、ちくま学芸文庫、2004年)
人間は目の前にいる他人を殺すことができない戦争に向いていない動物であることがわかる本です。
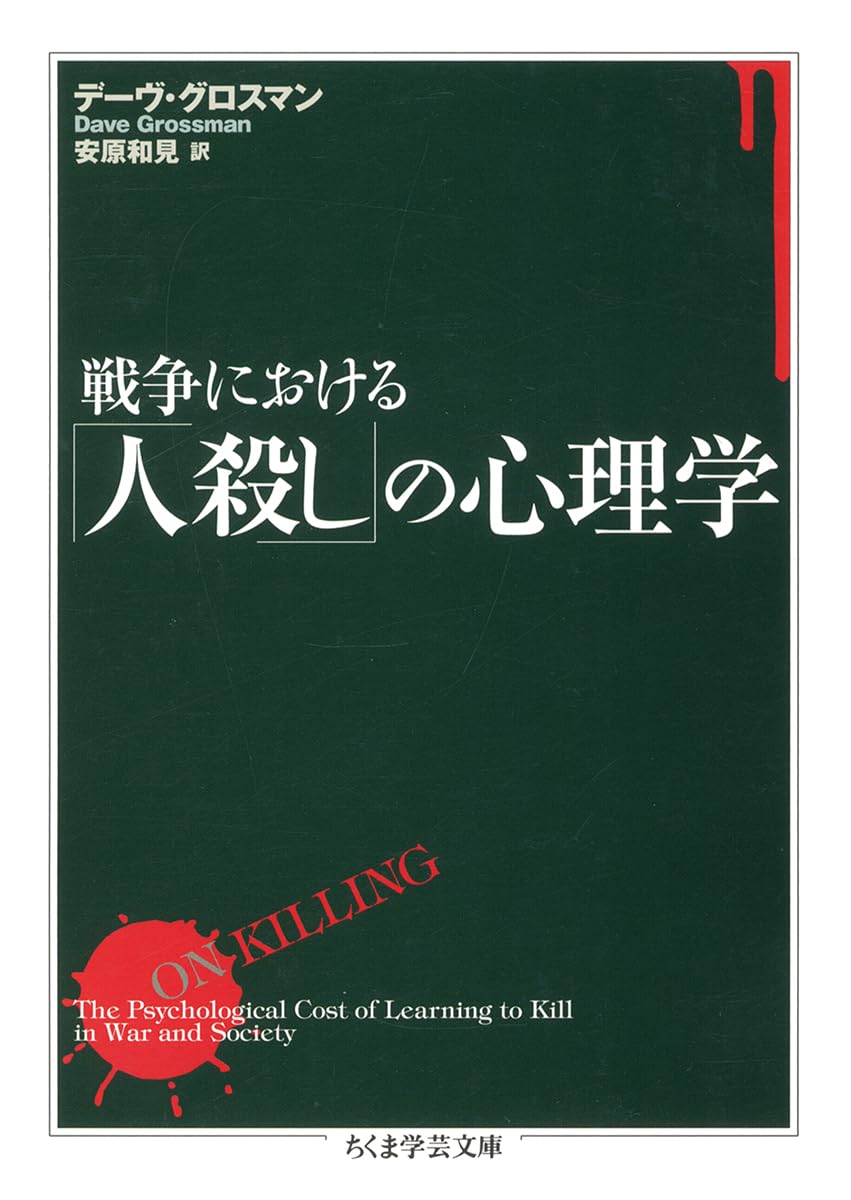
ギュスターヴ・ル・ボン『群衆心理』(桜井成夫訳、講談社学術文庫、1993年)
この本が書かれた19世紀末にはすでに分かっていた人間の浅はかさが、100年経った今でも克服できていない。

菊池裕子
Yuko Kikuchi ed., Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan, Honolulu: University of Hawai‘i Pres, 2007.
英語、日本語出版共に植民地台灣における「工芸」の視覚文化の広いコンテクストが共同研究されたものは未だ少ないため、筆者編のこの本を薦める。現在、台灣において20世紀末になって大学のカリキュラムとして創られた台灣史、台灣美術・視覚文化史、台灣建築史、台灣文化人類学の創始者たちと日本人研究者により複雑なcolonial modernity (植民地下の近代)の様相をうかがい知ることができる。例えば「郷土」や「南国」という日本帝国が生み出す概念が植民地下の政治・文化を介して大衆の台灣意識として浸透し人種と視覚文化を直結していく過程が理解できる。
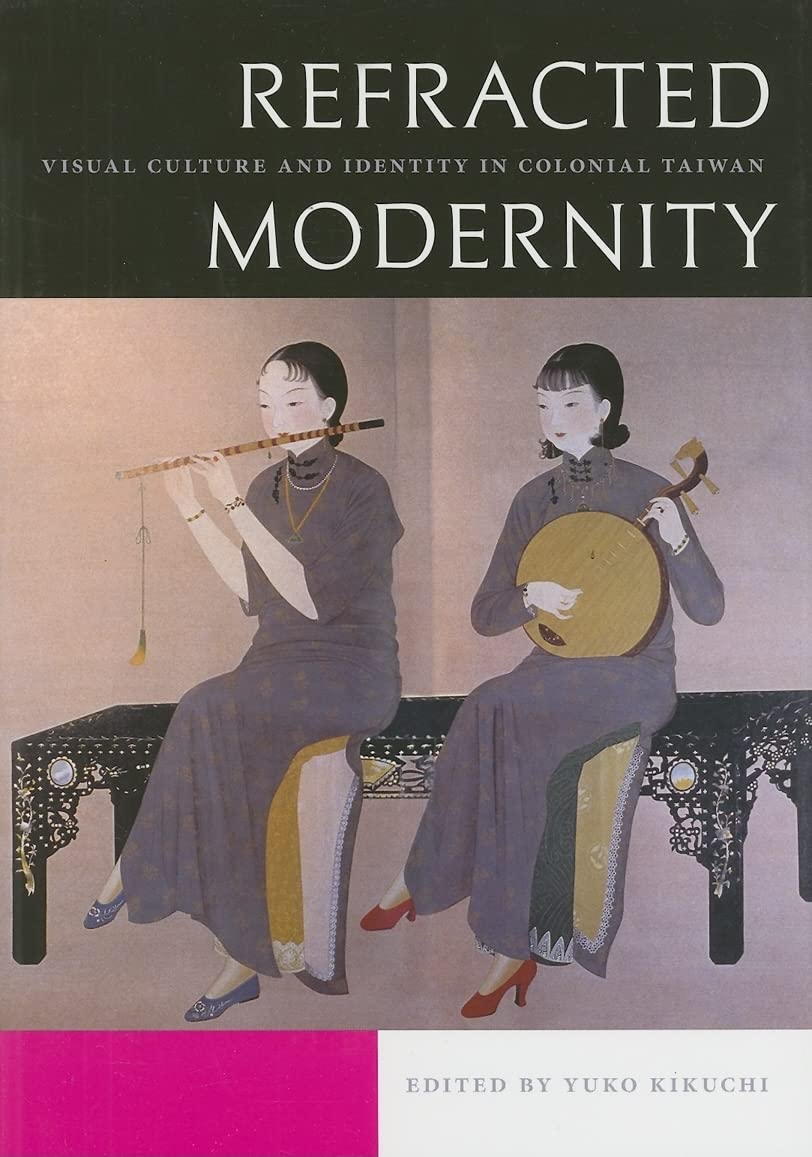
山崎明子『近代日本の「手芸」とジェンダー』(世織書房、2005年)
この分野では最も重要なテキストであるRozsika ParkerのThe Subversive Stich (1984)は未だ邦訳がなく残念だが、山崎はそれを先行研究として日本の近代が制度化した家父長制と労働の階層化の中で「手芸」という分野が創り上げられていく過程を追う。「手芸」が周縁化されていく過程は日本において特殊ではなく近代化と国家創設というグローバルな動向の中で行われた視覚文化のジェンダー化を共有し、本書の中心を占める例証研究において英国留学後に下田歌子の生み出した「婦徳」という概念が日本帝国版への文化翻訳として提示されるのが興味深い。
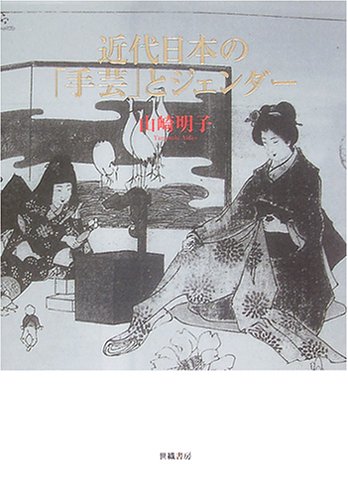
北澤憲昭『アヴァンギャルド以後の工芸 ――「工芸的なるもの」をもとめて』(美学出版、2003年)
北澤憲昭は佐藤道信と共に近代日本における「美術」というものの制度と境界概念を問題にし多くの著作があるが、本書は北澤の「工芸的なるもの」という表現により、周縁化され混沌としてまとまりのない要素に注目する。モダニズム美術が再生し「進歩」するために必須としてきたアヴァンギャルド概念が現代芸術において終焉した後に残された「工芸」の中から「工芸的なるもの」を凝視し評価し実践することで「近代」の思考を解体する可能性をみつけることを示唆する。現在、特に永米圏で日本よりさかんに議論されている現代工芸論と共鳴するものがある。
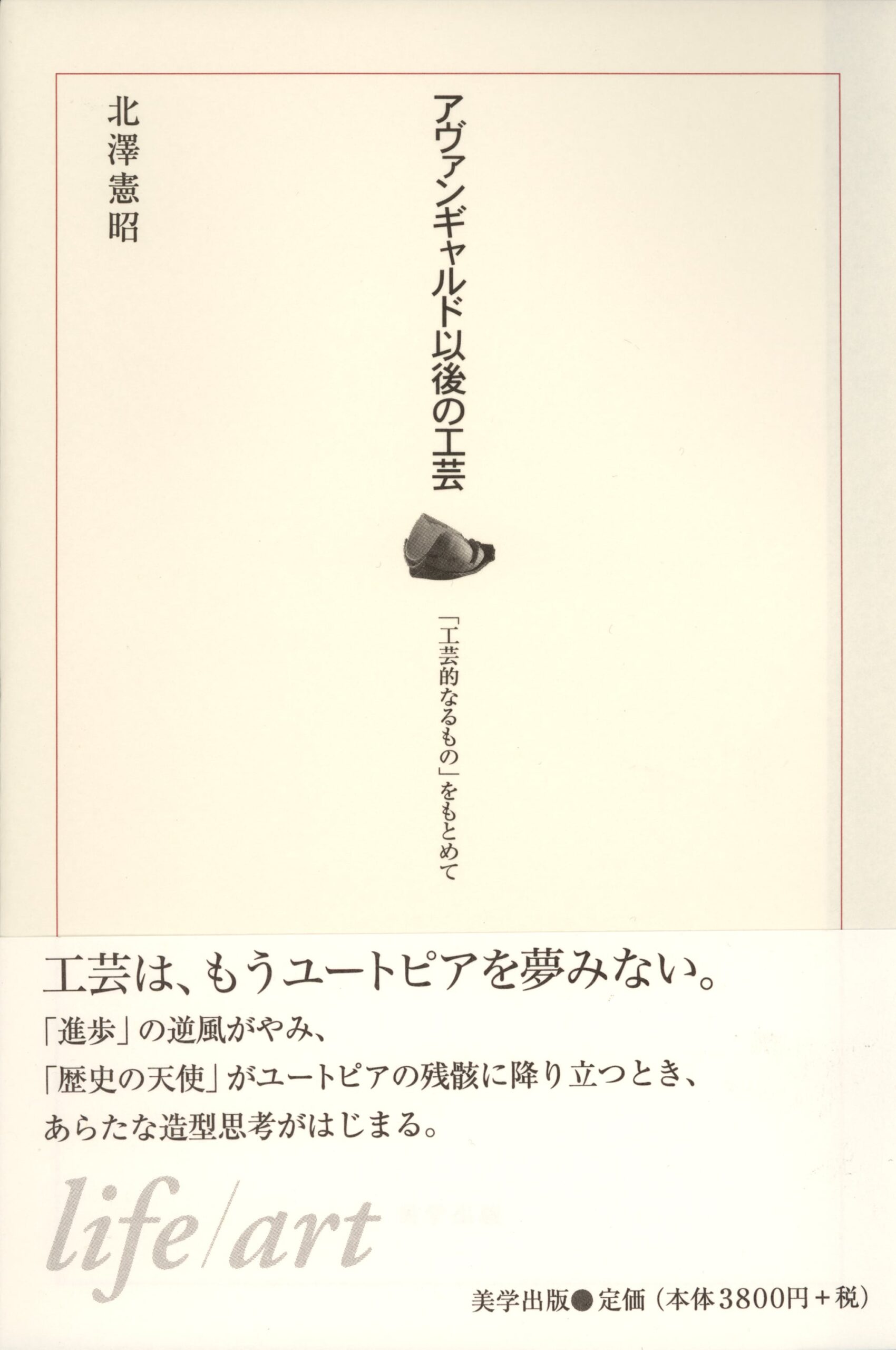
馬 定延
Stuart Comer, Michelle Kuo (eds.), SIGNALS: How Video Transformed the World (exh.cat), The Museum of Modern Art, New York, 2023.
「権力はもはや土地、労働力、資本ではなく、情報へのアクセスとそれを広める手段によって測られる。」一九七〇年、雑誌『Radical Software』は、ビデオという新しい映像メディアに内在する政治性にいち早く着目して、このように宣言した。ニューヨーク近代美術館の映像作品コレクションを中心にする同名の展覧会の企画者でもある二人の編者は、参加、連帯、情報の民主化を夢見た二〇世紀後半の芸術的実践と革命的思想の系譜が、二〇二〇年代の時点では「過去」のものになってしまったことを否定はしないが、ブラック・ライブズ・マター、ウクライナとロシアの戦争のような同時代の社会問題に取り組み、世界をより良い場所へと変えていくために、私たちの時代の「信号」を発信する方法論を学ぶことができると提案している。

與那覇潤『帝国の残影――兵士・小津安二郎の昭和史』(文藝春秋、2022年/初版、NTT出版、2011年)
「いちばん日本的だと日本人が思っている映画監督」とも評される小津安二郎の人生と映画に存在する「欠落」と「混淆性」を通じて、「昭和」と「戦争」という近代史をめぐる日本の歴史語りを批判的に考察する。文化史と帝国史の方法論を意識しつつ、映画批評と作家論という異分野に越境する気鋭の歴史学者が、類例を見ない知的な刺激に溢れる思考の旅に読者を招いていく。単行本が文庫化にあたり、二〇二一年に豊田市美術館で開催された、ホーツーニェンの個展「百鬼夜行」のカタログのために書かれた「入れ替わることと一つになること ほー・ツーニェンの歴史実践」を含む増補記事が収録された。
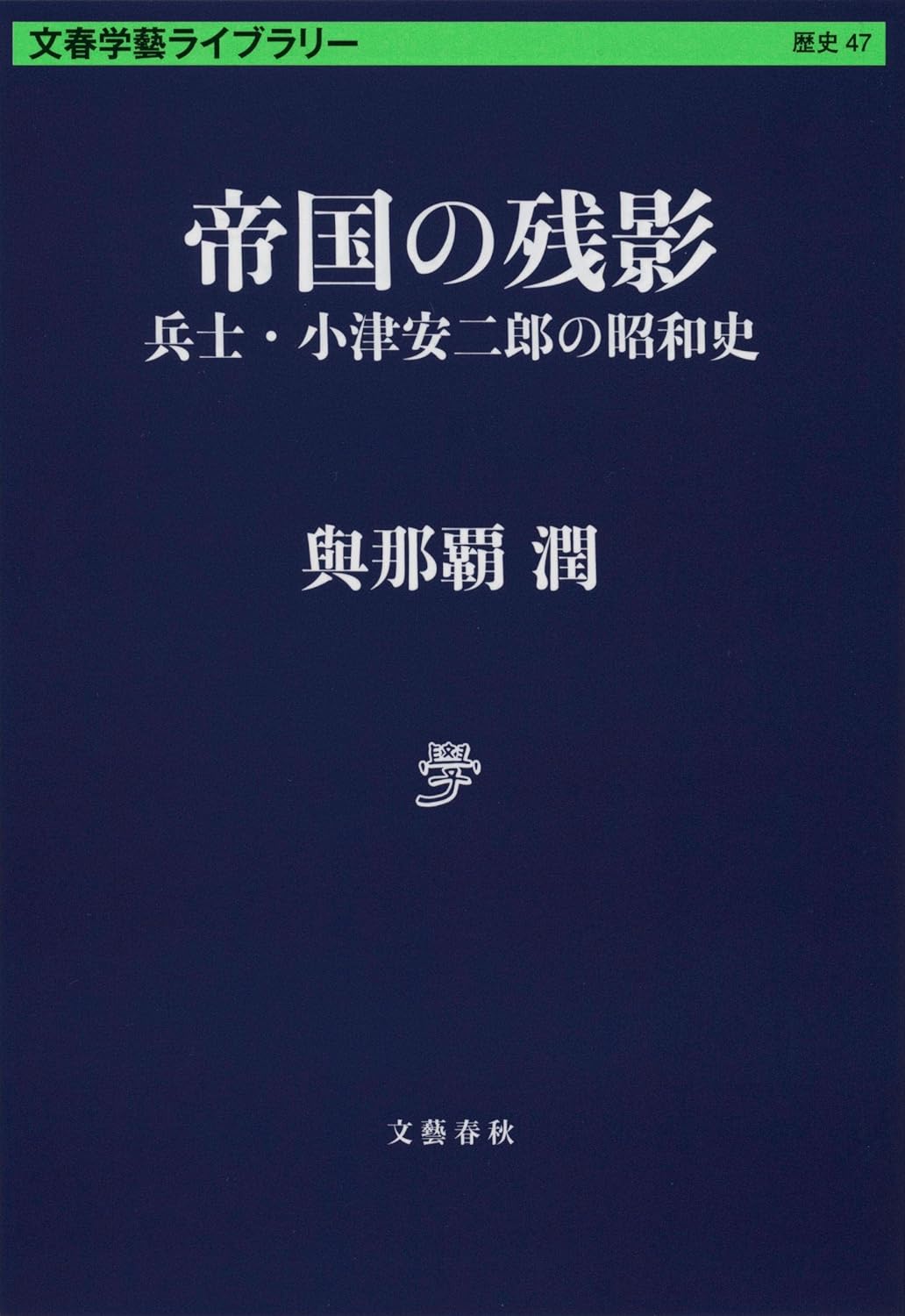
吉見俊哉編著『一九三〇年代のメディアと身体』(青弓社、2002年)
「さまざまな知が戦争に向けての動員体制へとつぎつぎにのみこまれていった」一九三〇年代を問題する議論の変遷が、その後の半世紀間にわたり、各時代の異なる視角を反映する「鏡」のようや意味をもっていたと、編著者の吉見は指摘した。六人の研究者が総力戦、宣伝、観光、メディア、口演、放送というテーマに焦点をあてて、一九三〇年代という「暗い過去」を考察するこの本は、いまは過去となった二〇〇二年という当時の「現在」を把握する手がかりとなる。それから約二〇年が経過した二〇二三年に刊行される『この国』という本が、「芸術」という切り口で歴史を反省的に振り返り、「現在」を照らし出す「鏡」として参照されることを願う。

富澤ケイ愛理子
Mary Louis Pratt. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. 2nd Edition. (Routledge, 2007)
本書の日本語訳出版が期待されています。『コンタクトゾーン』(しばしば異なる文化間の相互理解や誤解、交渉、および権力関係の研究に使用)の提唱者であるプラットの著書。植民地時代の帝国主義とトランスカルチャーという大きな文脈の中で、旅行記がどのような役割を果たしていたかを批判的に分析しています。
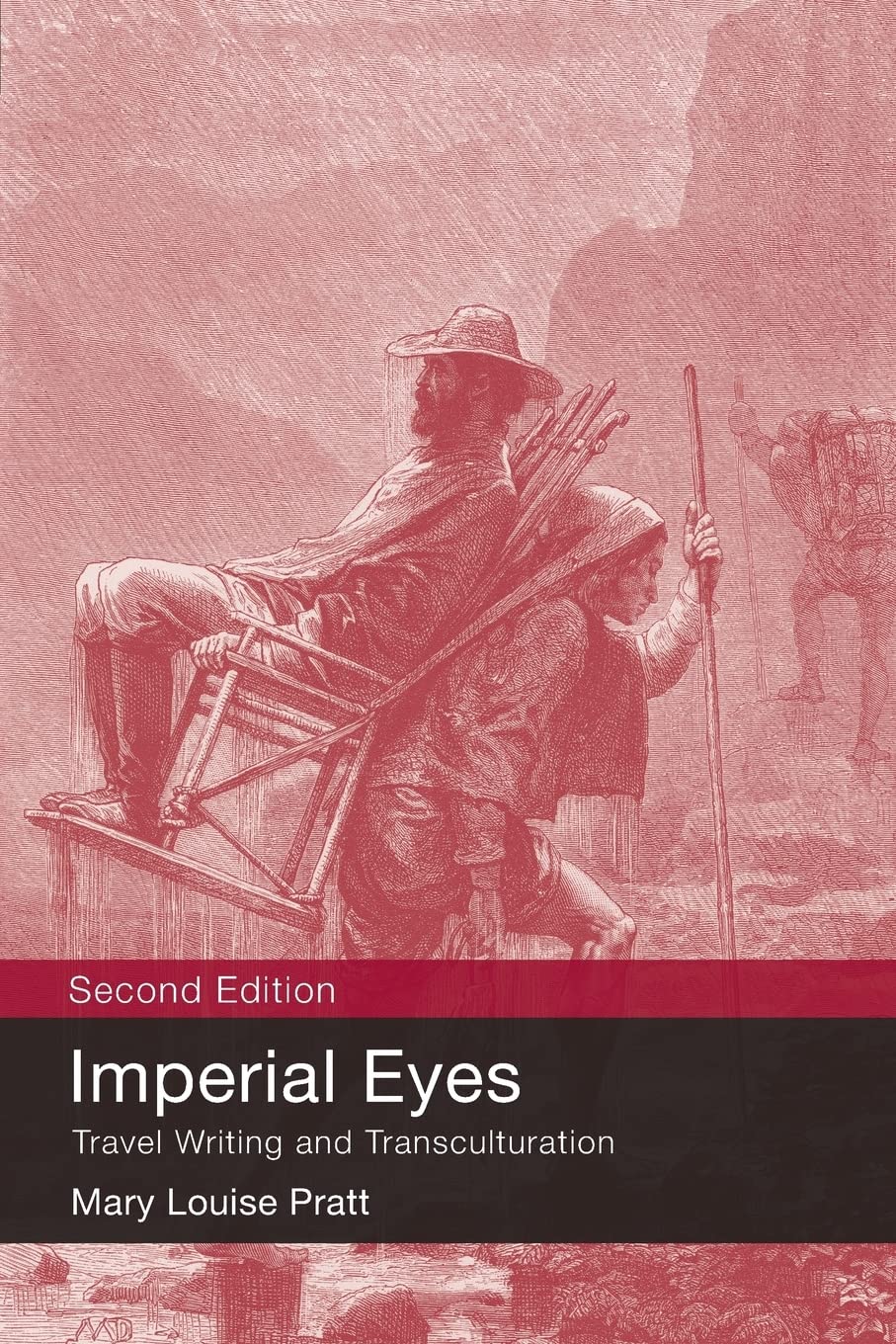
翁長直樹『沖縄美術論――境界の表現 1872–2022』(沖縄タイムス社、2023年)
は、近現代沖縄美術史と沖縄の代表的なアーティストについて知識を得たい読者にとって必読の一冊です。第一部は「沖縄・美術の流れ」に焦点を当てており、沖縄美術の進化と変遷について探求しています。第二部は「作家論」に捧げられており、特定のアーティストたちに焦点を当ててその作品と貢献について論じています。ただし、作家論のセクションでは、字数の関係から著者が探究できるアーティストの数に制限があったため、本書に収録されていない多くの優れたアーティストが沖縄には存在することも理解が必要です。
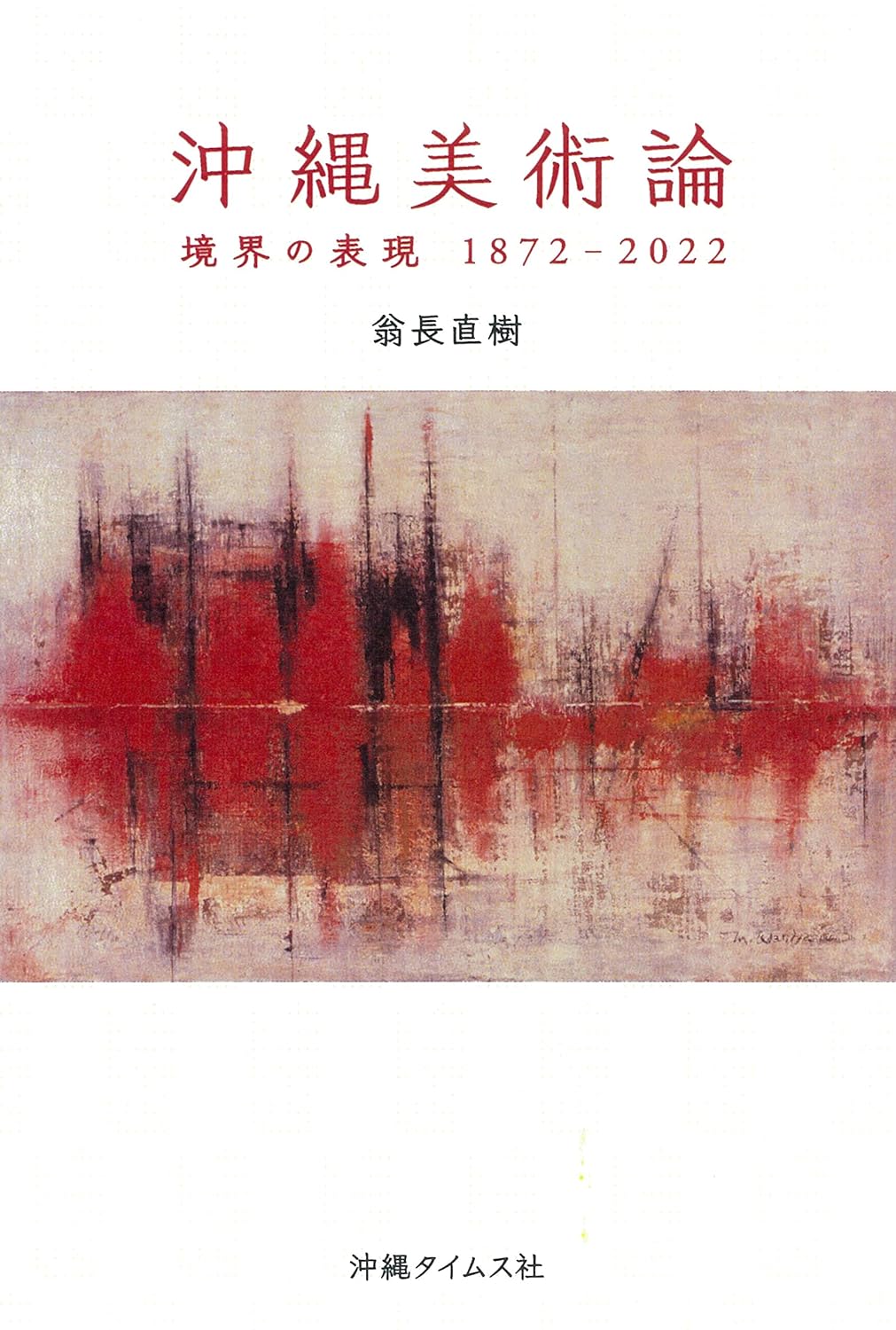
古田亮・北澤憲昭 編『日本画の所在――東アジアの視点から』(勉誠出版、2020年)
は、《日本画》の概念、画材、政治性、および可能性等について、多角的なアプローチを用いて論じる一連の学術論文が掲載されています。これらの論文は、脱中心化とトランスナショナルな視点で、《日本画》に関する新たな理解を提供しています。本書は、東アジアにおける《日本画》の受容と将来の展望についても充実した情報を提供しており、興味深い洞察が得られるはずです。

吉國 元
村松武司『海のタリョン―村松武司著作集』(皓星社、1994年)
「朝鮮の文学には、旧支配者の影がみちている。逆に日本の文学について考えた場合、朝鮮の影は薄い」(『朝鮮植民者―ある明治人の生涯』1972年)と書いた村松武司は、植民地朝鮮で生まれ育った植民者としての自己と生涯向き合い、一貫してそれについて書き、掘り下げました。僕としては特に、『遥かなる故郷―ライと朝鮮と文学』の「黒いゲーム」にある、13歳の村松が、村松家で住み込みの「丁稚」として働いていた朝鮮人少年と一緒にお風呂に入る挿話に注目したいです。そこから展開する朝鮮人少年のその後と、村松の回想を読んでほしいです。

山本めゆ『「名誉白人」の百年 南アフリカのアジア系住民をめぐる エスノ-人種ポリティクス』(新曜社、2022年)
ガーナ大学におけるガンディー像の撤去にはじまる本書は、南アフリカにおけるアジア系移民の人種的地位と経験を細やかに検討した優れた研究です。とりわけ、日本人駐在員の妻と、その家に雇われている現地の家事労働者の女性(ドメスティックワーカー、メイド)の交流を示すひとつの挿話が興味深かったです。そのひとつに、「桜を見たい」と言ったメイドの女性を、日本に招待した夫妻の証言があり、はるばる桜を見るために渡日した南アフリカ人女性との邂逅のシーンが目に浮かびます。山本は、このような女性たちの実践を、「外交や貿易関係とは異なるオルタナティブな」「女性たちよるささやかな」「反アパルトヘイト」としています。
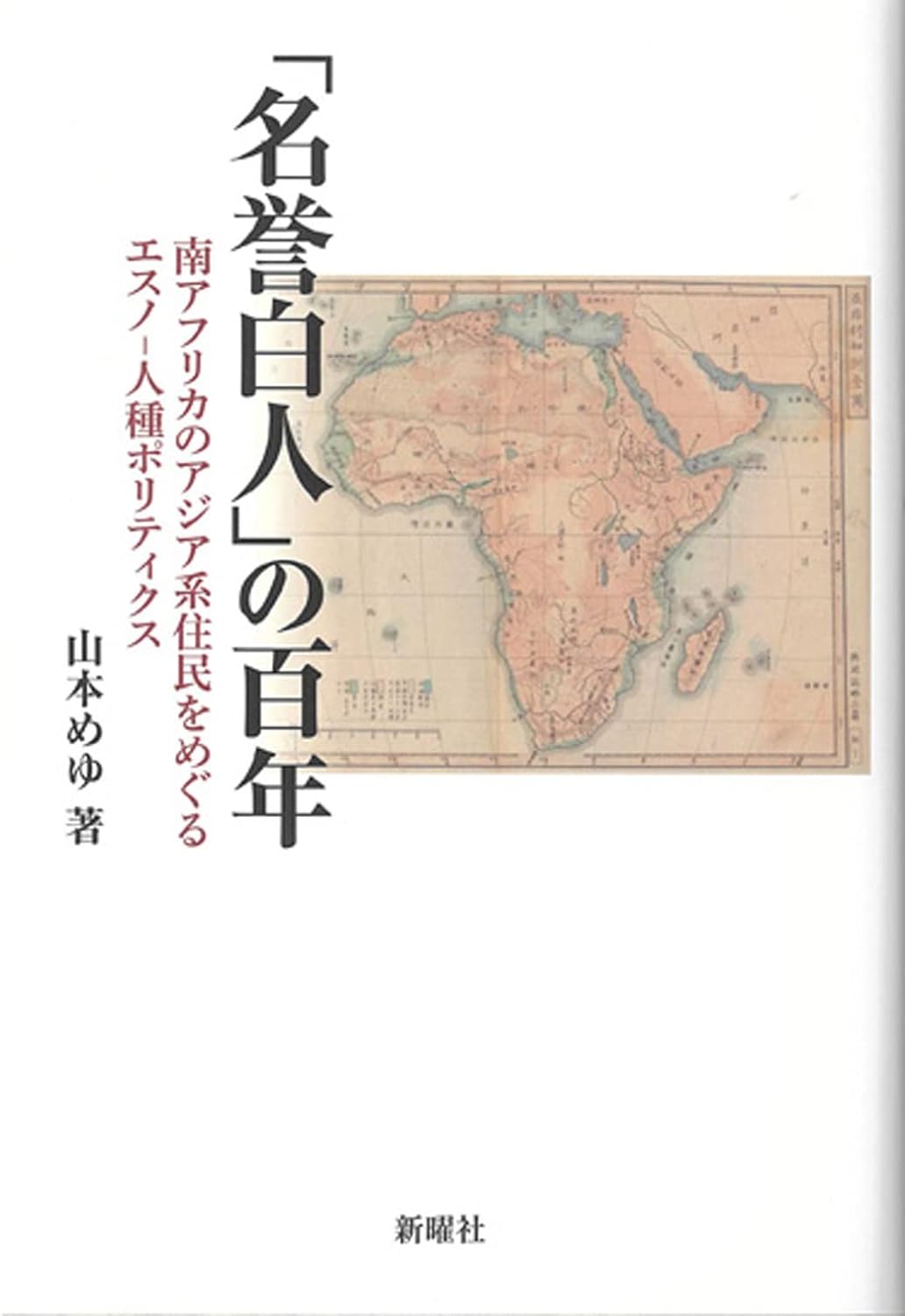
ペティナ・ガッパ『イースタリーのエレジー』(小川高義訳、新潮クレスト・ブックス、2013年)
「独立の英雄」ロバート・ムガベ前大統領の死は、ネットの報道で知りました。父はすでに亡くなっていて、これでジンバブエにおけるひとつの時代が終わったのだろうかと、その時は思いました。本書にある短編「軍曹ラッパが鳴り終えて」は、ジンバブエ政府高官であった夫の葬儀を未亡人となった妻の視点で書いたもので、「公式な真実だけが真実だ。それだけが歴史の本に残って子供に教えられる」という妻の苦い認識が記述されています。しかし、この言葉にはガッパの「実際はそうではないはずだ」という想いも込められていて、祖国において、語られない、書かれない、声にならない声を掬い取ろうとする作者の決意が刻まれています。

小田原のどか
『なぜ戦争をえがくのか:戦争を知らない表現者たちの歴史実践』(みずき書林、2021年)
こちらの本には私のインタビューも収録されています。本をつくることについて、ひとり出版社の未来について、みずき書林代表・岡田林太郎さんの昨年のご逝去にふれ、多くを考えさせられました。本書が長く読まれることで、岡田さんの本づくりへの思いが受け継がれていくだろうと信じています。
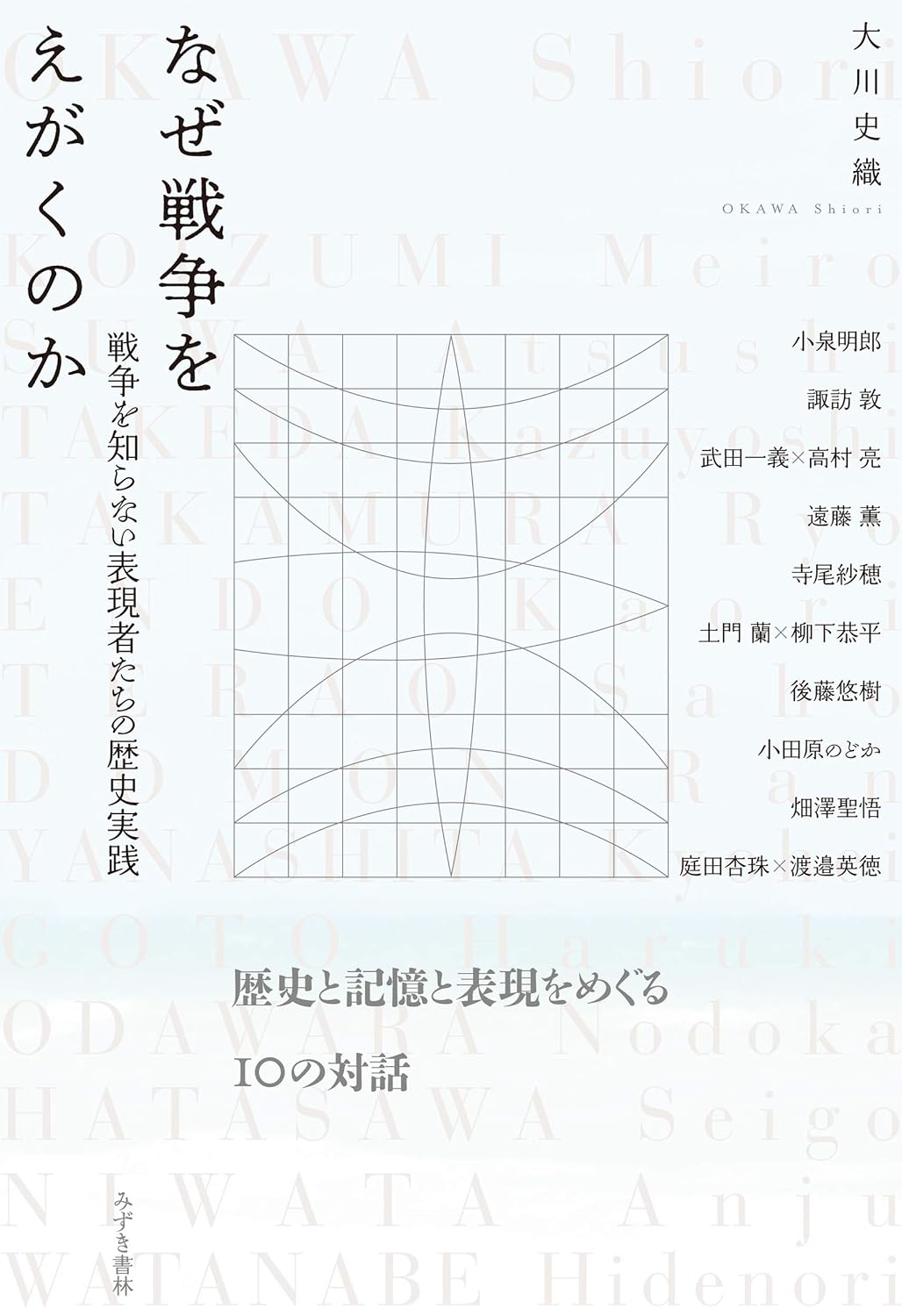
ベル・フックス『アート・オン・マイ・マインド:アフリカ系アメリカ人芸術における人種・ジェンダー・階級』(杉山直子訳、三元社、2012年)
『この国(近代日本)の芸術』の「はじめに」は、この本の引用から始めました。ベル・フックスが書いたもの、その存在そのものが、私にとって大きな指針です。ぜひ『この国(近代日本)の芸術』と合わせて読んでいただきたいです。
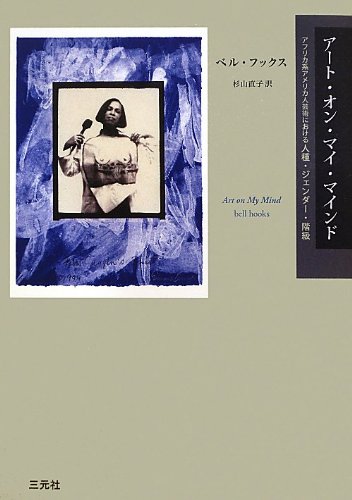
『千野香織著作集』(千野香織著作集編集委員会編、ブリュッケ、2010年)
どうにかして再版してほしい一冊です。千野さんのご研究の視座は、日本美術史の脱帝国主義化に欠かせないものです。

山本浩貴
白凛『在日朝鮮人美術史1945-1962──美術家たちの表現活動の記録』(明石書店、2021年)
エスニック・マイノリティの芸術表現は、戦後、国民国家という「想像の共同体」(ベネディクト・アンダーソン)を自明の前提とした美術史という学問分野で優勢となっているナショナルな枠組みのなかで見過ごされてきた。さらに悪い場合、かつての帝国の負の歴史としての植民地支配を忘却しようとする「国家」と「国民」の共謀のなかで意図的に「消失」させられてきた歴史もある。日本というコンテクストにおいては、その際立った一例が在日コリアン美術の歴史の周縁化である。本書『在日朝鮮人美術史 1945–1962──美術家たちの表現活動の記録』(2021年、明石書店)の上梓や、在日朝鮮人の芸術・文化の保存を目的とする「一般社団法人在日コリアン美術作品保存協会」の創設などに代表される、在日朝鮮人美術史を専門とする美術史家・白凛(ペク・ルン)の近年の仕事は、この盲点・消失点に果敢に挑み、その暗がりに新しい光を投じていくという重大な意義を有する。
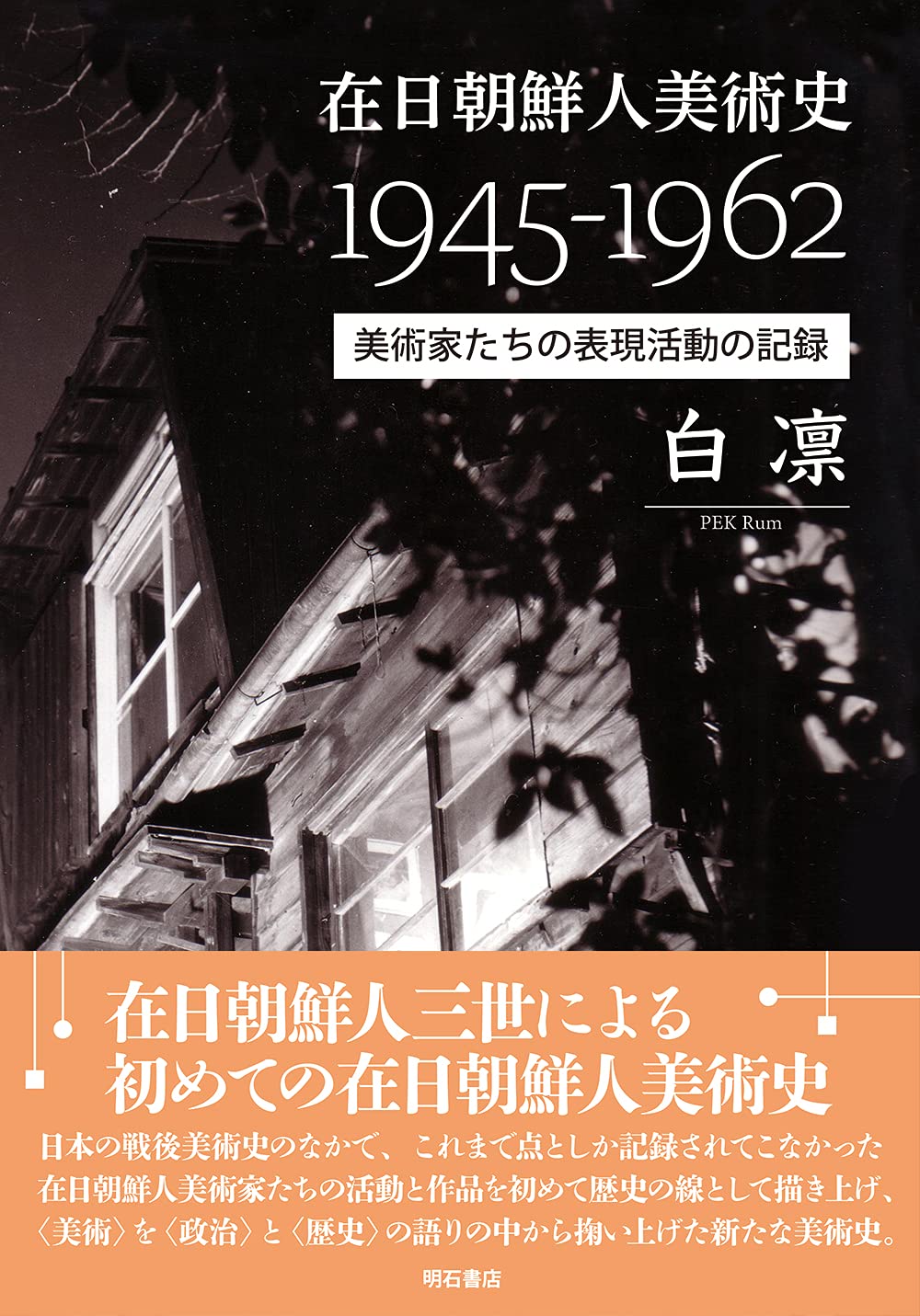
黒ダライ児『肉体のアナーキズム──1960年代・日本美術におけるパフォーマンスの地下水脈』(グラムブックス、2010年)
日本美術史のなかで長らく周縁化されてきた、戦後に勃興したパフォーマンス・アーティストたちの政治的芸術実践の軌跡を黒ダライ児独自の視点も交えて記している。芸術がその特異性と保持しながら、なお政治的コンテクストと不可分に絡み合う様相が独特のスタイルと口調で生き生きと描き出されている。なぜこうした美術史の一部がそれまでのナラティブから排除されてきたのかを考えると同時に、なぜ本書には女性作家の登場が少ないのかということについても、真剣な考察に値するトピックだろう。
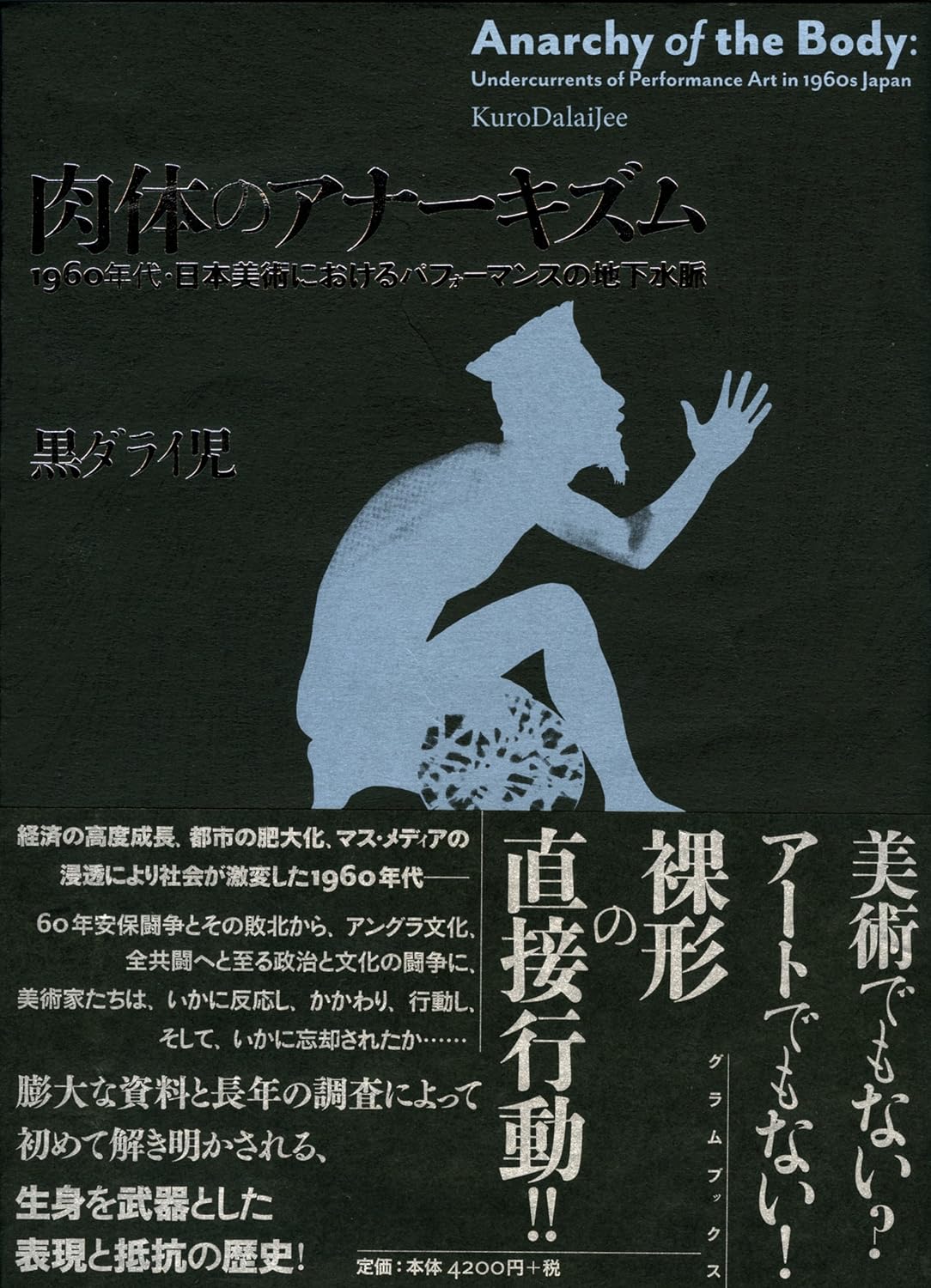
萩原弘子『ブラック──人種と視線をめぐる闘争』(毎日新聞社、2002年)
これまで歴史的に周縁化されてきた、主に英米のブラック作家による視覚芸術表現を丁寧に分析し、「移動・移民」、あるいは「人種と視線」といった今なお討議され続けているアジェンダを先駆的に提示した、日本における黒人文化研究のパイオニア的著作である。本書は2002年の初版だが、その刊行後20年以上を経ても、今日でもヴィヴィッドな論点を開示している刺激的な書物である。また、「ブラック」をめぐる諸問題を遠く欧米諸国で発生している「対岸の火事」として超越的に論述していくのではなく、常に「今ここ」で(そして、日本語で)思考する意味を念頭に置きながら、注意深く議論を展開していくその方法論から学ぶところは大きい。

儀三武桐子
カロリン・エムケ『なぜならそれは言葉にできるから』(浅井昌子訳、みすず書房、2019年)
言葉はどのようにわたしたちの世界に存在しているのか。世界各地の紛争地を取材するジャーナリストであるカロリン・エムケが、極限状態の体験の証言を軸に言葉と世界の関係性について考察した本書。語りにまつわる障壁は、その語りを困難にしているわたしたちの社会の問題だとし、沈黙する者は語りの能力ではなく、聞き手である他者への信頼が傷つけられたのではないかと問う。語り手と聞き手が力を合わせることで障壁を克服できると述べるエムケのまなざしはつねに、未だ語られていない、言葉になっていない声に注がれている。『なぜならそれは言葉にできるから』というタイトルには、わたしたちの社会と世界に、言葉の根底に、信頼を据えるという意志が感じられる。
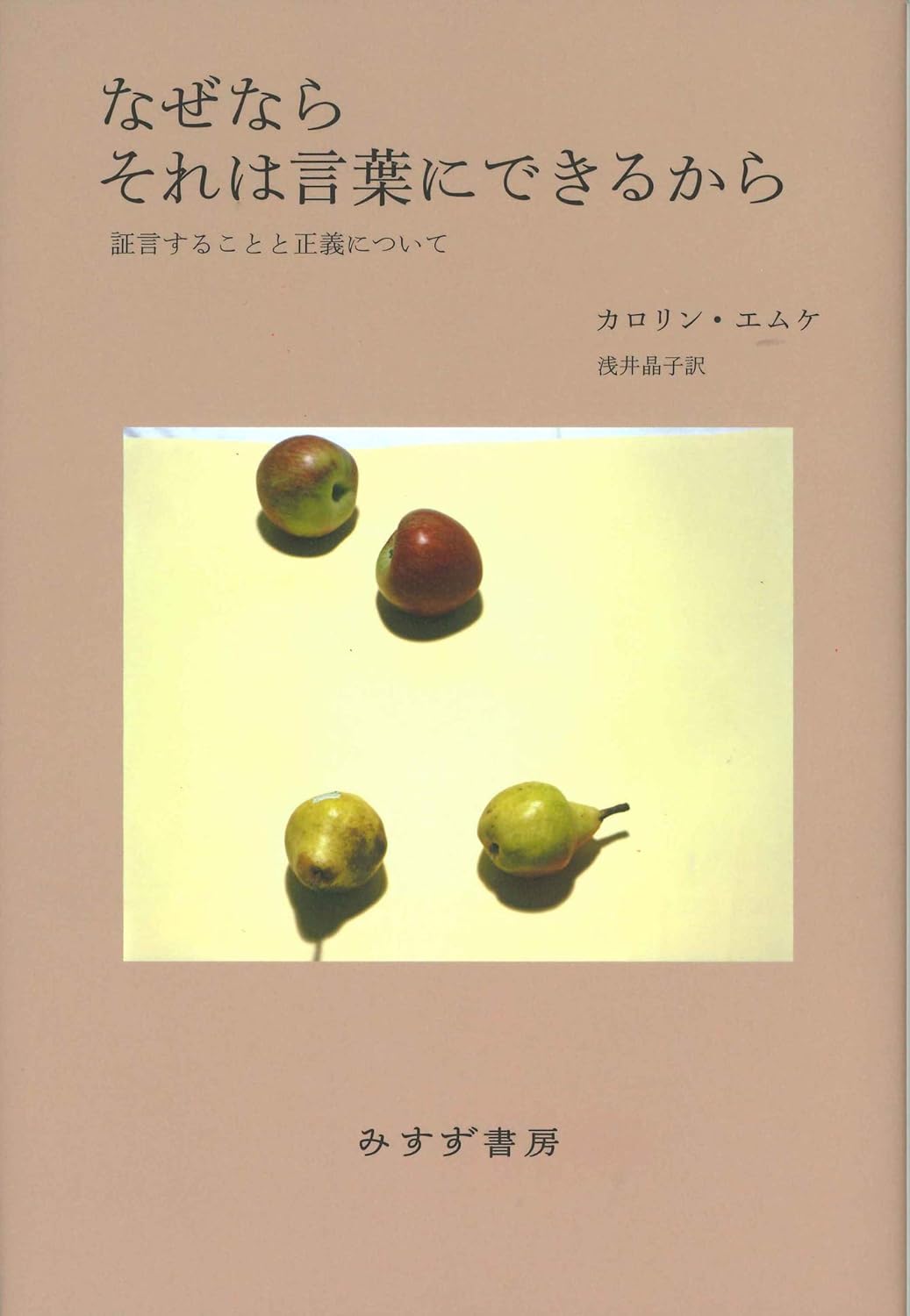
石牟礼道子『椿と海の記』(河出書房新社、2013年)
一、二、三、と数える先はどこまであって、此処の果てには何があり、人が生まれかわりならば今いる自分はいったい誰か。大海のような世の茫漠に戸惑うみっちん=石牟礼道子が「意識のろくろ首」となり経巡るのは、まだ水俣病が起こる前、「会社ゆき」が段々増えゆく1930年代熊本・不知火海沿岸の町。ありとあらゆるものに移り身し、代わり身し、さまようみっちんの目から見えてくるのは、さまざまなものたちが住まう町の、山の、海の、ときに残酷でときに慈悲深くもある在り様である。だからこそその海への冒涜は道子に『苦界浄土』を書かせるきっかけともなる。いのちはそもそもがほつれていて、ゆえに別のほつれと紡がれあう。本書に響くおもかさまの機織り唄に耳をすませば、そんな目に見えないほつれとほつれの気配が浮かびあがってくるかのようだ。

ハン・ガン『すべての、白いものたちの』(斎藤真理子訳、河出書房新社、2018年)
「私の生と体を貸し与えることによってのみ、彼女をよみがえらせることができるのだと悟ったとき、私はこの本を書きはじめた」光州事件を題材にした『少年が来る』上梓後、ひょんなことからワルシャワに来た作者。蜂起の報復として徹底的に破壊され、しかし根気強く再建を果たした「白い」都市で、生まれてすぐ亡くなった姉を想起し、彼女になりかわってえた体験を記した本書は「白いものたち」で満ちている。赤ん坊を包むおくるみ、傷を修復するペンキ、蝶のような魂……雪のように降り積もる白が余白となり、自分の、誰かの記憶を呼び戻す。冒頭のあとがきはこう続く。「彼女にあたたかい血が流れる体を贈りたいなら、私たちがあたたかい体を携えて生きているという事実を常に手探りし、確かめねばならなかった。(中略)どうあっても損なわれることのない部分を信じなくてはならなかった――信じようと努めるしかなかった」