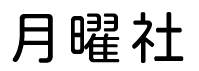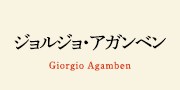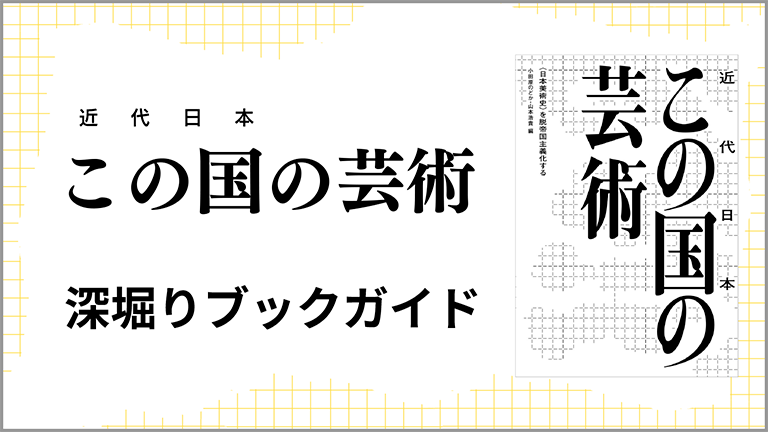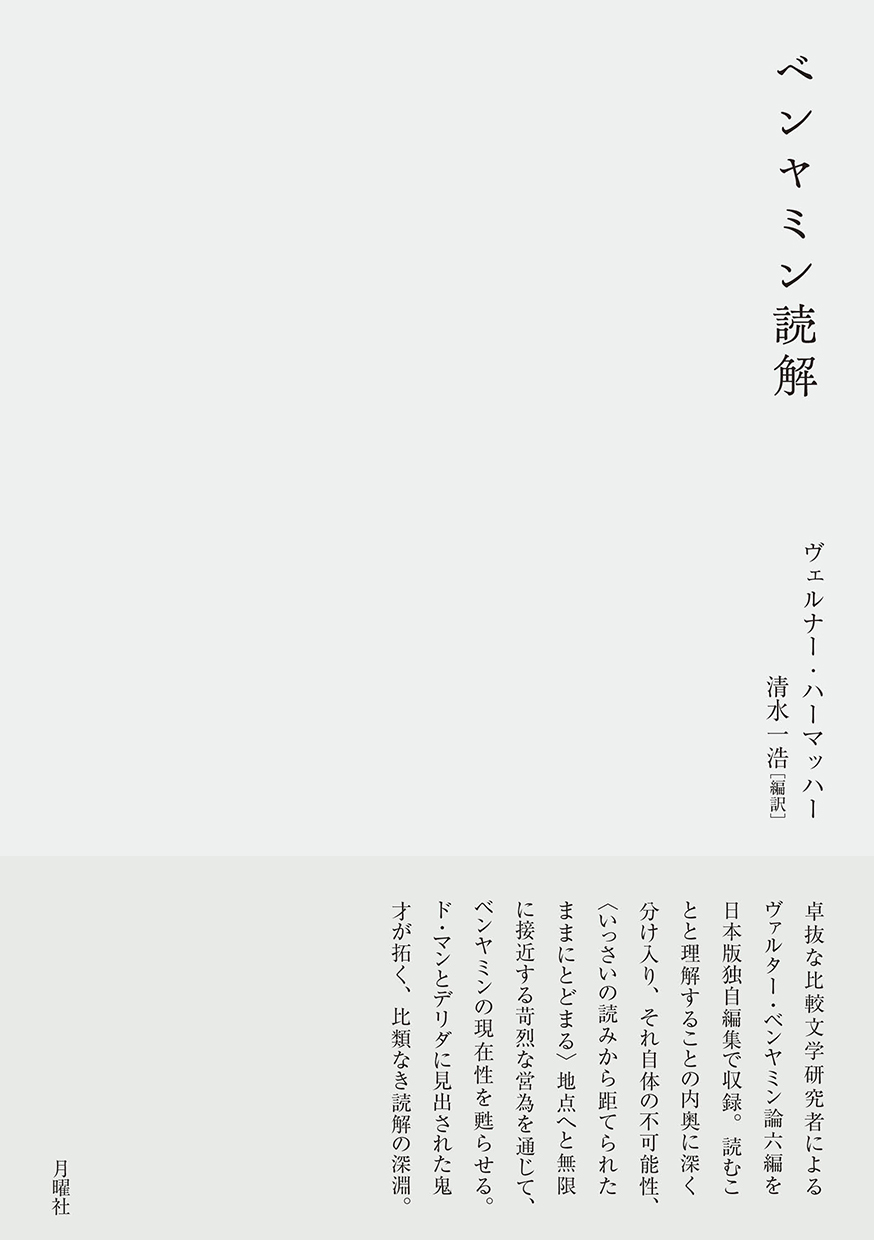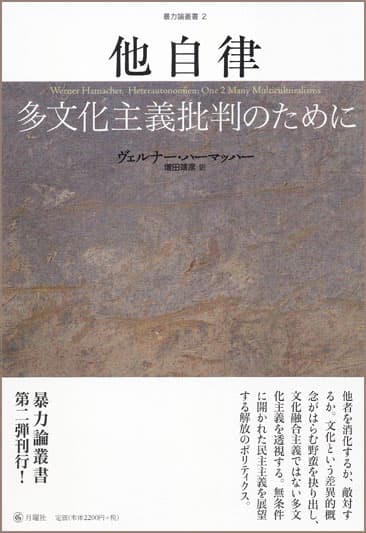卓抜な比較文学研究者によるヴァルター・ベンヤミン論六篇を日本版独自編集で収録。読むことと理解することの内奥に深く分け入り、それ自体の不可能性、〈いっさいの読みから距てられたままにとどまる〉地点へと無限に接近する苛烈な営為を通じて、ベンヤミンの現在性を甦らせる。ド・マンとデリダに見出された鬼才が拓く、比類なき読解の深淵。シリーズ・古典転生、第32回配本、本巻第31巻。
ベンヤミン読解
ヴェルナー・ハーマッハー
¥4,500 (税別)
清水一浩[編訳]
- 刊行年月:2025年10月
- A5判並製384頁
- 本体価格4,500円
ISBN:978-4-86503-212-3
収録論文
「雲という言葉――それが一つの言葉であるのなら」»Das Wort Wolke ̶ wenn es eines ist«. 著者より2004年に提供された未刊行のドイツ語タイプ原稿から訳出。
「アフォーマティヴ、ストライキ」»Afformativ, Streik«, 1994.
「内包的な諸言語」»Intensive Sprachen«, 2001.
「「今」――歴史的時間についてのベンヤミン」»‘Jetzt’. Benjamin zur historischen Zeit«, 2002.
「罪の歴史――ベンヤミンのスケッチ「宗教としての資本主義」」»Schuldgeschichte: Benjamins Skizze ›Kapitalismus als Religion‹«, 2003.
「メシア的なものの空所」»Vakanz des Messianischen (Das Theologisch-politische Fragment)«, 2006.
「それは、ヴァルター・ベンヤミンのテクストにおいて、さまざまな志向を表現する言語にあって「言語そのもの」にむかう言語の志向を印づけるべく定められている言葉の一つである。というのも「言葉〔Wort〕」が「雲〔Wolke〕」に似ているために、この言葉において、言語は、自らのなかで言われているもの全て――それが何であれ――の忘却にいたる敷居のうえに立たされるからである」(雲という言葉)。
「ヴァルター・ベンヤミンの論文「暴力批判論」は、純粋な媒介性〔Mittelbarkeit〕の政治にむけたスケッチである。ベンヤミンにとって、この政治の手段〔Mittel〕は、純粋な手段である。この手段は、媒介性の圏域のそとに想定されるような目的のための手段ではないからだ。そのような目的は両義的である」(アフォーマティヴ、ストライキ)。
「認識は一つの関係である。この関係のなかで、そのつど何かが認識される。それも、その何かの認識可能性において認識される。この認識可能性それ自身はそのような何かではなく、むしろ媒質である。この媒質のなかで、認識が認識されるものに関わり、もって両者が――すなわち一方で認識が、他方で認識されるものが――構成されるのである」(内包的な諸言語)。
「ベンヤミンが『歴史の概念について』の諸テーゼで発見しているのは、政治的情動の時間構造である。幸福へと方向づけられた政治的時間にこそ、歴史的時間は基礎づけられているのであり、それゆえあらゆる歴史理論は――歴史的認識と歴史的行為との理論は――この情動の時間こそを出発点としなければならない。政治的なものの理論における受苦・情動・情熱は、ベンヤミンの時代にはすでに一般に信用を失っていたが、このことはベンヤミンにとって、それらのもつ真に政治的な次元の消滅というほかなかった」(「今」)。
「機械的な因果性に基づく現象の連鎖として歴史を考えることができない以上、諸々の出来事のあいだの連関に歴史が存しているのだとすれば、この連関は少なくとも以下の二つの要求を満たさなければならない。すなわち、この連関は諸々の特定の出来事にそくして、それらの出来事の特定の結合形式において示されうるものでなければならないが、それでもなお自由の余地を残し、自らの規定のうちに開かれたところを残してもいなければならないのである」(罪の歴史)。
「一九三七年から三八年への年の変わり目の頃、ベンヤミンは、友人であるグレーテル・アドルノ、テオドア・ヴィーゼングルント・アドルノとともにサン・レモに滞在していた間に、歴史哲学についてのノート原稿を彼らに紹介した。そのノートにアクチュアリティが感じられたために、アドルノは――おそらくベンヤミン自身がはっきりそうだと言ったわけではなかったのだが――それがごく最近に書かれたものに違いないと確信し、各方面からの反論にもかかわらず、終生この確信を捨てなかった」(メシア的なものの空所)。
著者:ヴェルナー・ハーマッハー(Werner Hamacher, 1948-2017)ドイツの比較文学研究者、哲学者。著書に『他自律――多文化主義批判のために』(増田靖彦訳、月曜社、2007年)がある。
編訳者:清水一浩(しみず・かずひろ, 1977-)東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程単位取得退学。訳書に、アレクサンダー・ガルシア・デュットマン『友愛と敵対』(共訳、月曜社、2002年)、ヤーコプ・タウベス『パウロの政治神学』(共訳、岩波書店、2010年)、マルクス・ガブリエル『なぜ世界は存在しないのか』(講談社選書メチエ、2018年)などがある。