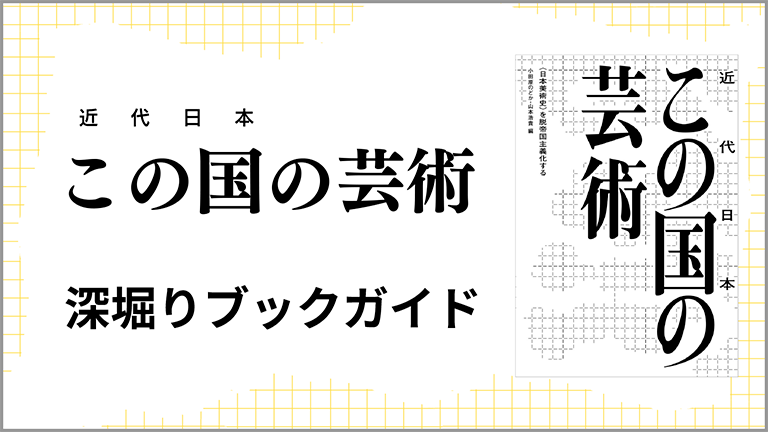「エレベーター・ガール」シリーズほか90年代の代表作を集成した大判作品集。
初期のエレベータ・ガールのシリーズには、神戸で生まれ、京都で生活する作者の身体感覚ともいえる自然な日本趣味が表出されている。だが、やなぎの場合、エキゾティスムをクールに客体化する先鋭なクリティシズムも備えている。
その批評性は大阪出身で写真を手がける森村泰昌に近いまなざしである。たとえば、植物園や動物園などを含めて、日本の博物館や美術館などの文化施設の建築空間を、やなぎはデパート文化と同様に西洋を参照して発達した人工的なモダニズムとみなしている。森村が西洋美術史を彩る名画に自らの肉体を挿入する方法で、個々の作品に対峙したのとは異なり、やなぎはモダニズムの虚構性を温存し続ける空間自体をテーマにした。そのなかで生粋のマニュアルで飼育された架空のエレベーター・ガールたちが、日本の芸術や文化のメタファーとなる。
短大の女子学生がサービス業のバイトをすると、途端に他者から好感をもたれる外見や人格などに豹変する過程を、やなぎみわは驚きといらだちをもって見ていた。彼女たちは無理やり型にはめられて言葉をはぎとられてゆくといったフェミニズム的な抵抗や被害者意識もなく、嬉々として他者のまなざしの欲望にしたがい、美しい「もの」へと変身する。それはあたかも、西洋というモデルに媚びてつねにしつらえを整えてきた日本の人工的美意識のようである。やなぎのエレベーター・ガールには、こうした歴史的無意識が影のように潜んでいる。
(岡部あおみ 武蔵野美術大学教授)[WHITE CASKET解説より]