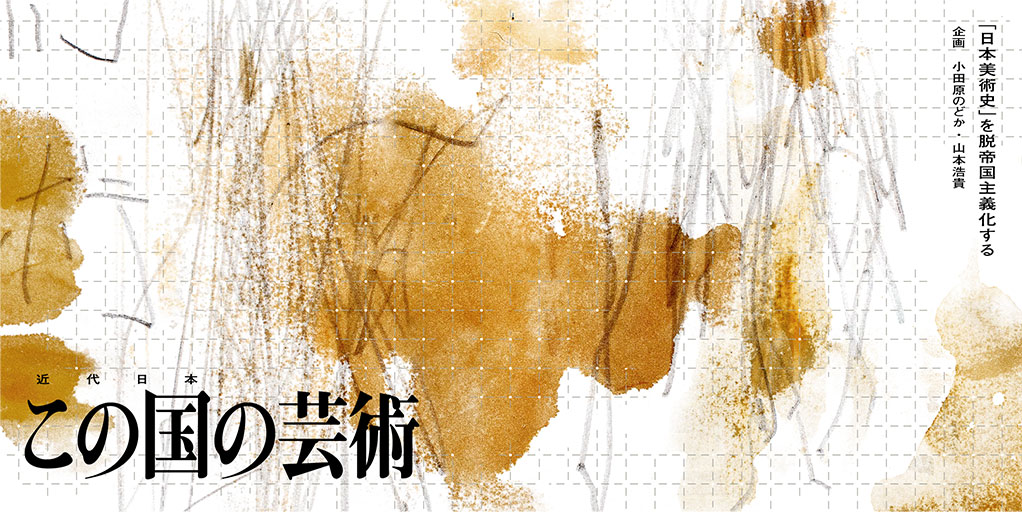
『この国の芸術:「日本美術史」を脱帝国主義化する』
収録予定の書き下ろし原稿を公開します
2022年7月に月曜社ウェブサイトにて、小田原のどかと山本浩貴の対談記事(https://getsuyosha.jp/20220711-2/ )を公開し、書籍『この国の芸術:「日本美術史」を脱帝国主義化する』の詳細を明らかにしました。
対談記事の公開後、本企画の発端であった飯山由貴さんの映像作品《In-Mates》をめぐり、深刻な検閲が東京都人権部によって行われたことが明らかになりました(https://chng.it/pJ6T486MRv )。これに強く抗議するとともに、このような現状への理解を深めるため、書籍刊行にいっそうの切実さをもって取り組みたいという思いを新たにしています。
また、同対談で開催を予告した、書籍寄稿者による全10回のオンライン連続講義(https://www.odawaranodoka.com/konokuni)は順調に回を重ね、残すところあと1回となりました。連続講義は多くの方にご視聴いただき、感想を寄せていただいています。寄せていただいた感想により、登壇者の執筆内容に変化があるなどの双方向性も生まれています。そして、ここでの売上げから登壇者と寄稿者全員に報酬を支払えることも確定しました。ご支援いただいたみなさんに心から感謝いたします。
7月に公開した対談記事は、山本による「より多くの方々にこのプロセスに巻き込まれて欲しいと願っています」という言葉で終わっています。ここからさらに本書の取り組みに関わっていただく機会を増やしたいと考え、この度、新たな取り組みを公開することにいたしました。
まず、2022年12月22日の講義最終回に際し、単発での視聴とともに、すでに終了した8回の講義[※第1回は録画公開対象ではないため、第2回から9回までの8回]の録画を見ることができるチケットをあわせて販売いたします[詳細→https://konokuni.peatix.com/]。
これに加えて、来夏刊行予定の書籍『この国の芸術:「日本美術史」を脱帝国主義化する』の「美術とレイシズム」をテーマとする第6章(仮)に収録予定の小田原のどかと山本浩貴による論考の第1稿を、一足先に全文公開いたします。
第1稿ですので、ここから変化があるはずです。残りの講義に参加していただくことや、あるいは、ここで公開したふたつの論考の感想を送っていただくことなどを通じて、本書のプロセスに多様な方法で関わっていただければ幸いです。本をつくることの様々な可能性を、みなさんと共有することできればと願っています。
2022年12月14日 小田原のどか・山本浩貴
アートとレイシズム——ブラック・ライブズ・マターを「対岸の火事」としないために*I
山本浩貴
1. 「レイシズム」とは何か
日本人論・日本文化論の古典『菊と刀』(1946年)の著者である文化人類学者のルース・ベネディクト(Ruth Benedict)は、1940年に世に出た『レイシズム』という著作のなかでレイシズムを「迷信」と断言し、その真正性をはっきりと退けている。*II 『レイシズム』のなかで、ベネディクトは「レイシズム」を「エスニック・グループに劣っているものと優れているものがあるというドグマ[筆者注:独断や偏見に基づく説や意見]」と定義し、「どれかの人種を絶滅させようとしたり、あるいは純粋に保とうとする」この歪んだ臆見こそ、「たった一つの人種によって進歩と未来が約束されるなどと人々に言わせ」、「数年前にドイツの政治体制に組み込まれて、そしていまや世界に蔓延している」当のものに他ならないと強く主張した。*III さらに、19世紀以降のヨーロッパを中心とした国民国家間の緊張関係の高まりに呼応し、レイシズムが「階級ごとの優劣を説くドクトリンから、国家ごとの優劣を説くドクトリンへと変わった」と彼女は分析する。*IV ベネディクトの議論を踏まえると、排他的ナショナリズムと結託した、現在頻繁に見られる形式のレイシズムはこうした歴史的経緯を経て形成された事象だと言える。
2020年に『レイシズム』を新訳した精神科医の阿部大樹は、その「訳者あとがき」において、その現代的意義を認めつつ、激化する第二次世界大戦の最中に同書が多様な人種構成を有するアメリカ合衆国で総動員体制を敷くためのプロパガンダとして機能した側面もあったことに注意を促す。*V こうした複雑な時代背景への慎重な配慮は、疑いなく重要である。しかし、そうした注意点や80年以上も前に書かれた本であるという事実を差し引いたとしても、ベネディクトの『レイシズム』には「国家的レイシズムの歴史は、【排外主義】の歴史そのものである」や「現代というナショナリズムの時代には、レイシズムは政治家の飛び道具である」といった、現在の国際・地域社会を考察するうえで今日でもなお有効と思われる鋭い箴言と洞察が随所に示されていることも同様に確かだ。*VI
加えて、近年では「インターセクショナリティ」という観点からレイシズムの問題を解きほぐすことの肝要さが盛んに唱えられている。この概念に関する包括的な入門書を共編したパトリシア・ヒル・コリンズ(Patricia Hill Collins)とスルマ・ビルゲ(Sirma Bilge)の説明を借りれば、「インターセクショナリティとは、交差する権力関係が、様々な社会にまたがる社会的経験や個人の日常的経験にどのように影響を及ぼすのかについて検討する概念」であり、人種、階級、ジェンダーなどの「数々のカテゴリーを、相互に関係し、形成し合っているものとして捉える」考え方・方法論と説明される。*VII レイシズム研究を主専門とする梁英聖は、新書として一般向けに書かれた『レイシズムとは何か』(2020年)において、「インターセクショナリティとは、現実の歴史の中では従属が、レイシズムやセクシズムなど、常に複数の従属と交差しているということを明確にするための概念である」と説明し、「レイシズムやセクシズムはそれぞれ単独で存在するわけではない」ことに注意を促している。*VIII 梁の提言は、レイシズムという現象を考えるにあたり、「人種」という要素だけではなく「性・ジェンダー」、「階級」、「障害(の有無)」といった異なる複数の変数も注意深く考慮に入れて検討する必要があることを私たちに教える。
*I:本稿は、2022年2月にオンライン・アート・ジャーナル『Tokyo Art Beat』に寄稿した拙稿「レイシズムとアート——誰もが他人事ではいられない問題と、芸術を通して向き合う」に加筆・修正を加えたものである。この文章は元々、連載企画「【シリーズ】○○とアート」の一部として構想・執筆された。同論考の転載を快諾してくださった、編集者の福島夏子さんにお礼を申し上げたい。福島さんから執筆の依頼を受けた論考が書籍のなかに収録されるのは、彼女が『美術手帖』編集部に在籍していたときに依頼をいただいた、「エコロジーの美術史」(同誌2020年6月号・特集「新しいエコロジー」に掲載)に続いて2回目となる。この論考は大幅な加筆・修正を施したあとで、同一タイトルのもとに長谷川祐子編『新しいエコロジーとアート——「まごつき期」としての人新世』(2022年、以文社)に所収された。現代世界において喫緊とされる重要なテーマやトピックに関わる論考の執筆について、いつも筆者に声をかけてくださる福島さんに感謝すると同時に、変化し続ける時代の趨勢を捉える彼女の優れた知性と感性に対して、ここで改めて敬意を表したい。
*II:アメリカで最初に刊行されたとき、『レイシズム』の原題はRace: Science and Politicsであった。その2年後に出版された英国版では、タイトルがRace and Racismに変更された。その後も数度にわたって版を重ねた同書であるが、いずれの改訂版でもこの英語タイトルが踏襲されている。
*III:ルース・ベネディクト『レイシズム』阿部大樹訳、講談社、2020年、118頁。
*IV:同書、147–154頁。
*V:同書、205頁。
*VI:同書、167頁。
*VII:パトリシア・ヒル・コリンズ、スルマ・ビルゲ『インターセクショナリティ』下地ローレンス吉孝監訳、小原理乃訳、人文書院、2021年、16頁。
*VIII:梁英聖『レイシズムとは何か』筑摩書房、2020年、273–276頁。
2. アートとレイシズムの歴史的関係
ベネディクトも述べるように、極端なナショナリズムと手を結んだ国家的レイシズムの高まりは、確かに第二次世界大戦以降に目立つようになった傾向だが、彼女が言うところの「エスニック・グループに劣っているものと優れているものがあるというドグマ」、すなわちレイシズム自体はその遥か昔から存在してきたことは忘れてはならない。『人種主義の歴史』(2022年)の著者である、フランス植民地史を専攻する平野千果子は「この[筆者注:「人種主義」という]言葉がヨーロッパの言語に由来しており、そのヨーロッパが大西洋を越えて異なる人びととの接触が始まったことが、今日における人種概念やいわゆる人種問題にも大きくつながっている」という考えに基づき、レイシズムの歴史に関する入門書として構想された同書の出発点を15世紀に始まる大航海時代に定めている。*IX
のちにトリニダード・トバゴ共和国の初代首相となり、「トリニダードの父」と称えられることになる歴史家・政治家のエリック・ウィリアムズ(Eric Williams)は、英オックスフォード大学に提出した博士論文を下敷きに書かれた『資本主義と奴隷制』(1944年)のなかで、18世紀のイギリスを端緒とする産業革命を準備したのは、それまで通説として支持されてきたような、禁欲と合理主義に特徴づけられる「プロテスタンティズムの倫理」(マックス・ヴェーバー, Max Weber)なるものではないと主張して既存の学説に真っ向から異を唱えた。それに代わってウィリアムズが同定した産業革命のドライビング・フォース(原動力)は、奴隷貿易と奴隷制プランテーションを通じて、言い換えれば人種的不正義の歴史のなかで徐々に蓄積された資本であったのだ。ウィリアムズはまた、「奴隷制は、人種差別から生まれたのではない。正確にいえば、人種差別が奴隷制に由来するものだった」と喝破し、現代にある人種のヒエラルキー構造が非人間的な不正義を通して歴史的に構築されたものであることを説得的に示し、その因果関係をコペルニクス的な仕方で転倒させた。*X
そして、よく知られている通り、奴隷制が作り出したヒエラルキーを「自然な」ものとみなす人種差別の意識は、近代の形成を加速させるイデオロギー的メイン・エンジンとなる植民地主義を正当化するための都合のいい口実へとすり替えられていった。ラテンアメリカの専門家であるオレリア・ミシェル(Aur’elia Michel)は、『黒人と白人の世界史』(2020年)のなかで、資本主義を蝶番のような役割として結びつく奴隷制と植民地支配の共犯関係について次のように述べている——「19世紀全般にわたる奴隷制廃止と植民地拡大の流れにおいて明確に示されたことは、資本主義は、労働を強制移動する目的のため、奴隷制と後の人種によって許可された暴力のシステムに大いに頼ることができたということだ」。 こうした歴史的経緯のなかで、「科学的には無効であっても、政治的、社会的現実として人種は存在する」という現状が生成されたとミシェルは喝破した。*XII
要するに、「「資本主義的世界経済」の形態をとって、「長期の16世紀」にヨーロッパと南北アメリカの一部に出現したが、以来、発展を続けて地球全体を包含するに至った」とされる、社会学者のイマニュエル・ウォーラーステイン(Immanuel Wallerstein)が精緻に理論化したところの、現在の私たちがその内部に生を送る「近代世界システム」は、その揺籃期からしてすでにレイシズムの種子を胚胎していたというわけである。 事実、「史的システムとしての資本主義のもとで、もっとも入念に練りあげられ、そのもっとも重要な支柱のひとつとなってきたのが、[…]制度としての【人種差別】である」とウォーラーステイン自身も明言している。 加えて、人種主義と植民地主義の双方において、国家規模でしばしば強制的に実施された「セクシュアリティの管理を通じた再生産のコントロール」がそれらの欠くべからざる構成要素をなしていたという、フェミニズム理論からの重要な指摘も忘れてはならない。*XV
では、アートと奴隷制に起因するレイシズムの登場・拡大のあいだには、歴史的にどのような連携が切り結ばれてきたのだろうか。そうした連携を考えるうえで、西洋美術史・西洋思想史を専門とする岡田温司による『西洋美術とレイシズム』(2020年)は、有意義な示唆を与える書物である。岡田は同書で、とりわけキリスト教美術を根幹にもつ西洋美術が、絵画のなかで聖書に登場する呪われた者たちを根拠もなくユダヤ人や黒人を彷彿とさせる姿に描いたり、反対に本来は「黒い皮膚」をもつ聖人や賢者たちに「白い仮面」を被せたりする行為によって、レイシズムを含有していたことを暴き出した。「黒い皮膚」や「白い仮面」という言葉を、筆者は精神科医でポストコロニアル理論の先駆者の一人とされるフランツ・ファノン(Frantz Fanon)による著作『黒い皮膚・白い仮面』(1952年)から借用している。仏領マルティニーク島で生まれ、アフリカから同地に強制連行された黒人奴隷を祖とするファノンは、同書のなかで自身が経験した人種差別の実態を告発し、差別者の心理構造を分析するだけではなく、「黒い皮膚」のうえに「白い仮面」を自ら進んでまとおうとする、黒人自身によるそうした差別構造の「内面化、よりよくいえば、[…]劣等性の表皮細胞化」にまつわる心理プロセスを真正面から解剖している。*XVI
さらに、ファノンは『黒い皮膚・白い仮面』の結論部で、「ひとりの人間が精神の尊厳を勝利せしめるたびに、ひとりの人間が彼の同胞を奴隷化する企てにノンと言うたびに、私はその行為との連帯を意識した」、あるいは「黒人も白人も、原本的なコミュニケーションが生まれ出ずるために、彼ら双方の父祖たちのものであった非人間的な声を振り棄てなければならない」と書いている(なお、ここでファノンが「彼」あるいは「父祖」という言葉を選択することで、このイシューにおける主体が男性に限定され、女性の存在があらかじめ排除されていることには別の問題として批判的な注意が向けられなくてはならない)。*XVII こうしたファノンの記述は、レイシズムの問題が「白人」や「黒人」という人種カテゴリーを超越し、あらゆる「人間」に関係する普遍性を帯びたものであることを示唆する。また、ファノンによるこの示唆は、後述するブラック・ライブズ・マター(BLM)運動の理念とも深く共鳴するものである。
さて、先述した岡田の『西洋美術とレイシズム』から私たちが得られる知見に話を戻せば、同書を通じて、つまるところ、レイシズムが誕生し、伸張していく歴史的プロセスにおいて、(主に絵画を中心とする)アートはその初期から、人々の視覚やイマジネーションに強烈に訴えるような仕方で存在しない人種間の優劣を捏造する差別的イデオロギーを擁護することに寄与してきたことがわかる。加えて、「西洋絵画のなかで飽くことなく脱色され漂白されてきた」黒人人物の多くが女性であったということは、「レイシズムがセクシズムと結託してきたことの証左」に他ならないという岡田の指摘は、先述した「インターセクショナリティ」の観点から見ても非常に重要である。*XVIII
なお、岡田の論述は「西洋美術」を対象としているが、日本の文脈では、芸術思想史と黒人文化研究を専攻する萩原弘子による、「南蛮屏風」(桃山時代から江戸初期にかけて人気を博した風俗画の一種)に登場する黒人図像に関する研究論文がある。萩原は南蛮屏風に描かれた多数の黒人について、「明るく健康的で躍動感にあふれているように描いているからといって、黒人に対する偏見の無さを証しているとは限らない」という留保を入れつつも、「アフリカ人の顔の造作をよくとらえた描写もあるし、労働する者を活写する画家の技量を確認できるものも多い」と述べてそのクオリティに対して一定の評価を与えている。 *XIX だがそもそも、萩原自身も同論考内で強調しているように、「南蛮屏風にはかなりの数の黒人が描かれている一方で、南蛮屏風を論じる文章には[…] 黒人図像への言及がほとんどと言ってよいほど存在しない」という事実自体が、日本において美術史・芸術論の領域では人種のヒエラルキーに関わる問題にほとんど関心が払われてこなかったことを明確に傍証していると言える。*XX
*IX:平野千果子『人種主義の歴史』岩波書店、2022年、2頁。
*X:エリック・ウィリアムズ『資本主義と奴隷制』中山毅訳、筑摩書房、2020年、20頁。
*XI:オレリア・ミシェル『黒人と白人の世界史——「人種」はいかにつくられてきたか』児玉しおり訳、明石書店、2021年、317頁。
*XII:同書、13頁。
*XIII:ウォーラーステイン『史的システムとしての資本主義』川北稔訳、岩波文庫、2022年、183頁。
*XIV:同書、124頁。
*XV:清水晶子『フェミニズムってなんですか?』文藝春秋、2022年、206頁。
*XVI:フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』海老坂武・加藤晴久訳、みすず書房、1998年、34頁。
*XVII:同書、244頁、249頁。
*XVIII:岡田温司『西洋美術とレイシズム』筑摩書房、2020年、138頁。
*XIX:萩原弘子「南蛮屏風の黒人図像——視覚イメージの存在と研究言説における不在をめぐって」『異文化研究』2巻、山口大学人文学部異文化交流研究施設、2008年、110頁、112頁。
*XX:同論文、107頁。
3.アートとレイシズムの現代的関係(1)——英ブラック・アーツ・ムーブメントとブラック・ライブズ・マター
ガーナにルーツを有する、1977年ロンドン生まれの作家リネッテ・イアドム・ボアキエ(Lynette Yiadom-Boakye)の平面作品は、しばしば歴史書や古典絵画などの二次文献から着想を得て制作される。それは芸術を通して黒人に付与されてきた歴史的表象を、再び芸術を通して再解釈する試みであり、ひいては、上に述べたようなアートとレイシズムの歴史的関係を解体する作業ととらえることができる。《数々の気がかりなこと(Any Number of Preoccupations)》(2010年)や《定足数(Quorum)》(2020年)などに代表される彼女の絵画は、黒人の表象が文化的に周縁に位置付けられてきた世界に対し、私たちの認識における根本的なレベルから揺さぶりをかけてくる。このように、戦後、各国においてレイシズムにまつわる様々な問題にアプローチする多様な実践が現代アートの世界で見られる。
ボアキエが生まれた時期、1970年代後半から1980年代にかけてのロンドンでは、若い黒人作家を中心として「ブラック・アーツ・ムーブメント」と総称される運動が展開されるようになった。この運動では、1970年代後半以降のイギリス社会における黒人住民に対する敵愾心の際立った高まりに直面して、アフリカ大陸/カリブ海地域/インド亜大陸などの様々な土地にルーツをもつ黒人作家たちの多くが自ら「ブラック・アーティスト」と名乗って一致団結し、レイシズムへの抵抗を試みた。*XXI その運動に深く関与した一人であるエディ・チェンバース(Eddie Chambers)が1979年から1980年にかけて制作したコラージュ作品《国民戦線の破壊(Destruction of the National Front)》は、その当時に勢いを増しつつあった極右政党「ブリティッシュ・ナショナル・フロント(イギリス国民戦線)」の台頭に対して、英国国旗であるユニオンジャックを、ナチスを想起させる鉤十字のかたちにコラージュして、その排外主義的な性質を苛烈に批判した。さらにチェンバースはその4点のコラージュを左から右にかけて徐々にバラバラに分解したものを並列し、人種的な排外主義への拒絶と抵抗の意思を明確に示した。
チェンバースよりやや年長のルバイナ・ヒミッド(Lubaina Himid)も、ブラック・アーツ・ムーブメントに関わった重要なアーティストである。1954年に東アフリカに位置するタンザニア・ザンジバルで生まれたヒミッドは、アーティストとしてピカソの有名な絵画に登場する少女たちを黒人として描き直したドローイングを含むインスタレーション作品《自由と変化》(1984年)などを発表するいっぽう、キュレーターとして男性作家に比してそれまであまり注目されてこなかった「黒人女性」作家に焦点を当てた「五人の黒人女性たち」(1983年)、「黒人女性たちの現在」(1983〜1984年)、「細い黒の線」(1985一九八五年)などの画期的な展覧会を企画した。ヒミッド以外にも、2022年のヴェネツィア・ビエンナーレにおいてイギリスの黒人女性として初となるイギリス館の代表を務めたソニア・ボイス(Sonia Boyce)や、代表作「トリロジー」シリーズ(1982年)などの絵画作品で、ステレオタイプを打ち破り、鑑賞者の中の無意識の偏見に挑みかかってくるような仕方で黒人女性の多彩な姿を生き生きと描き出した画家のクローデット・ジョンソン(Claudette Johnson)といった黒人女性作家らが、1980年代のイギリスにおけるブラック・アーツ・ムーブメントにおいてレイシズムとセクシズムのインターセクショナルな領域を探る実践を展開した。
こうした彼女たちの活動は近年、かなり遅ればせながらではあるが、ようやく正当な評価に浴することようになりつつある。2017年に「50歳未満」というそれまでの年齢条項が撤廃された最初のターナー賞(イギリス現代美術界で最大の賞のひとつ)の受賞者は、ルバイナ・ヒミッドであった。さらに、先述したソニア・ボイスがヴェネチア・ビエンナーレで国別パビリオンの最高賞である金獅子賞を受賞したことは、美術界で比較的話題を集めたニュースとなった。芸術を通して人種と性の交差性に果敢にアプローチしてきた彼女らの芸術実践の意義が、ようやく最近になって適切に評価されるようになってきたと同時に、これらの出来事は、ジェンダーやエスニシティをめぐる問題が昨今の現代アート界で絶対に無視することのできない重大な論点として浮上していることを如実に表している。
先に紹介した、近世初期日本の南蛮屏風に描かれた黒人図像に関する数少ない研究論文の執筆者である萩原弘子は、1980年代後半にイギリスに渡り、ブラック・アーツ・ムーブメントの作家たちとも濃密な交流を行っていた。萩原は、当地で聴講したルバイナ・ヒミッドの講義(彼女をゲスト講師として招聘したのは、当時リーズ大学で教鞭を執っていたフェミニスト美術史のパイオニアとして知られるグリゼルダ・ポロック, Griselda Pollockであった)が、「美術学校におけるカリキュラムの西洋中心主義に対する批判に始まり、美術機構の人種主義、美術史研究におけるジェンダーと人種のバイアス、英国によるアフリカ植民地支配の後のさらなる文化的支配を分析、批判する」という革新的な内容だったことを回顧している。*XXII 萩原は日本に帰国した後に『ブラック——人種と視線をめぐる闘争』(2002年)を刊行し、イギリスにおけるブラック・アーツ・ムーブメントの詳細を日本に紹介する役割を果たした。加えて次節で詳述するように、同書がたんなる海外の動向の紹介であるにとどまらず、イギリスにおけるアートとレイシズムの問題を日本独自の文脈からの議論も試みている点は非常に重要である。
非黒人警察官の不適切な拘束方法によって黒人男性が命を落とした、2020年の出来事(「ジョージ・フロイド事件」)を機に急速に世界中に広がった「ブラック・ライブズ・マター(BLM)」運動は、まだ私たちの記憶に新しい。先に述べたように、昨今の現代アート界で人種や民族にまつわるテーマがたいへん重要視されているのも、こうしたグローバルな流れと密接に結びついていることは明白だ。しかし、この運動はそれ以前から世界各地で頻発していた黒人に対する(主に白人の)警察官による不当で過剰な暴力——2012年の「トレイボン・マーティン射殺事件」、2014年の「エリック・ガーナー殺害事件」、同年の「マイケル・ブラウン射殺事件」など——に対して継続的に強い抗議を行ってきた。同様に、上で見た通り、戦後のイギリスに暮らす黒人アーティストたちは、人種間に存在しないヒエラルキーを捏造しようとする動きに対して作品制作や表現活動、創造的行為を通じた異議申し立てを起こしてきた。また、本節ではイギリスの事例に焦点を当てたが、アメリカやその他の様々な国や地域においても——一例としては、アメリカでは1950年代以降に盛んになったアフリカ系アメリカ人による公民権運動とも絡み合いながら——レイシズムと格闘する芸術家の挑戦は多様な仕方で展開されてきた史実は見落とせない。
さらに言えば、冒頭でルース・ベネディクトの定義を引きながら示した通り、レイシズムは「エスニック・グループに劣っているものと優れているものがあるというドグマ」であり、ゆえに必ずしも肌の色だけによって規定される概念ではない。このことは、レイシズムの問題は決して黒人と白人のあいだの係争だけに限定されないことを意味する。例えば、コロナ禍におけるヨーロッパ諸国やアメリカでは、その発生源とされるアジアにルールをもつと認識された人々が不当な差別や暴力の被害者となる事例が多数報告されているが、これもまた紛れもないレイシズムの顕現であると言える。そのような理由から、文化研究者の石松紀子は「ブラック・アート」という言葉を「帝国主義という歴史的な背景のもとで引き起こされる人種差別に関わる表現や、そのような差別から生じる苦境を言及している」芸術であるとして、その定義を拡張的に用いている。*XXIII 帝国主義やそれと密接に関わる奴隷制や植民地主義がレイシズムのイデオロギーを形成してきたことはすでに確認した。レイシズムに抗するアートは、これらの誤った歴史が産み落としてきた負の遺産と格闘する芸術実践に他ならない。
ところで、ブラック・ライブズ・マターに関連して世界中で彫像の引き倒し運動が発生したことは、その印象的なニュース映像のインパクトとともに記憶に焼き付いている人も多いだろう。19世紀のアメリカ南北戦争で奴隷制度を支持する南軍の司令官を務めたロバート・E・リー(Robert Edward Lee)などを筆頭として、奴隷貿易に関与していた、あるいは奴隷制度を支持していたとされる人物たちの像が現在進行形で次々と公共の場から撤去・破壊されている。この現象に関連して、自身も彫刻家である批評家の小田原のどかはブラック・ライブズ・マターを特集した『現代思想』誌に寄せた論考「モニュメンツ・マスト・フォール?——BLMにおける彫刻削除をめぐって」のなかで、「[筆者注:彫像を]削除するならば、撤去し、引き倒し、海に投げ入れたあとの空白を何で埋めるのか」もまた問われるべきであると主張している。*XXIV この点について、視覚表現を中心としたアートの実践は「空白」のあとに来たるべき未来を描くイマジネーションの可能性をはらんでいるのではないだろうか。
*XXI:Eddie Chambers, Black Artists in British Art: A History since the 1950s, I.B. Tauris, 2014, p.1.
*XXII:萩原弘子「英国ブラック・アート運動研究をめぐるあれこれ——回想、夢想、展望」『人文学論集』35巻、大阪府立大学人文学会、2017年、82頁。
*XXIII:石松紀子『イギリスにみる美術の現在——抵抗から開かれたモダニズムへ』花書院、2015年、41頁。
*XXIV:小田原のどか「モニュメンツ・マスト・フォール?——BLMにおける彫刻削除をめぐって」『現代思想』48巻、13号、青土社、2020年、245頁。
4. アートとレイシズムの現代的関係(2)——日本の反レイシズム的芸術実践
ブラック・ライブズ・マターは日本でも盛んに報道されたが、本邦ではどこか他人事のように事態を眺める見方が優勢だったのではないかとの懸念を筆者は抱いている。これは端的に言って誤った、危険な認識だ。日本に暮らすどの人々にとっても、ブラック・ライブズ・マター運動が照射する問題、すなわちレイシズムの問題は決して他人事として素通りすることなどできないものだ。なぜなら、本稿で論じてきた通り、レイシズムの問題は、資本主義と深く結託した奴隷制とそれに続く植民地支配という歴史の流れが作り出した現代世界に生きるすべての人々に関わるからだ。そして、レイシズムに苦しむ(大部分はエスニック・マイノリティである)すべての人々はそうした不当な抑圧から解放される権利を有するし、抑圧者の側に立つ(主にマジョリティとして生きる)すべての人々はそのために十分な努力を行う責務が課されるべきである。
ブラック・ライブズ・マターと日本の関わりについて留意しなくてはならないこととして、当然ながら日本に在住する黒人はたくさんいるという単純ではあるが忘れがちな事実がある。アフリカ近代史を研究していた父の関係でアフリカ南部の一国ジンバブエで生まれた画家・吉國元は、「来者たち」シリーズ——このタイトルは、詩人の大江満雄がハンセン病者について「癩者は来者である」と書いたことに由来する——などの絵画作品において、およそ10歳まで過ごした当地で出会った人々の記憶を描き続ける一方、日本に住むアフリカ出身の人々のコミュニティを独自に取材し、様々な媒体を通して発信していく個人プロジェクトを継続している。このプロジェクトでは自作の雑誌『MOTOマガジン』を(2022年8月時点で)すでに2冊刊行しており、それらのなかで吉國はセネガルやウガンダ出身の日本在住者たちに東京で開催されたBLMマーチについて丁寧な聞き取りを重ねている。吉國は自身のホームページに掲載したテキスト「私のフィールドワーク」(この文章の初出は、2018年9月26日に投稿されたメールマガジン『FENICS』50号に掲載されている)のなかで、「戦争、コロニアル、ポストコロニアル、レイシズムやマイノリティー」の問題は「遠い国の出来事だけではない。それは現在足元で起こっている事でもあり、その場所は現代日本とも関係している」と記す。*XXV レイシズムの問題が「対岸の火事」として軽視されがちな日本において、この国に暮らす私たちは改めて彼の言葉を重く受け止めなくてはならない。
続いて、また別の観点から日本におけるレイシズムの問題を考えてみたい。先述した萩原弘子による2002年刊行の著書『ブラック』のなかの次の一節は大いに傾聴に値する。
日本語で「人種差別」と言うと、黒人対白人という皮膚の色による二分と、その二者間の権力関係のことと理解され、日本にはない、よその問題と考えられてしまう。しかし人種差別(racism)は、皮膚の色を理由とするものではなく、奴隷制度と植民地統治で築きあげた権力関係をその後も維持するために、皮膚の色が、はっきりと人為の権力関係を自然化してみせる論法として利用されている。そうであるなら、在日朝鮮人や他の第三世界出身者に対する植民地主義的な権力関係の維持という、歴史的、政治的、経済的な動機に根ざす不公正を制度化した日本は、人種差別(racism)社会と言える。*XXVI
萩原が同書を世に問うてからすでに20年近くが経過しているが、この鋭い洞察は現在の日本の状況をも的確に言い当てているように思われる。そして、「在日朝鮮人や他の第三世界出身者に対する植民地主義的な権力関係の維持」のために、そうした人々を抑圧し攻撃する「ヘイトスピーチ」は、現在も日本に偏在するレイシズムの顕現であろう。こうした問題に作品を通じて取り組んできた、在日コリアンや日本人の現代アーティストたちがいる。
例えば、映像・パフォーマンス作家のクム・ソニ(琴仙姫)は、米留学中に制作した映像作品《獣となりても》(2005年)の一場面において、日本の北朝鮮コミュニティで育った自身の体験にも言及しながら、在日コリアンに対する迫害の歴史を前景化している。同作は、単線的で「わかりやすい」物語を欠き、一見すると難解な作品である。《獣となりても》は複数の場面から構成されるが、その一部として、チマチョゴリに身をつつんで登場する琴自身が、民族学校に通っていたときに体験した日本人男性からのレイシスト的暴力に言及する。他方、突如出現するヤギの群れには、冷戦下でさかんに核実験がなされたマーシャル諸島の被爆者たちのポリフォニックな声がナレーションとして重ねられる。こうしたことから、この映像作品では、東アジアの戦争、植民地支配、冷戦が作り上げた国際的「秩序」における、さまざまな犠牲者たちの姿が、「贖罪のヤギ(スケープゴート)」というイメージを通して視覚的に連結されていることがわかる。琴の作品は、その鑑賞者たちが、現代日本に蔓延するレイシズムを、こうしたより広い歴史的文脈に位置づけて把握することを可能にする。
琴の最新作《朝露:Mourning Dew–Stigma of Being Brainwashed》(2020年)は映像インスタレーションであり、同作の主題は、途中に数年の中断期間はあったが1959年から1984年まで継続された、現在では日本戦後史の忘却された歴史的出来事となっている通称「北朝鮮帰国事業」である。主に日朝赤十字の主導により実現された同事業のなかで、およそ25年のあいだに、たくさんの在日コリアンと日本人配偶者を含むその家族たちが北朝鮮にわたった。その数は「総計93,340人」にも及ぶと推定される。*XXVII これほど多くの在日コリアンが「祖国」へと「帰国」した背景には、当時北朝鮮がさかんに宣伝していた「地上の楽園」——そこでは出自にかかわらず、誰もが自由に学び、働くことができるとされた——というプロパガンダの効力があった。しかし同時に、こうした虚像が多大な影響力を及ぼした後景には、日本での在日コリアンに対する社会的・制度的な差別の存在があったことを忘れてはならない。*XXVIII そして、こうした排他的差別は、今もなお日本社会に根強く残存している。
1991年に神戸で生まれた在日コリアン三世のアーティストであるチョン・ユギョン(鄭裕憬)は、《For one and only country!》(2013年)や《Let’s all go to the celebration square of victory》(2018年)など、2010年代前半から国家や民族にまつわる思索から作られる絵画作品を発表してきた。その一方で、チョンは、ナショナリズムが高揚するオリンピックの時期には、ピクトグラムを用いた「ZAINICHI AGAINST RACISM」という缶バッチを自作して販売するなど、アクティビスト的なエンゲージメントの手法を通してもレイシズムとの戦いを展開している。いわゆる「デジタル・ネイティブ」の世代に属する彼は、現代日本におけるレイシズム的な動向を注視し、それを的確な言葉で批判する一方で、反レイシズム的な動向をよりたくさんの人たちに知らしめ、それを力強く後押しするために、TwitterやFacebookなどのSNSを効率的に活用している。

また、チョンは朝鮮大学校美術科の5人の現代アーティストによる絵画を中心とした、現代美術ギャラリー「eitoeiko」を会場として行われた展覧会「在日・現在・美術」展(2014年)の企画者でもあり、ナショナルな枠組みが強固で閉鎖的な日本美術界において在日コリアン参加の存在を可視化するためのキュレーション的活動も行ってきた。同展出展アーティストの個々の作品に目を向けると、写実的なものからポップ・アートを彷彿とさせるものまで幅広い作品が並び、その振幅はそのまま、一括りにまとめることなど到底できない在日コリアン作家の多様性を象徴する。参加アーティストの一人である美術家のリ・ジョンオク(李晶玉)は、『朝鮮新報』に掲載されたインタビュー記事(2014年5月19日)のなかで、「閉鎖的な日本美術界で『在日朝鮮人アーティスト』としてチャレンジすることに意味がある」と語っている。このことは、「在日・現在・美術」展のような展覧会を実現すること自体が、日本のアート界の中で、在日コリアン作家という「異質な」存在を可視化する、意義深い挑戦であったことを示唆する。
1977年生まれのアーティスト・竹川宣彰は、ドローイング作品《新大久保レイシズム昆虫合戦図》(2013年)の作者である。同作は、2010年代半ばごろから日本で目立つようになった在日コリアンをはじめとする本邦のエスニック・マイノリティに対する排外主義と、それに対抗する人々の様子を「昆虫合戦図」に仮託して描き出した作品である。竹川は作品制作・発表を通じてのみならず、特に在日コリアンらに対するヘイトスピーチに抗する政治運動にも連帯・参加しながら、日本におけるレイシズムの跋扈と格闘し続けているアーティストだ。こうした彼の動きについて、横浜美術館主任学芸員の木村絵理子は、竹川へのインタビューを経て構成されたレポートのなかで、「竹川の活動の根底にはつねに、歴史、とりわけ近代史に対する内省的な視点が貫かれている」と総括している。*XXIX しかしながら、日本ではこうした類の芸術実践や、それを行う作家、そうした作家たちをまとめあげて展覧会を構成するキュレーターたちの活動の意義が十分に認知も討議もされていないのが現状である。

ここまで繰り返し強調してきた通り、レイシズムは現代世界を生きるあらゆる人々——当然ながら、そこにはアーティストやアート関係者も含まれる——に関わる問題である。誰も他人事のような顔をしてはいられないのだ。日本において、世界中で盛り上がりを呈するブラック・ライブズ・マター運動を、ある一部の人にとってはこのうえなく重要ではあるが、自身とは無関係で痛痒を感じる必要のない出来事、すなわち「対岸の火事」としてはならない。そのために、本邦においても、アートを通してレイシズムと対峙し、対決する様々な実践が今後さらに広く深く議論されていくことが喫緊の急務である。
*XXI:吉國元「私のフィールドワーク」MOTO YOSHIKUNI、https://www.motoyoshikuni.com/texts(参照:2022年8月20日)。
*XXVI:萩原弘子『ブラック——人種と視線をめぐる闘争』毎日新聞社、2002年、33頁。
*XXVII:菊池嘉晃『北朝鮮帰国事業——「壮大な拉致」か「追放」か』中央公論新社、2009年、i頁。
*XXVIII:テッサ・モーリス・スズキ著、田代泰子訳『北朝鮮へのエクソダス——「帰国事業」の影をたどる』朝日新聞出版、2011年、89–91頁。
*XXIX:木村絵理子「国境を超えた他者との関わり、歴史への視点。竹川宣彰インタビュー」『美術手帖』2021年2月号、163頁。
次の100年を見つめて──日本美術史と人種主義の交点に立つ*III
小田原のどか
[…]吾々がエタである事を誇り得る時が来たのだ。
──「水平社宣言」1922年3月 *XXXI
吾々は、かならず卑屈なる言葉と怯懦なる行為によって、祖先を辱しめ、人間を冒涜してはならぬ。そうして人の世の冷たさが、何んなに冷冷たいか、人間を勦る事が何んであるかをよく知っている吾々は、心から人生の熱と光を願求禮讃するものである。
水平社は、かくして生れた。
人の世に熱あれ、人間に光あれ。
1 個別具体的な問題を見つめる
1922(大正11)年3月3日、封建的な身分差別を背景とする部落差別の解消をめざす運動団体「全国水平社」の創立大会が、京都市岡崎公会堂で開催された。「穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス」と定めた1871年8月の太政官布告、いわゆる「賤民解放令」からおよそ50年後のことである。1868年の明治維新により徳川幕府は消滅した。明治政府は近世身分制を廃して「四民平等」を推し進めたが、これは天皇に権威を集中させ、天皇のもと平等な臣民を統治する「一君万民」の理念を強化するものであり、「解放」も「平等」も形式に過ぎなかった。天皇をいただく王政の復古と、これに基づく新たな身分制度の確立。この国の近代国家はこうして立ち現れる。ゆえに全国水平社創立大会は、部落解放への期待を胸に集った者たちの熱気に包まれていた。ここで読み上げられ、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と結んだ水平社宣言は、この国初めての人権宣言だといわれる。水平社宣言から100年を経たいま、当事者らのたゆまぬ闘いにより、部落差別を取り巻く状況はめざましく前進した。しかしいまだ、完全に解消されたと言うことはできない。
東京都総務局人権部が2021年2月に公開した「人権に関する都民の意識調査報告書」*XXXII では、「仮にあなたが同和地区の人と結婚しようとしたとき、親や親戚から強い反対を受けたら、あなたはどうしますか」という質問に対し、「自分の意思を貫いて結婚する」は19.2%、「親の説得に全力を傾けたのちに、自分の意思を貫いて結婚する」が27.5%、「家族や親戚の反対があれば、結婚しない」は8.9%、「絶対に結婚しない」5.8%、「わからない」は38.5%であった。『結婚する』との回答は合計46.7%、すなわち50%以上が結婚を断念する選択をしうるという結果が出ている *XXXIII。 2020年代においてなお部落差別が存在する現状に対し、当事者の心中は察するにあまりある。しかし同時に、こと部落問題において、結婚が中心的な話題とされ続けるのはなぜかに注視する必要がある。
中国文学者・評論家の竹内好が「私がなぜ部落問題に関心をもつのかといえば、日本の社会の問題、日本の文化の問題、ひいては文明観そのものを考える上に、部落問題は絶対にはずしてはならぬ視点だと思うからである」 *XXXIV と述べ、「日本の問題を考える上でどうしても抜かしてはならぬカナメの部分」*XXXV だと指摘したように、部落差別に日本社会の特質が如実に反映されていると捉える視座は決定的に重要なものである。どういうことか。つまるところ、部落差別は民族差別ではない。部落差別とは「つくられた人種」をめぐる差別に他ならない。人種主義については本書所収の山本浩貴による論考「アートとレイシズム——ブラック・ライブズ・マターを「対岸の火事」としないために」を参照していただきたいが、歴史学者の酒井直樹もまた、「人種という概念を「合理的」に説明することは非常に困難である」と言い、「社会的かつ審美的な判断を自然科学的に断定しようという試みを含んでいて、それ自身は自然科学の概念とは認めがたい」と述べている*XXXVI 。
つくられた人種差別としての部落問題をめぐりいまなお続く結婚差別には、近世において部落内で「血族結婚」が繰り返されてきたという紋切り型の認識が影響している。しかし、「血族結婚」は被差別部落に固有のものではなかった *XXXVII。これを受け、被差別部落史を研究する歴史学者の黒川みどりは、明治期の被差別部落認識について、「自らも近親婚を繰り返している民衆が、被差別部落との通婚を忌避するというのは、[…]社会ダーウィニズムの論理をもってしては説明しえない」とし、「民衆が頑なに守ろうとするのは、遺伝的な資質とは無縁の家柄・家格であり、個人の資質よりむしろ「家」の継承に力点のある血筋と称される、優生思想による科学主義・合理主義では説明できない」と断じている *XXXVIII 。
中世日本の歴史学者・網野善彦によれば、13世紀後半に畏怖の対象であった「ケガレ・穢れ」観念は忌避・賤視の対象としての汚穢へと転回する *XXXIX 。加えて、江戸幕府による食肉・皮革生産の一元化は賤民身分の固定を決定づけた *XL 。そしてここに、黒川が指摘するこの国特有の不合理な「家」・血筋意識が分かちがたく結び付いている。なぜ、現在においてもなお、部落差別をめぐる話題は、「親や親戚からの強い反対」という家・血筋意識の問題としてことさら俎上に載せられるのか。それこそがまさに「日本の問題を考える上でどうしても抜かしてはならぬカナメの部分」なのだ。日本固有の差別問題の精髄は、黒川の視座を抜きに見据えることはできない。
さらに考慮すべきは、東京都総務局人権部により2013年に行われた前回調査との比較である。2013年の調査においては「自分の意思を貫いて結婚する」26.1%、「親の説得に全力を傾けたのちに、自分の意思を貫いて結婚する」30.4%、「家族や親戚の反対があれば、結婚しない」10.5%、「絶対に結婚しない」4.9%、「わからない」28.1%であった。2013年に比べ2021年の調査では、『結婚する』がマイナス9.8ポイント減少し、「わからない」が10.4ポイント増加している。この増加に注目したい。2002年3月に同和対策事業特別措置法が廃止され、「同和対策」や「同和教育」はより包括的な「人権教育」に置き換えられていったといわれる。つまり、2021年の調査における「わからない」の増加は、部落差別を知らない者の増加としても見ることができる。これは部落問題が人権教育へと流し込まれた結果、個別の問題としての理解が妨げられていることの証左ではないだろうか。
黒川は、「人権」は「言葉の天下り」になりかねないと苦言を呈した政治思想史学者・丸山眞男の言*XLI を引き、「人権意識は、個別具体的な問題を見つめることによって獲得され陶冶されるもの」だと主張している*XLII 。ゆえに本稿もまた、「個別具体的な問題を見つめる」ことを重視する。このようにして、日本美術史と人種主義の交点を探りたい。まずはこの国の美術史からこぼれ落ちた人物と作品に、個別の光を当てることから始めよう。
*XXX:本稿第4節は、『文學界』2022年10月[特集:もうひとつの芸術史]に寄稿した拙稿「不在・欠損・病──彫刻、理想化された身体をめぐって」を改稿したものである。また、本稿で用いた「穢多(えた)」「非人(ひにん)」「特殊部落」などの用語は、差別的な意味で使用されてきた背景を持つが、本稿においては歴史的用語としてそのまま使用する。
*XXXI:一部、旧仮名づかいを改めた。
*XXXII:東京都総務局人権部「人権に関する都民の意識調査報告書」2021年2月。URL=https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/base/upload/pdf/ishiki.pdf(2022年9月12日最終閲覧)
*XXXIII:合計が99.9%であるが、「人権に関する都民の意識調査報告書」の結果に従った。
*XXXIV:竹内好『竹内好全集』第12巻、筑摩書房、1981年、497頁。
*XXXV:竹内好『竹内好全集』第9巻、筑摩書房、1981年、316頁。
*XXXVI:酒井直樹『死産される日本語・日本人』新曜社、1998年、215頁。
*XXXVII:竹永三男『近代日本の地域社会と部落問題』部落問題研究所出版部、1998年、252頁。
*XXXVIII:黒川みどり『被差別部落認識の歴史』岩波現代文庫、2021年、93頁。
*XXXIX:網野善彦『日本の歴史をよみなおす』筑摩書房、2017年、118頁。
*XL:野間宏・沖浦和光『日本の聖と賤 近代篇』人文書院、1992年、99−100頁。
*XLI:丸山眞男『丸山眞男話文集』続2、みすず書房、2014年、151頁。
*XLII:黒川みどり『被差別部落認識の歴史』岩波現代文庫、2021年、370頁。
2 西光万吉《毀釈》──「転向」の自画像
冒頭に引いた水平社宣言は、当時27歳であった西光万吉[ルビ:さいこうまんきち](1895-1970年)が全体を起草し、仲間の検討を経て完成した。西光は水平社宣言の公表後、1922年5月に水平社の精神を意匠化した荊冠旗を完成させている。文筆だけでなく画業にも秀でた西光は、実のところ、寺松国太郎 、中村不折 、橋本静水 らに師事し、中央画壇で画家としての未来を嘱望されるも、部落差別によりその道を断念することを余儀なくされた人物であった。多数の作品が残されているものの、画家としての西光に着目した研究はほとんど皆無である。なぜか。それは西光の「転向」の問題に関わっている。三・一五事件で投獄された西光は獄中で転向したとされる。部落解放運動の創始者でありながら、出獄後は国家主義運動を主導し、侵略戦争を支持した。こうした西光のありようは、「天皇主義者への転落」と否定的に評価されてきた *XLIII 。それゆえ、まとまった伝記の成立を逸し、評伝の類も限られる。唯一の画集『西光萬吉の絵と心』においても、天皇主義者としての横顔への言及は慎重に避けられている。西光は語りづらい。しかしその語りづらさにこそ、手掛かりがあると思えてならない。それは、これまでなおざりにされてきた、日本美術史における転向研究の糸口である。
1895(明治28)年、西光は奈良県南葛城郡掖上村柏原北方の浄土真宗本願寺派(西本願寺派)の西光寺の住職・清原道隆とコノエの長男として生まれた。本名は清原一隆、西光万吉は成人後に自らつけた名である。西光の出生地・北方は被差別部落であった。この地から部落解放運動は広がった。現在、西光寺の向かいには水平社博物館が立ち、御所市柏原は「人権のふるさと」と呼ばれる。とはいえ西光誕生当時の同地域においては、1871年の「賤民解放令」後も賤視が改められることがなかった。
1901年4月、掖上村立尋常小学校に入学した西光は、北方の子どもが他地域の子らとは区別され、「エタ」「新平(新平民)」と罵られる部落差別を目の当たりにする。1905年4月に御所高等小学校に進学、1910年4月には県有数の名門校であった畝傍中学校に入学するが、教員からの差別により通学をやめている。翌年4月、おそらくは父の配慮により西本願寺が経営する京都市平安中学校に編入学するが、奈良出身の教師に部落出身者であることを暴かれ、ことあるごとに同級生の前で侮辱されるようになる。耐えきれず同校を中途退学した西光は、僧侶となることを断念するに至る。
平安中学中退後の1911年秋、西光は京都市の関西美術院に入り、洋画家・寺松国太郎(1876-1943年)に洋画の手ほどきを受けた。本格的に画業に取り組む決意をして1913年春に上京し、谷中の太平洋画会研究所へ入塾。洋画家・中村不折(1866-1943年)から洋画を、日本美術院の橋本静水(1876-1943年)から日本画を学んだ。1913年秋には国民美術展覧会に上位入選し、翌1914年3月には二科会の画展に入選した。画業は順調であり、支援者にも恵まれた。しかし平穏な日々は長くは続かなかった。部落差別は西光についてまわった。上京して最初の夜に起きた出来事について、西光はこのように回想している。
東京へ行った第一夜、始めての晩ですよ。太平洋画会の紹介で下宿に着いて、あてがわれた部屋に荷物をおろし、自画像を描いていると、階下で下宿のおかみさんたちが話しているんです。
「新しいこどもが来ましたね。どこから来たんです」「奈良県ですよ。奈良県には、名物が三つありますよ」「何でしょう」。ほかに下宿している人たちも話し込んでいるんです。「ひとつは奈良の鹿。ひとつは奈良のおかゆ。あとひとつは、えたや。部落民や」いうてるんですよ。私はその夜眠れませんでした。畝傍中学で差別を受けてやめ、故郷を離れれば、こんな差別的なことばを聞かなくてよいと思って東京に来たのにその第一夜にですよ。寝られますか。 *XLIV
1916年1月、西光はパトロンのひとりであった松岡なる美術商に奈良見物の案内役を請われ、父親に引き合わせてほしいと頼まれた。西光の画才を見込んで便宜を図っていた松岡にしてみれば、他意のない依頼であったことだろう。しかし、西光には恐怖でしかなかった。被差別部落出身であることを知られると考えた西光はこの美術商を避けるようになり、以後、二度と会うことはなかった *XLV 。またほぼ同時期に、恩師のひとりから娘との婚約を勧められる *XLVI 。ここでも出自が露見することを恐れた西光は八方塞がりとなり、画塾に紹介された下宿からも、画塾自体からも遠ざかった。師事した画家たちとの関係をすべて断ち、西光が画家として活躍する未来は途絶する。
この時期、掖上村立尋常小学校の二学年上の友人であり、全国水平社をともに立ち上げる生涯の同志・阪本清一郎(1892-1987年)が上京していた。北方で膠製造業を営む裕福な地主の家に生まれた阪本は、ゼラチン研究のため東京工科学校(現・日本工業大学)に進学していた。西光は、青山にあった阪本の下宿に身を寄せるが、希死念慮にとりつかれ失意のなか著しく体調を崩し、1917年秋、阪本にともなわれて帰郷する。東京在住時に清原一隆の名で発表され、評価を受けた作品は、残されなかった。
帰郷後、県下の部落差別はいっそう苛烈であった。1918年には阪本らと「柏原青年共和国」をつくり、部落差別がはびこる日本を捨て南洋セレベス島への移住を計画するが、頓挫する。翌年、阪本らと「部落問題研究会」をつくり、日本社会主義同盟に加入する。決定的であったのは機関誌『解放』1921年7月号に掲載された佐野学(1892−1953年、日本共産党(第二次共産党)中央委員長を務めたのち転向)の「特殊部落解放論」である。「部落民自身が先ず不当なる社会的地位の廃止を要求するより始まらねばならぬ」と書かれた佐野の論文に感銘を受け、ただちに阪本と上京し、早稲田大学で講師をしていた佐野を訪ねて教えをうけた。9月には阪本・駒井喜作らと柏原の野小屋に水平社創立事務所を設け、水平社の組織活動に取り組んでいく。水平社設立趣意書や水平社宣言のみならず、ロマン・ロラン Romain Rolland(1866-1944年)『民衆芸術論』(大杉栄訳、アルス、1921年、原著は1903年刊行)やウィリアム・モリス William Morris(1834-1896年)の活動を参照し、水平社の広報パンフレットの挿図や、支援者の勧めで出版した戯曲集の装画などで西光は才を発揮した。
全国水平社の創立後、1927年秋に日本共産党に入党した西光は、同党に対する大規模弾圧事件である1928年3月の三・一五事件により投獄され、獄中で国家主義者へ「転向」したとされる。出所後は水平運動から距離を置き、「君民一如の搾取なき新日本の建設」を目指した大日本国家社会党に入り、同党奈良県掖上支部を結成した。1938年には『新生運動』第8号において、「今や我らは『人間に光あれ、人世に熱あれ』の願望を惟神道に求め八紘一宇の高天原展開に邁進せんとする」と、水平社宣言と大日本帝国の侵略戦争を正当化する標語・八紘一宇とを接続し、全国水平社を「国体の本義に基きて更に反省せよ」と批判している。とはいえ、西光の転向は「転落」とひと言で言い表せるほど単純なものではない。
西光は水平社宣言を「全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ」と始め、マルクスとエンゲルスによる『共産党宣言』(「万国の労働者よ団結せよ」)を参照した。しかし西光は日本共産党入党時、綱領第6項「君主制の打倒」に記された、身分差別の根源としての絶対主義的天皇制の打破を否定していた。京都部落史研究所所長でもあった日本史学者・師岡佑行は西光の評伝において、西光の思想形成において天皇制はきわめて重要だと指摘する。日本社会の構造において天皇・貴族と部落は対極かつ表裏一体であり、天皇制をなくさねば部落差別はなくならないと「貴族あれば賤族あり」 *XLVII と唱えた全国水平社の松本治一郎(1887-1966年)の存在をして、水平社が創立当時から天皇制と対立していたと見るのは誤りだと主張している *XLVIII 。
出獄後、北方の地に落ち着いた西光は、一時は画工として身を立てようと考えた。この時期、阪本のために戸襖絵《醍醐の花見》や、生家の西光寺に壁画《天女の舞》を、大和高田市は宗願寺に壁画《釈迦》、同寺に天井画《龍》を描き残しているが、北方区長となり区民の生活相談などで多忙を極め、画業の継続はできなかった。その後、皇国農民同盟奈良県連合会を結成し、1944年には勤労報国隊の一員として福岡・三井三池炭鉱での労働にも従事した。敗戦翌月の9月15日、「日本がその悪業のために敗れ、自分がその悪業を浄化するための真の知恵と気力を欠い」たと、慚愧の念から忠魂碑の前でピストル自殺を図り、未遂に終わる *XLIX 。侵略戦争を支持した己に厳しい反省を加えるが、天皇の責を問うことはなかった。西光は日本国憲法を、敗北した日本にとっての「金鵄」と捉えた。天皇制のもとの西光の不戦・平和思想「和栄運動」の実践は生涯続いた。
1970年に75歳で没する西光が、1960年代に描いた《毀釈》と題された掛軸がある 。支援者への返礼品として描かれるも、西光の手元に残された*LI 。絵の中では、冬枯れの木と阿形の狛犬を背に、僧侶が焚き火で暖を取っている。僧侶のモデルは西光自身といわれる。僧侶を暖めるのは、仏壇や木造仏の一部などの残骸に焚きつけた火だ。それらは足元の手斧により、僧侶自身が破壊したのだろう。画題の毀釈とは「釈を毀る」、つまり釈迦の教えを壊すことを意味する。廃仏毀釈とは明治政府の神道国家教化政策に依拠した仏教排斥運動だ *LII 。この絵では、僧侶自らが毀釈を行う。それは強制されたものではない。僧侶はほくそ笑んでいる。苦渋や諦念は窺えない。成し遂げられた毀釈により立ち上る煙とともに視線を上げれば、背後の狛犬もまた大口を開け高笑いしているかのようだ。僧侶は自らが寄って立つ根拠を打ち壊し、これに熾した火で自分を生かした。これが西光晩年の自画像である。

制作年:1960年代
図版典拠:『西光萬吉の絵と心』西光萬吉画集刊行委員会編、大阪人権歴史資料館、1990年
協力:一般社団法人西光万吉顕彰会
改名後の姓が生家の西光寺に由来しているように、西光にとって仏教の教えは自身の根幹をなすものであった。天皇への親しみとともに、西光はキリスト教にも多大な関心を寄せた。水平社宣言に「犠牲者がその荊冠を祝福される時が来た」と書き、荊冠旗がナザレのイエスが十字架の上で被せられた荊の冠をかたどっていることからも、宗教思想を人間賛歌へと接続する志向は明らかである。《毀釈》は西光の信仰との決別を意味すると説明されるが *LIII 、この絵の持つ意味はそれだけにとどまるものではないだろう。寺の長男に生まれるも、つくられた人種差別により僧侶となることはなかった自らを僧侶として描き、依拠するものをその手で打ち壊し、それにより自分を生かす姿を絵にとどめた。西光の笑みは転向の完遂への満足とも、転向そのものへの反語表現にも取れる。《毀釈》は、この国の「転向」の自画像であるように筆者には思われる。その意味があなたたちに分かるかと、絵の中で西光は問いかけ続けている。
*XLIII:梅沢利彦「西光万吉の栄光と悲惨──天皇主義への転落」『文学の中の被差別部落像──戦前篇』明石書店、1980年を参照のこと。
*XLIV:福田雅子『証言 全国水平社』日本放送出版会、1985年、66頁。
*XLV:師岡佑行『西光万吉』清水書院、1991年、21頁。
*XLVI:西光萬吉画集刊行委員会編『西光萬吉の絵と心』大阪人権歴史資料館、1990年、112頁。
*XLVII:松本治一郎『部落解放への三十年』近代思想社、1984年、219頁。
*XLVIII:師岡佑行『西光万吉』清水書院、1991年、83頁。
*XLIX:山田敬義「故郷柏原北方と西光さん」『部落解放』247号、解放出版社、1986年、30頁。
*L:筆者の調査により、《毀釈》は西光万吉顕彰会所蔵のものと個人蔵のものとで同名の作品が二作存在することがわかっている。ここでは『西光萬吉の絵と心』に掲載された個人蔵《毀釈》を扱う。
*LI:西光萬吉画集刊行委員会編『西光萬吉の絵と心』大阪人権歴史資料館、1990年、106頁。
*LII:畑中章宏『廃仏毀釈──寺院・仏像破壊の真実』ちくま新書、2022年、9頁。
*LIII:師岡佑行『西光万吉』清水書院、1991年、204頁。
3 「膠を旅する」展——生と死をつなぐ営みをたどる
1985年に大阪人権歴史資料館として開館し、2020年に休館に追い込まれた大阪人権博物館では、西光万吉の盟友であった阪本清一郎が経営した阪本製膠所で使われていた巨大なれんが造りの煙突と、膠の原料となる皮屑を煮込む鉄製の大釜(和釜)を見ることができた。阪本は家業を引き継ぎ、掖上村の膠産業を隆盛させたが、全国的に膠産業は斜陽の一途をたどる。同館の阪本製膠所の遺構は同製膠所が廃業した際、持ち込まれたものだった。
膠は「煮皮」に由来する。獣や魚類の皮・骨などを石灰水に浸してから煮て凝縮し、冷やし固めてつくられる粗製のゼラチンである。古来、膠はテンペラ画や、日本画にも欠かせない画材であり、定着剤の役目を持つ。その意味で、日本画を日本画たらしめるものが膠であると言ってよい。なぜなら日本画の岩絵具とは鉱石を砕いてつくられた粒子であり、それだけでは接着性を有しないからだ。煮溶いた膠液を岩絵具に加えなければ、たやすく支持体から剥がれ落ちてしまう。そのような日本画における「伝統素材」としての膠は、この国の皮革産業や部落問題と深い関わりを持っている。しかしこれまで、膠の物質的特性のみならず、日本画や日本美術史と、屠場とこれを仕事にする人々や部落解放運動の歴史が重ねて論じられる機会は多くはなかった。
そんな中、膠の文化史に焦点を当てた美術展覧会が開催された。日本画家・内田あぐり(1949年-)監修による「膠を旅する——表現をつなぐ文化の源流」展[会期:2021年5月10日―6月20日、会場:武蔵野美術大学 美術館・図書館]である。50年にわたり和膠を用いて日本画を描き続ける内田は、手工業による国産膠の生産が終わると知ったことを契機に、美術史家や研究者たちとともに「膠とはいったい何か」を探るため、共同研究に取り組み始めた。研究成果は展覧会とともに『膠を旅する』(国書刊行会、2021年)にまとめられている。同書冒頭の内田と画家・山本直彰(1950年-)と膠の研究者・上田邦介(1939年-)による鼎談では、上村松園(1875-1949年)の日本画《序の舞》(1936年制作)における絵具の剥離と「膠の限界」が話題にのぼり、日本画に付随する文化の終わりも示唆された。手工業による国産膠の生産終了は、時代の移り変わりというだけではない。「終わりの始まり」でもあるのだ。そのような日本画の過去・現在・未来を見据え、内田たちは、北海道網走市、大阪浪速区・貝塚市、兵庫県姫路市、東京都・墨田区など膠が生み出される場所を訪ね、調査を行った。
膠を軸に文化の源流を探るため各地を調査した内田たちの研究は、トランスナショナル transnationalな可能性に開かれている。北海道での北方少数民族の動物資源利用の調査で明らかになったのは、先住民族の文化の民族固有性である。北方少数民族は生きものの皮で生活に必要な様々な物をこしらえていたが、例えば「皮なめし」ひとつをとっても、カムチャッカ半島の先住民族コリヤークは内陸と沿岸部で大きく二つの集団に分かれ、保有する技術は異なっているという。魚皮を縫製した「魚皮衣」はロシアと中国北東部の国境に接するアムール河流域からサハリン、北海道にまで分布するが、ナナイ、ウリチ、ニブフ(ギリヤーク)、ウイルタ、アイヌの魚皮衣にはそれぞれに民族固有性がある。そしてここには、先住民族間の文化のつながりが見て取れるという。内田たちの膠研究からは、豊かな交易を行い固有の文化を持つ北方少数民族が、国境線が引かれた世界地図という「近代」に暴力的に包摂されていく過程を看取することができた。
「膠を旅する」展の会場ではたくさんの乾皮と膠が配置され、北方少数民族による皮革を巧みに利用した衣類や道具、調査にまつわる写真に加え映像なども紹介された。膠をめぐる文化の多様性が実物資料によって示されるとともに、同館が所蔵する内田の作品と物故作家らの日本画の展示も行われた。麻田鷹司(1928-1987年)《牛舎》(1952年)、毛利武彦(1920-2010年)《檻》(1958年)、丸木位里(1901-1995年)・丸木俊(1912- 2000年)《原爆の図 高張提灯》(1986年)だ。麻田24歳の作である《牛舎》は、ジョルジュ・ブラック Georges Braque(1882-1963年)の画面構成を参照し、これを日本画に適応できるかを試みた作品だという *LIV。画面上の乳牛と人間の筆致にさほどの区別はなく、世話をする/されるという関係性がゆるやかに溶解していくかのようだ。しかしやはり、描かれた牛舎は、乳牛と人間の共生よりも管理の側面が主題とされているように見える。《檻》は毛利38歳の作である。とげとげしい3種の鶏籠が画面全体を占めている。ここで鶏籠は鑑賞のためというよりも、収容する檻として描かれていることがわかる。他方、檻の中の金色の鳥はわれ関せずの様子だ。直線が多用された檻の格子が、支持体に切り込まれた無数の裂け目のようにも映る。麻田、毛利は内田の師に当たる。ここでの展示は、動物の管理と観賞を描いた日本画の検討というだけでなく、同大学における日本画教育の変遷が示されていた。そしてまた、膠の歴史性をふまえて鑑賞するともっとも見方が変わると思われたのは、丸木位里・丸木俊《原爆の図 高張提灯》である。
内田たちの共同研究を機に大阪人権博物館から同館に寄贈された本作は、膠による修復を経て初公開された。位里85歳、俊74歳の作である《原爆の図 高張提灯》は、1986年に大阪部落解放同盟主催「いのち、愛、人権」展に出品されるも、「知られざる原爆の図」といわれてきた。本作は、「原爆の図」シリーズ15編の番外編として、広島は福島町の被差別部落の被爆を描いている。画面右下には「広島の被差別部落では原爆のとき 軍隊に見張られてどこへも逃げ出せなかった 医療班も入らなかった」と書かれているが、後年の調査でこれが事実ではないことが明らかにされている。これについて同館学芸員・北澤智豊は、同和教育の教科書に掲載された俊の文章「いまようやくここに立って」を引きながら、「原投下という惨劇のなかで、「高張提灯」を大きな歴史のなかで見過ごされてしまった、日本社会構造としての根深く存在する差別問題における一つの象徴」と本作の制作意図を説明し、本作における位里によるたらし込み技法の水墨画表現の効果にも言及している *LV 。
同展において内田らの共同研究をふまえて《原爆の図 高張提灯》を実見した際、この絵を絵としてつなぎとめている膠とは、生きとし生けるもの、その「生と死」をつなぐ営みなのだと気付かされた。そしてまたそのような膠の特性は、本展監修者・内田あぐりの作品においても顕著である。2000年以降、内田の作品は、初期からモチーフとされてきた人体がトルソー形に近づき、楮紙に糸を張るなどの作為と物質性の強い素材が画面上に出現するようになる。そのような種々の要素が膠によってつながれている。「膠は接着剤というよりも、動物の体液で描いているという意識が私にはある」と内田は言う *LVI 。おそらく内田に「動物の体液で描いているという意識」があったからこそ、膠への関心が本展のような射程の広い共同研究へと結実したのだろう。文化にはつねに明暗があるが、それが〈暗部〉だけにとどまるかは語り手次第だ。膠がなければ成立しなかったもののひとつがこの国の美術である。その事実をこそ「膠を旅する」展は提起していた。
*LIV:麻田鷹司『麻田鷹司画集:作品1942−1979』講談社、1980年、4頁。
*LV:北澤智豊「日本が表現をめぐる三つの所蔵作品」『膠を旅する』国書刊行会、2021年、188-189頁。
*LVI:内田あぐり「膠と私」『膠を旅する』国書刊行会、2021年、234頁。
4 舟越保武《ダミアン神父》——差別と偏見と表現とを問う
本稿では、個別具体的な問題を見つめることを指針とし、部落解放運動の創始者・西光万吉の絵画から「転向」の主題を読み解き、内田あぐり監修の展覧会「膠を旅する」から動物産業の文化史と日本美術の関わりの一則面を捉えることを試みた。終節では舟越保武が手がけた《ダミアン神父》をめぐる論争を取り上げる。この論争では、ハンセン病にかかる差別と当事者の表象、そして美術館の役割が厳しく問われた。本稿の終わりにこの論争を取り上げることで、日本美術史と人種主義の関わりをいかに問うかの筆者なりの解を示したい。
彫刻家・舟越保武(1912-2002年)は岩手に生まれ、高村光太郎が編纂・翻訳した『ロダンの言葉』を読んで彫刻家を志した。東京美術学校彫刻科を卒業後、ほぼ独力で大理石による彫刻を習得する。当時の日本には大理石彫刻家がほとんどいなかったこともあり、粘土による彫塑と大理石による彫刻を手掛けた舟越は彫刻界でも特異な存在であった。1950年、長男の死を機にカトリック教徒となる。以後、キリスト教を主題とした作品を制作に取り組み、1962年には、1597年2月5日に豊臣秀吉の命により長崎で磔刑に処された26人のカトリック信者を記念する《長崎二十六殉教者記念碑》を長崎・日本二十六聖人記念館のために制作した。また、1971年には、江戸幕府のキリシタン弾圧に対する反乱であり、日本の歴史上最大規模の一揆といわれる島原の乱を題材にした《原の城》を制作する。本作は1972年にローマ法王庁に贈られ、舟越は翌73年、ローマ法王より「大聖グレゴリオ騎士団長」の勲章を授与されている。
キリスト教を主題とする舟越の彫刻のなかでも、代表作のひとつとされるのが《ダミアン神父》(1975年)だ。この作品は、もとは《病醜のダミアン》という名であった *LVII。ここで舟越は、19世紀の終わりにハワイ諸島はモロカイ島のカラウパパに隔離されていたハンセン病患者の「救済」に献身したベルギー人神父・ダミアンを塑造によって彫像化した。ダミアンは私財を投じて聖堂や病舎を建て布教に励むが、ハンセン病で亡くなったとされる *LVIII 。「人道的な人間愛」「信仰に人生を捧げた崇高さ」「尊い犠牲」「勇気ある自己犠牲」などの形容詞で語られる彼の人生を顕彰するため、舟越は《病醜のダミアン》を制作した。

制作年:1975年
岩手県立美術館蔵
筆者撮影
本作は、岩手県立美術館、埼玉県立近代美術館、兵庫県立美術館がそれぞれに所蔵しているが、埼玉県立近代美術館では長く本作の特別な展示が行われていた。それは埼玉県立近代美術館が開館して1年後に起こったある抗議に端を発している。当時、同館の3階までの吹抜けの底面には、いずれもキリスト教を背景に持つ彫刻、ジャコモ・マンズー《枢機卿》(1979年)、クロチェッティ《マグダラのマリア》(1973-76年)、舟越保武《病醜のダミアン》が展示されていた。1983年、ハンセン病の「東京・退所者の会」のひとり、ハンセン病回復者で文筆家の冬敏之(1935-2002年)が同館を訪れ、《病醜のダミアン》における病の表現がハンセン病についての誤った認識を与えかねないと彫刻の撤去を求めた。冬の抗議を受け、当時の埼玉県立近代美術館館長・本間正義らは彫刻の展示室からの撤去を決めた。とはいえここでの撤去とは、収蔵庫にしまい込むのではなく応接室に展示し、受付で見学希望を申し出る者には職員が個別に案内し、鑑賞してもらうというものだった *LIX 。吹き抜けから《病醜のダミアン》が移動された1984年1月から1999年8月6日まで、15年の時間をこの彫刻は応接室で過ごすことになる。冬は《病醜のダミアン》を所蔵する岩手県立博物館と兵庫県立近代美術館にも展示の中止を求めたが、両館はこれに応じていない。
ところで、ハンセン病は極めて感染力の弱い細菌による病であり、現在この国に感染源として恐れるべきものはない。早期に治療すれば身体に障害が残ることは少なく、治療薬により完治する病気だ。偏見や差別の烙印と見なされた身体の変形は、運動神経麻痺や知覚神経麻痺による受傷に起因する後遺症障害による。これらは何度確認してもしたりることはない。しかしながら、元患者たちは長く偏見と差別に苦しめられてきた。日本においては、治療薬が確立されつつあったなか、療養所の園長3名が隔離継続を提言した、いわゆる「三園証言」と国民の無関心により、「社会防衛」「公衆衛生」の名目でハンセン病者の隔離は継続・正当化され、終身隔離・患者撲滅政策は改められることがなかった。強制隔離を固定化する「らい予防法」は1996年まで継続した。1998年、鹿児島と熊本の入所者13人が、熊本地裁に「らい予防法は基本的人権の尊重を定めた憲法に違反し、強制隔離などで人権侵害を受けた」と補償を求めて提訴する。最終的に900人を超える入所者が原告となったこの裁判の2001年の勝訴を経て、国は控訴を断念し、国家による不法行為についての謝罪を表明した。
冬敏之が《病醜のダミアン》に対して声を挙げたのは、らい予防法違憲国家賠償請求訴訟以前のことである。以下は、1984年の『多磨』65巻3 号に公開された冬の意見文だ。
ハンセン病は幼児を除いてほとんど感染しないというのは、すでに早くから知られていた事実である。それが証拠には、職員の中でたった一人も感染したり発病したりした人が出ていないというのが、本病の啓蒙に当っての有力な武器であった。が、それに水をさすかのように「絶対隔離主義者」たちが言うのが「ダミアンがいるじゃあないか!」という言葉であった。これはたしかに応えた。多少とも社会復帰など考えている者にとっては、神経を逆なでされる思いであったろう。
──冬敏之「「病醜のダミアン」像」『多磨』65巻3 号
[…][《病醜のダミアン》は]それが秀でたものか否かを別として、やはり醜く恐ろしいのである。それを見て深い感動を覚えるという人がいるのは否定できないけれど、芸術的な感動を覚える前に、その像の恐ろしさに立ちすくむであろう小学生や中学生がいるであろうことも指摘しておく必要があろう。[…]現実にハンセン病がまだ絶滅されていない限り、この像のイメーシは容易に今の患者(菌の有無とか治癒などにかかわりなく)や回復者へもつながってゆくのである。
冬の文面からは、患者とともに生活を送り発病したとされるダミアン神父の存在が、強制隔離を自明とする「絶対隔離主義者」に利用され、社会復帰を望む回復者の障壁となる可能性についての恐れが窺える。現在であれば、「患者・元患者とその家族の名誉回復を図るために、ハンセン病問題に関する正しい知識の普及啓発による偏見・差別の解消を目指す」ことを目的として、2007年に再開館した国立ハンセン病資料館でハンセン病についての適切な知識や、隔離政策の誤謬を知ることができる。しかし当時はまだそのような状況ではない。ゆえに、《病醜のダミアン》についての冬の危惧は切実なものである。他方、これに異を唱えた者がいた。冬と同じく元患者で文筆家の伊波敏男(1943年-)である。伊波は1985年に『多磨』66巻12号に「ダミアンの沈黙」を寄稿し、「「病醜のダミアン像」について」を「芸術家が攻撃を受けている。作品の生命が否定されようとしている」と反論した。
ハンセン病を知ると言うのは一体どういう事を指すのだろうか? あるいは、当事者体験の資格が必要とでも言うのだろうか。それとも北條民雄の文学まで遡ろうとでも言うのだろうか。
──伊波敏男「沈黙のダミアン」『多磨』66巻12号
我々が新しいタブーを作り、芸術・文学を規制する愚は避けなければならない。科学的誤認への批判姿勢と芸術表現への批判姿勢は、自ずと違うルールで律するのは当然の理である。
ダミアン像は観る人に感動は与えはしても、決して嫌悪感を与える低劣な作品ではない。しかし、百歩譲ってこの作品から「醜さ」しか感得し得ない人が居たとしても、何も恐れる事はない。感動を失った人の心には「病醜ダミアン」像はハンセン病への偏見助長と言う「焼付け影響力」など与えはしないからである。
伊波はここで埼玉県立近代美術館の対応を批判し、「「ハンセン病」へのいわれのない偏見が今なお、実在するからこそダミアンに語らさなければならない。ダミアン像に沈黙を強いる道を私達は、断じて選ぶべきではない」と呼びかけた。冬と伊波の論争からは「元患者の社会復帰」の個別で多様な事情が浮かび上がり、ダミアンという人物への共感の違いも窺える。1999年に冬は舟越に作品名を《ダミアン神父》に変更してほしいと求め、舟越はこれを受け入れている。こうして《病醜のダミアン》は《ダミアン神父》となった。題名変更とともに、国立ハンセン病資料館が監修した病気についての説明文を付すことが決まり、同年8月、《ダミアン神父》は応接室から元の吹き抜けの底面へと戻された *LX 。
実際に《ダミアン神父》を鑑賞すると、その大きさに驚く。2メートル近いこの彫刻にと向き合うと、おのずと見下ろされることになる。ダミアンを見上げる自分が、まるで子どもや加護対象になったように感じられる。舟越がダミアンに施した「病醜」は、顔と手に集中している。顔の変形にとくに視線が集まるようにつくられているが、ダミアンと視線は合わない。ダミアンの両目には穴が穿たれており、そこにはぽっかりとした空洞がのぞいている。ブロンズ製の彫刻は内側に空洞を有する。《原の城》も同様だが、虚空を内包していることを本作もまた強調する。
《病醜のダミアン》が偏見を助長するかは、彫刻に表現された醜さや恐ろしさのみを指標とすることはできない。社会状況により鑑賞者の見方は大きく変わるからだ。本作において舟越は「美」の否定的命題としての「醜」をあえて持ち出すことで、ダミアンに対する畏敬の念を込めたのであろう。舟越の気概は作品の細部に満ちている。しかしながら、ダミアンの「救済」が美談として語られ、作品化される際、本来であれば、差別に苦しみ名誉回復の機会を奪われ続けた、名もなき患者たちにこそ光が当てられてしかるべきではないだろうか。ダミアンの「献身」は素晴らしいものであったことに違いはない。しかし、ダミアン神父のみが主題化され、美化されるならば、それはキリスト教布教の正当化以上のものではないように思われる。
ここで今一度、人種主義の構造を振り返れば、酒井直樹が「「人種」は対話の回路から外された第三者としての他人を認知・同定するためのホモソーシャル(均質志向社会性)な範疇」*LXI であると指摘するように、差別に共通するのは差別される側にのみ固有の「特殊性」があるとし、そのような烙印を押す側の「特殊性」は「無徴」として不問に付されることである *LXII 。関連して、冨山一郎は「観察される客体である「アイヌ」や「琉球人」は、自己と他者の限界をふちどる多くの徴候にまみれ、たえず言及されるのに対して、「日本人」自身は直接言及されないまま、沈黙しつづける」 *LXIII と主張している。
あと三十年か四十年もすれば、ハンセン病への偏見の問題は、日本では社会問題として話題とすることもなくなってしまうだろう。偏見がなくなるのではなく、偏見を生み出した主体ともいうべきハンセン病が、ほとんど消滅してしまうのである。平均年齢が六十二歳の入所患者は、三十年のちにどれだけの人が生き残っているだろうか。入所者の最後の世代に属する私にしても、あと三十年も生きられるとは考えられないし、仮に過去ハンセン病であった人がいたとしても、病気そのものを知らない世代と交代しているであろう未来では、もう偏見の生ずる余地はなくなっているにちがいない。それまでのしばらくの間、「病醜のダミアン」像によって無用の波風を立ててもらいたくないというのが、社会復帰者の大方の気持であると思う。
──冬敏之「「病醜のダミアン」像」
ここでの冬の問題提起からすでに30年が過ぎた。偏見がなくなるのではなく、偏見を生み出した主体としてのハンセン病がなくなると冬は書いた。言うまでもなく、偏見を生み出すのは病そのものではなく、病と患者に偏見を押し付ける人間によってである。前述のように、個別具体的な差別が普遍的な人権教育に流し込まれ、部落問題とともにハンセン病を知る機会も減少している。それでいいのだという声もあるだろう。何も知らない者にわざわざ問題を知らせる必要はなく、放置すれば自然と解決するという「寝た子を起こすな」言説に代表される対策不要論は根強い。しかしながら第1章でふれたように、結婚差別は依然として過去のものでなく、新型コロナウイルスの世界的流行が明らかにしたように、感染症への偏見もまた過去の遺物ではない。部落解放・人権研究所が編集した『部落問題人権事典』の「寝た子を起こすな」の項目には、「いずれも問題解決への消極的姿勢であるゆえに否定すべきものだが、差別の残酷性を熟知しているための〈寝た子〉と、差別を黙認したうえの〈寝た子〉とが有する含意は区別されねばならない。〈寝た子を起こすな〉の発想は今日、〈部落分散論〉や〈部落解消論〉の形態をとり、差別撤廃をめざす一切の取り組みを事実上ないがしろにする反動的イデオロギーの役割を果たしている」と記されていることを無視することはできない。
だからこそ、埼玉県立近代美術館における《ダミアン神父》の15年の特別展示は、決して意味のないことではなかった。こうして冬と伊波の議論と舟越の決断、そして美術館の対応を検証することができるからだ。とはいえ残念でならないのは、現状、岩手県立美術館、埼玉県立近代美術館、兵庫県立美術館のいずれもが、作品名変更の事実だけでなく、《ダミアン神父》をめぐる論争や舟越の対応についての説明を控えていることである。当事者の訴えを受けとめ、舟越は《病醜のダミアン》を《ダミアン神父》に改め、国立ハンセン病資料館が監修した解説が作品に付された。ここで作家が下した決断を、その選択に導いた者たちの存在を、なかったことにするべきではない。それらに口をつぐむ態度は、「寝た子を起こすな」言説と根を同じくするものだ。
日本美術史と人種主義の交点は、いま、ここにある。わたしたちはすでに、ずっと、そこに立ってきた。この国初めての人権宣言である水平社宣言から100年が経った。次の100年にどのような社会を望むのか。それは、何を語らんとするかにかかっている。
※本論考執筆に際してご協力くださった国立ハンセン病資料館学芸員・西浦直子氏と吉國元氏に、この場を借りて深く感謝いたします。
*LVII:舟越保武『巨岩と花びら 舟越保武画文集』ちくま文庫、1998年。
*LVIII:やなぎやけいこ『二つの勲章──ダミアン神父の生涯』ドン・ボスコ社、1994年。現在、ハンセン病が原因で死に至ることはほとんどない。
*LIX:前山裕司「舟越保武《病醜のダミアン》を展示しないという決断」『aica JAPAN NEWS LETTER』第6号、美術評論家連盟、2016年。
*LX:この15年の間に埼玉県立近代美術館の《病醜のダミアン》は、国立ハンセン病資料館の前進となる高松宮記念ハンセン病資料館1階ロビーにおいて、1993年11月1日~12月20日まで展示された事実がある。館のリニューアル経て、現在は《ダミアン神父》は常設展示ではなくなっている。
*LXI:酒井、前掲書、283頁。
*LXII:酒井、同上。
*LXIII:冨山一郎「国民の誕生と「日本人種」」『思想』845号、1994年、39頁。
両論考へのご意見ご感想は、こちらから投稿いただけます[※投稿は2023年5月末に締め切らせていただきます]。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUE9m8JqkmlXX6Tt20adwHoXUDwx69a31euPMU7XGpzMUXUA/viewform?usp=sf_link
小田原のどか(おだわら のどか)
彫刻家、評論家、出版社代表。1985年宮城県生まれ。多摩美術大学彫刻学科卒業後、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻にて修士号、筑波大学大学院人間総合科学研究科にて芸術学博士号取得。著書に『近代を彫刻/超克する』(講談社、2021年)。主な共著に『吉本隆明:没後10年、激動の時代に思考し続けるために』(河出書房新社、2022年)など。主な展覧会に「近代を彫刻/超克する 雪国青森編」(個展、国際芸術センター青森、2021年)、「あいちトリエンナーレ2019」など。経営する出版社から『原爆後の75年:長崎の記憶と記録をたどる』(長崎原爆の戦後史をのこす会編、書肆九十九、2021年)、『彫刻2:彫刻、死語/新しい彫刻』(小田原のどか編著、書肆九十九、2022年)を刊行。
山本浩貴(やまもと ひろき)
文化研究者、アーティスト。1986年千葉県生まれ。一橋大学社会学部卒業後、ロンドン芸術大学にて修士号・博士号取得。2013~2018年、ロンドン芸術大学トランスナショナルアート研究センター博士研究員。韓国・光州のアジアカルチャーセンター研究員、香港理工大学ポストドクトラルフェロー、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科助教を経て、2021年より金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科芸術学専攻講師。単著に『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論新社、2019年)、『ポスト人新世の芸術』(美術出版社、2022年)、共著に『トランスナショナルなアジアにおけるメディアと文化 発散と収束』(ラトガース大学出版、2020年)、『レイシズムを考える』(共和国、2021年)、『東アジアのソーシャリー・エンゲージド・パブリック・アート 活動する空間、場所、コミュニティ』(ベーノン・プレス、2022年)など。
〈書籍について〉
2023年刊行、月曜社より刊行予定。編著者は小田原のどかと山本浩貴。参加者は、千葉慶、穂積利明、飯山由貴、加藤弘子、北原 恵、琴 仙姫、北澤憲昭、吉良智子、小金沢 智、小泉明郎、國盛麻衣佳、菊池裕子、馬 定延、中嶋 泉、長津結一郎、大坂紘一郎、嶋田美子、富澤ケイ愛理子、吉國元(アルファベット順、敬称略)。デザイナーは真崎嶺。
→企画詳細ページ https://www.odawaranodoka.com/konokuni
→講義詳細+チケット申し込み https://konokuni.peatix.com/
