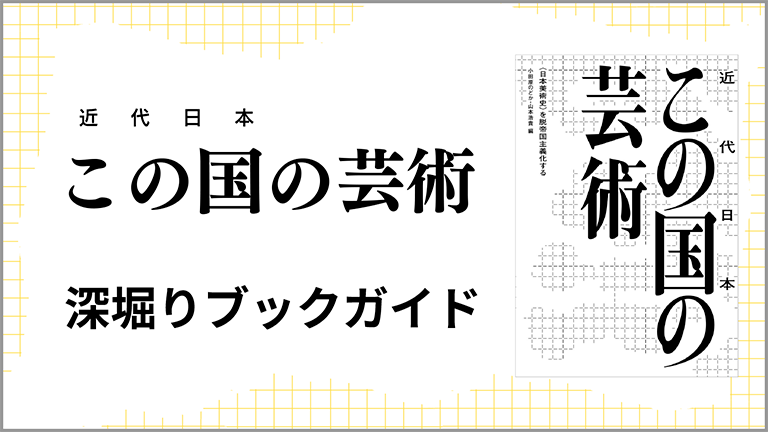Digging my way to London
大竹伸朗、21歳、パンク吹き荒れるロンドンでみたものの大部分
ロンドンへの穴掘り 大竹伸朗
1977年5月3日から1年あまりをイギリスで過ごした。
その大半はロンドンだ。入国半年後、観光ビザが切れヴィクトリア駅前から激安「マジックバス」で10日間程パリに出た以外は結局一年あまりをロンドンで過ごした。それが初めての海外での一人暮らしだった。
〈中略〉
ロンドンに着いて3ケ月あまりが経った8月13日の土曜日の午後、ふと暇つぶしにポートベロー・ロードで毎週末開く蚤の市に寄ってみようと思った。しばらく雑踏の中を進み、道を横切る鉄道高架下を括り抜けると広場の様な場所に出た。店というよりは素人の持込みが並ぶ場所だったのかもしれない。その中に透明のビニール袋に詰めたマッチのラベルを手に、またそれらを貼り込んだノートブック2、3册をシートの上に並べている赤ら顔の中年男がいた。その袋の中のラベルを見た瞬間、自分がやりたいことはコレだと思った。それは生まれて初めての感覚だった。なにがコレか具体的なことは全く分らなかったがコレだと確信するものを感じた。それらを4ポンドで購入し急いで部屋に持ち帰りノートブックに貼り込んだ。その日を境に「貼る」ことが日常の中で焦点を結び出した。
二度と出会うことはないであろうその男が手にした大量のマッチのラベルとの出会いは「貼る」という方法を今迄とは異なる角度から意識の中に引き込んだ。バラバラにぶら下がっていた「写真」と「絵」と「貼る」ことの間に何か引き付けあう力が生じたような、また自分の内側に流れる時間に触れた感覚とでもいうのか、ロンドンへ来て何か初めて前に進み出したようなそんな気がした。
「写真」と「絵を描く」こと、そして何かと何かを「貼る」ことが自分の中で密接に結びついていることを意識するようになるには、その出会いから数年の時間を要したと思う。
「貼ること」を「コラージュ」とかたずけてしまうのは簡単だが、自分にとって「貼ること」はどうもそう単純なものではないようだ。あれから27年経過した今でも自分の中にある「貼ること」への「わからなさ」の力によって今日もまた貼り込むことを繰り返している。しかしわからないながら、あの日以来自分のものであれ他人のものであれ、「写真」と「描く」ことは「貼る」ことと常に同時に在り続けていることは確かだ。「答え」というものは何事に於いても後から見てみれば全く呆気無く単純なことが多い。が、至近距離ほど見えにくいものでもある。 あの日ポートベローの見知らぬ男と出会った瞬間、「見つけた!」と思った答はその時、再び新たな疑問とわからなさに突入した時でもあったのだと思っている。
この本にあるものはすべて1977年5月3日から翌78年4月28日までのイギリス滞在中に撮影し描き貼ったものである。ロンドンでの1年間は引っ越しや移動の連続で常に荷物をできるだけコンパクトにしておく必要があったため自然とカメラとノートブックという形になっていったのだろうと今になって思う。油絵は一通りの材料を揃える金銭的余裕もなく場所も取り、また絵の乾燥が遅く運搬に不便ということもあり結局一点も描かなかった。何点か描いたアクリル画も引っ越しや帰国の際世話になった知人友達にあげてしまい、それらの絵も数点の写真の中にあるだけだ。 写真やスケッチと一緒に出てきたノートは今迄てっきり通常の「日記」だと思い込んでいたのだが、今回改めて見てみるとほとんど「出納帳」であったことに気がついた。それまでも日記をつけるという習慣はなかったが、結果的に思いや感情を文章化した日記より一見無味乾燥な出費の数字記録の羅列を眺める方があの頃の日常のディテイルがより鮮明に蘇ってくるような感じがした。
「日記」を書くつもりが自分の意志を超え、結果的に少ない所持金の出し入れを事細かに記した「出納帳」になってしまったように、当時その場所で撮り続けた「写真」は、初めて経験する異国での日常の中で、それまで日本という国で染み付いた微妙な間会いを取りながら記した「出納帳」的なものだったのかもしれないとも思える。今、改めて写真の数々を眺めているとなにかその時の「出納帳日記」に似た無意識の結果のようなものを感じるのだ。もちろんこんな比較は十分に味気ないようにも思えるが、一見対極に位置するそんな関係の中に、本質は素知らぬ顔であるのかもしれない。