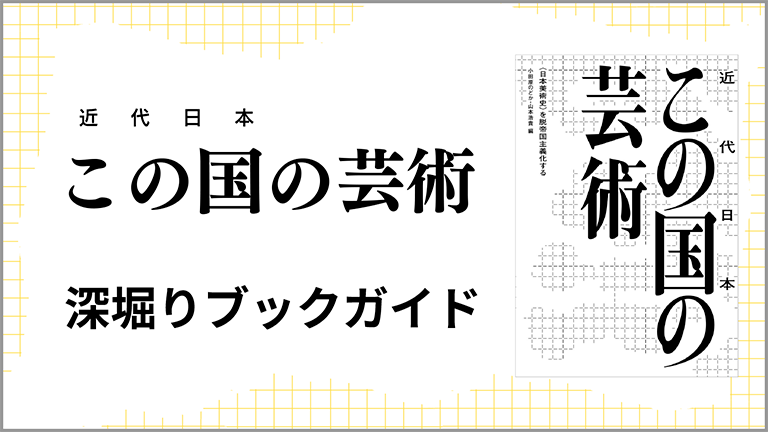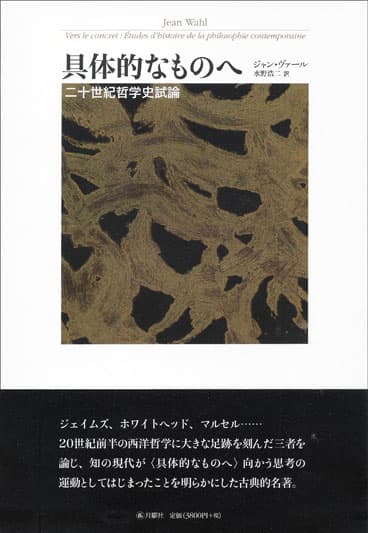ジェイムズ、ホワイトヘッド、マルセル……20世紀前半の西洋哲学に大きな足跡を刻んだ三者を論じ、知の現代が〈具体的なものへ〉向かう思考の運動としてはじまったことを明らかにした古典的名著。ヴァールの著作の訳書としては実に33年ぶりとなる。
シリーズ「古典転生」第3回配本。
「ジャン・ヴァールの著書の名『具体的なものへ』は、ここ最近50年の哲学の動きを十二分に言い表している。体系や理論より前に、経験そのものを拡大することが求められるのである。今世紀のはじめ以来、概念的なものを退けて、感じられるものの権利を回復しようとする弁証法的運動、あるいは少なくとも反対運動が、認められる。19世紀にあれほど大きな威信を享受していた認識論は、その本来の地位に、すなわち二次的な地位に戻る。意識という観念そのものが問題とされる。あるいは少なくとも、個人をそれ自身の主観性に閉じ込めるかわりに、意識はしばしば、ある状況のなかに他人と居合わせることといったものになる。哲学体系という概念が評判を失ったこと、多くの問題が解体したこと、価値を前にして存在の影が薄くなっていること、具体的な体験される実存と一体となろうと哲学が努めていることは、真実な変化が起こっていることのしるしである。」
――ジャン・ラクロワ『フランス現代思想の展望』1966年(野田又夫・常俊宗三郎訳『現代フランス思想の展望』人文書院、1969年)
「当時、われわれのあいだで一冊の本が大いに成功を博していた。ジャン・ヴァールの『具体的なものへ』である。」
――サルトル『方法の問題』1960年(平井啓之訳『方法の問題』1962年)