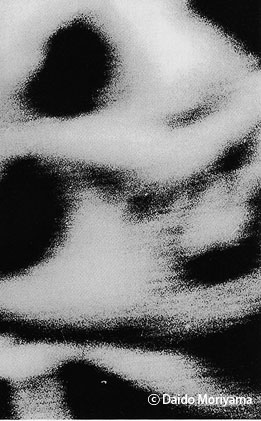森山大道のOn the Road
番外講義編
沖縄県立博物館・美術館 2014年1月25日
大竹昭子
※2014年1月25日に沖縄県立博物館・美術館でおこなわれた「森山大道 終わらない旅 北/南」展シンポジウムでの講演の採録です
はじめまして、大竹昭子です。沖縄には何度も訪れており、トークをする機会もありましたが、写真について語るのは今日がはじめてです。
まず最初に申し上げておきたいのは、わたしは一介の物書きだということです。よく「写真家」とか「写真評論家」という肩書きをつけられるのですが、わたしはそうは思っていないし、違和感があります。観客のみなさんにとってはどうでもいいかもしれませんが、わたしは物書きの立場から写真と関わること、写真のリアリティーをどう言葉にするかが、自分の課題だと思っているんです。 写真について書かれた本を読んだことのある方はご存知だと思いますが、たいがい難解で、わかりにくいです。だれもが写真を撮り、その結果をメールで交換し、楽しみあっていて、かつてないほど写真が親しまれているというのに、写真について語ると難解になる。このギャップがいつも気になるんです。
これから森山大道さんの写真について語るわけですけど、終わったときに、写真がどういうものなのかが少しだけわかった、という感想をもってお帰りいただけるように話していきたいと思います。 というのは、森山大道さんの写真を語っていけば、おのずと写真の深層に到達するからです。彼のなかでたえず「写真ってなんだろう」という問いが繰り返されており、しかも撮り方が一定でテーマが変わらないゆえに、写真の本質が浮き彫りになるのです。
まず写真の一般的な話からはじめましょう。
ものすごく大雑把に言って、写真は2種に大別できます。「地図を制作するような態度で撮られる写真」と、「日記を書くような態度で撮られる写真」です。前者ではできるだけ感情を交えずに、カメラという機械の能力を最大限に引き出し、対象がもっている要素を整理し抽象化した写真です。地図は現実に存在するもの全部描きこんでしまっては、ごちゃごちゃになって成立しません。さまざまなシステムと技術を使って不要なものを捨象し、必要なものだけを取り出すわけですが、地図のような写真というのは、このように対象を分析的に観察し、その意味を浮き彫りにする写真です。写真の特性を駆使すれば、それが可能なのです。
もうひとつの「日記を書くような態度で撮られる写真」というのは、書き手の感情や感覚や意識に重きをおいて撮られる写真です。日記ではなにを書き、なにを書かないかが、深い分析によって決まるわけではないですよね。もっと直感的にこのことを書こう、思って書く。分析的になるのは、その結果をあとで読み返したときです。作品指向は無用で、その日の出来事や食べたものなどを率直に記載することが大切であり、またそういう日記こそがのちに意味がでます。
「地図のような写真」と「日記のような写真」と分けましたが、どちらにも共通するのは記録であるということです。地図は実在する土地を平面化した記録であり、日記はその人の肉体を通過した出来事の記録です。写真もおなじように現実を記述したときにもっとも大きな力を発揮します。ただし夢で見たことは写らないですけど、日記ではそれが可能ですよね。写真は、現実に存在しているものしか写らない、しかもそこに光が必要である、これが二大原則です。
では、森山さんの写真は「地図」と「日記」のどちらでしょうか?
そう、後者の「日記を書くような態度で撮られた写真」であることは想像がつくと思います。森山さんは毎日写真を撮りますが、そのスタイルは一定していて、足のむく方向に歩いて、コンパクトカメラでパシャパシャ撮る、それだけです。カメラを換えることはなく、いつも同じカメラを使います。日記を書くのに、今日は万年筆だけど明日はパソコンということはないですよね。身になじんだ筆記具でおなじ日記帳につけていくのがふつうです。それと同じように、森山さんは世界のどこを撮ってもこのスタイルですし、今回の沖縄を撮ったときも同様です。
こういう写真家は、世界広しといえども、そうはいないように思います。荒木経惟さんもストリートスナップをしますけど、モデルを使った撮影もしますし、使用するカメラの幅も広いです。でも、森山さんはミニマリストというか、スタジオ撮影とか、三脚を使うとか、モデルを撮るとかはまったくなし。テーマもなし。いろんな土地を歩きまわってただ撮る、それだけなんですね。森山さんの下の世代には、おなじようなスタイルでストリートスナップをつづけている写真家が幾人かいますが、森山大道の存在がなければ、そういう写真のありようは定着しなかったと思います。
ふつうだと単純すぎて飽きてしまうんですけど、森山さんはそうではない。制限があったほうが集中できるし、意欲も燃えるというタイプなんですね。でも、そういうことは最初はわからないものです。いろいろと撮っているうちに、自分はこういうタイプだということが見えてくる。さまざまな実験のなかから、自分の写真を見る眼が育っていくわけです。
写真をはじめるのは簡単だけれど、撮りつづけるのはむずかしいというのが、わたしの持論です。どんな表現もそういう面はありますが、写真はとくにそうだと思うのは、シャッターを押すのは本人でも、写真そのものを写しだすのはカメラだからです。絵なら絵筆を自在に動かす技術がいるし、時間もかかります。でもカメラなら、いまのカメラはとくに操作が簡単ですから、センスがよければ初日から名作が撮れてしまうことがあるんです。でも名作が毎日撮れるなんてことはありえないですから、その後ずっと低迷したり、退屈したりします。
ですから、名作を撮ろうという意識ではつづいていきません。とくに「日記のような写真」の場合はそうです。だって日々は単調に過ぎていくものでしょう。昨日と今日の差なんてわからないほど似かよっている。よくみれば確かな差異がそこにあるけど、それに気づくためには永遠の自問自答が必要になるわけです。
森山さんは、物事と自分の関係を写真の形式のなかで問う、ということを時間をかけて、シンプルな方法でつきつめてきました。ではその作業がどのように行われてきたかを、スライドをお見せしながら話していこうと思います。
森山さんがデビューしたのは東京オリンピックの年、1964年です。とても覚えやすいです。細江英公さんのアシスタントを3年勤めて独立します。最初にまとめたのは「無言劇」というシリーズです。ご覧のように死産した胎児を撮影したもので、ホルマリン漬けになったものを瓶からだしてバックドロップを使って撮影してます。どうして胎児を撮りたいと思ったのか、理由はご自身でもわからないそうですが、撮りたいという気持ちだけは非常に強く、協力してくれる産院を捜しまわっています。
森山大道の写真はストリートスナップが特徴だとさっき言いましたが、最初の作品はそうではなくて、セットアップして撮っているんですね。このことをどう考えたらいいのかわかりません。森山さんが双子で生まれ、片方の方が赤ん坊のときに亡くなっています。それと結婚した直後にこれらの写真は撮られてます。というような説明をすると、みなさん、なるほど、そういうことが関係しているのか、と納得して気持ちがすっきりすると思うんですが、そんなに簡単にスッキリさせてはいけないという気がするんですね。
人は自分でもよくわからない行動をとることがある。その意味がずっと後になってわかることもあるし、ついにわからないということもある。犯罪にはそういう面がありますけど、写真もそれに似ていて、どうしてこれを撮ったのかわからないということがよく起きます。むしろ、写真を撮ることで謎が生まれてしまうのです。謎というのは、解けてしまったらなんてことはなくて、解こう、解きたいという気持ちが掻き立てられているときがもっともハイな状態ですよね。その意味で、写真は過程であり、解きたいという意欲をかきたてる装置、自分のなかに潜む謎を外にだす仕掛けである、と言えると思います。
1964年に撮られたもので、注目したいものがほかに二つあります。 ひとつは「ヨコスカ」シリーズです。森山さんが大きな影響を受けたのは東松照明さんですが、東松さんに全国の基地をとった「占領」シリーズがあります。それに刺激されて、住んでいる逗子からほど近い横須賀の基地の町を撮ったものです。
東松さんの場合は「占領」というタイトルからわかるように、米軍の支配下におかれた日本の戦後がテーマだったわけですが、森山さんは問題意識をもってむかったというより、撮る場所として思いついた、と言ったほうがいいでしょう。目的なくうろついて気になったものにシャッターを切る、その後ずっとつづいていった行為の最初がこれです。ですからタイトルも単純に地名がついてます。でもそれをカタカナで表記しているところに新世代の感覚が出てますよね。カタカナにすると文脈が断ち切られるでしょう。現代ではよくそういう例がありますよね。写真家名もカタカナになったりして。固有名詞をカタカナ表記してタイトルに使うというのは、もしかしたら森山さんのヨコスカが最初かもしれません。カタカナ表記の元祖ですね。
もうひとつは東京オリンピック関連の写真です。これをご覧ください。
カメラ雑誌でカヌーの練習風景を撮るという仕事をもらい、出向いたものです。画像がボケています。森山さんはその後ブレボケ写真で一気に有名になりましたが、その初期の一枚がこれです。撮っていても少しもおもしろくなかったそうです。望遠を駆使して迫力ある写真に仕上げることも出来たでしょうが、そう意欲は起きなかった。そもそもオリンピックにもスポーツ競技にも興味はなくて、ただ仕事でいっただけなんです。だから自分との結びつきが見いだせずに退屈したけど、ブレた写真はちょっとおもしろく思った、というわけです。
ここに森山大道のひとつの特徴が現れています。つまりカメラ機材を使いこなして対象に肉迫するという関心はないし、そういう器用さも持ち合わせてない、ということです。だけども、ブレた写真を見たときになにか気持ちに響くものがあった。肉眼が見たままをとらえた像ではなく、対象が喚起したイメージにずらしたほうがぐっときた。そういう自分の性向をこのときに知るのです。
ちなみにこの写真が載ったのはカメラ雑誌です。アサヒグラフなんかだったらだめだったかもしれないですけど、カメラ雑誌だから表現の範囲として許容されたんでしょうね。
気の向かないものでも撮れるように努力しなきゃ、と思う写真家もいるでしょうが、彼はそうではなくて、向かないものは止めておこうと思いました。ですので、そのときからいまにいたるまで、テーマがあらかじめ決まっている仕事はほとんど受けていないはずです。撮りたいものを自分が提案するならいいし、どこそこに行って好きに撮ってきてください、ならいいんですけど、相手の望むイメージが先に見えているとダメなんです。写真にはメディアの求めに応える職人的な要素がありますが、まったくそのタイプではない、ということです。
いまこう話していて、ひとつちょっと異質に感じるのは、そのあとに撮った「にっぽん劇場」というシリーズです。大衆演劇を撮ったもので、テーマがあるといえばあると言えるのですが、森山さんには思いつかないテーマです。なにせまだ20代ですから、若者が大衆演劇を撮るなんて、ふつうはありえないですよね。もっとカッコいいもの、自分の世代を代弁するものを撮りたいものでしょう。小屋があるのも下町や東京の場末で冴えないんです。
これは寺山修司が「俳句」という雑誌でエッセイの連載をはじめるにあたり、森山さんに写真を撮って欲しいと言われてはじまったものです。寺山さんは雑誌に載った「無言劇」を見てこの新人はおもしろそうだと声を掛けてきたんですね。打ち合わせの場に出向いたら、寺山さんにそのまま劇場に連れていかれ、撮らずにはいられない状況になったわけです。寺山さんが忙しくなり連載はすぐに打ち切りになったんですけど、そのまま撮りつづけてまとめました。
出かけるときはいやでいやで仕方がないのに、いけばすっぽりとはまって夢中で撮影してしまう、という日々だったそうです。写真ではそういう矛盾はしばしば起きます。恋愛関係と似てますよね。あの人に惹かれてはまずいと思いつつ、ずぶずぶと入っていく、ということがよくあるでしょう。それと似て、理念では説明のつかないものに背中を押されるわけです。胎児を撮った「無言劇」ともちょっと似ています。
この写真は「カメラ毎日」にもち込んで掲載され、高い評価を得て日本写真家協会批評賞を受賞します。まだ木村伊兵衛賞はなくて、これが若手の登竜門となる賞でした。それを受賞して活動に弾みがつくわけです。
四年後には、この写真をもとに雑誌で撮ったものも入れ込んで、はじめての写真集『にっぽん劇場写真帖』を出します。この写真集はふたつの点で新しかったのです。ひとつはお仕事写真も自主的に撮った写真もごちゃまぜにし、シリーズの枠組みも取っ払い、一冊にまとめたことです。こういう写真集はあまり例がなかったはずで、一冊にするにしてもシリーズの枠は維持しますが、それすらも外してバラバラにして組んでいます。セレクトも写真の順番もすべて森山さんが考えたとのことです。前例がないわけだし、相当な力技です。今日はこの会場に写真家の方も来ていらっしゃると思います。みなさん、概して撮ることには熱心だけど、自分の写真を見直すことをあまりしないという印象を受けます。自分の写真に対して他者になりきってない。『にっぽん劇場写真帖』の構成を、仔細に観察すればかなり勉強になるはずです。
もうひとつ、タイトルの「にっぽん」が漢字でなくてひらがなの点に注目ください。日本、とすると国家的だけど、にっぽん、とするととぼけた味わいがありますよね。横須賀をカタカナにしたのとおなじセンスがここに光ってます。それと「写真帖」という言葉。仰々しくない、プライベートな雰囲気があって、「日記のような写真」にふさわしいタイトルです。
90年代にホンマタカシさん、佐内正史さん、HIROMIXなど新しい世代の写真家が登場したときにこの写真集と似たことをしています。仕事写真も自主的な写真もごちゃまぜにしてポップなタイトルをつける。彼らは森山さんの仕事を知らずに、自分たちの感覚でそうしたわけなんですけど、実はそのセンスは60年代後半に森山さんに先取りされていた、というのがおもしろいです。
先ほど、メディアの求めに応じる職人的器用さとは無縁なこと、それを本人も自覚していたことを述べましたが、にもかかわらず、森山さんの若い時期の活動の場のほとんどは雑誌です。『アサヒカメラ』『カメラ毎日』などのカメラ雑誌、および新聞社からでていた『アサヒグラフ』『朝日ジャーナル』『毎日グラフ』などが主な活動場所で、そこで自分の思うままの写真を撮り、発表することで収入を得ていました。当時はまだカメラ雑誌やグラフ雑誌に勢いがありましたし、従来の写真作法に反逆するような写真を撮る若手写真家が登場したことで、雑誌のほうも活況がでる、という相乗効果があったわけです。
ところが、70年代になると連載の機会が減ってきます。写真界の流れが変わるんですね。これはどんなメディアでも起きることです。流行すれば必ず廃れる時期がやってくる。森山さんもこの潮流の変化をもろにかぶります。
この時期で重要なのは、『写真よさようなら』という写真集です。今回もそこから何点か展示されていましたね。ちょっと見てみましょう。どれもボケていて像がはっきりしませんよね。
これのどこがいいの?と思った方も少なくないと思います。おもしろいかと問われたら、わたしもイエスとはいいにくいです。やっぱりなにが写っているかわかったほうが、写真としての厚みは増すと思います。
でも、この写真集がなければ、いまの森山大道は存在しないのはたしかです。もっといえば、この写真集を出してなお撮りつづけた森山大道がいなければ、ということですね。いま森山さんの活動は世界的規模に広がっていますけど、その下地は、『写真よさようなら』の刊行とそれにつづく鎮静の期間に用意されたと、はっきり言うことができます。それはどういうことかを、これからお話します。
暗室作業をやったことのある方ならおわかりと思いますが、プリントするときに試し焼きというのをします。印画紙のちいさな断片に像を焼き付けて露光状態を見るんです。暗室には、そういう断片的な像とか、露光を失敗したプリントとか、だれかと共有しているならほかの人が捨てたプリントとかが散乱しています。暗いオレンジ色のライトのもとでそれらが目に入り、ふと引き寄せられる、ということがよくあるんですね。意味ではなく、像として。この世のかすかな痕跡への未練のような感情が湧いてくるんです。
きっと太陽光によって像を定着できた写真の誕生の瞬間にさかのぼるんでしょうね。科学的な仕掛けによって、存在しなかったものが現れたときの興奮が直感され、写真ってもとはこれだったんだ、というような素朴な感慨が湧きおこります。被写体が何であるかとか、それがうまく写っているかなんてことを飛び越え、像が出現していることへの歓びと共感ですよね。
そうやって写真への原初へと旅立ったのが、『写真よさようなら』という仕事であると、わたしは理解しています。つまり撮りつづけるうちに、写真とは何かという問いがいやおうなく浮上して、それを超えないかぎりは自分が写真を撮ることの意味が見えなくなってしまった、そこで一度故郷にもどってみたわけです。
森山さんはいま、自分の写真は町歩きとカメラが合体したに過ぎない、とおっしゃるわけだけど、そしてその言葉に嘘はないんですけど、事はそれほど単純ではないんです。歩きながらほいほいと撮れてしまう状態が50年間つづいてきたわけではなく、いまの森山さんはいったん写真の出発点までいってもどってきた結果なんです。それを「自己否定」などという言葉で表現すると文学的すぎて曖昧ですが、そうではなくて、形式への問いだったということです。なにを撮るかという被写体への問いは多くの写真家がしまけど、写真ってなんなんだ、という知的で原初的な問いがこの時期になされ、その思索が後半の活動の支柱となったわけです。
そこまで徹底しましたから、70年代後半は潜伏していた時期です。雑誌の仕事がほとんどなくて、時間だけがあるという状態ですね。さまざまな試みをしています。シルクスクリーンをやったり、コピー機で複写した写真集をつくったり、個人誌をだしたり、北海道にアパートを借りて撮影したり、仲間とギャラリーを開いたり、写真教室をやったりして、とにかく自分を揺さぶって、ブレたりボケたりして消えかかった像を再び自分の手に取りもどす努力をしています。
今回、展示の中心になっている北海道と沖縄のシリーズは、この時期の仕事です。まず北海道のことからお話しましょう。1978年、札幌にアパートを借りて道内を撮り歩きます。250本のフィルムを撮りますが、数点をカメラ雑誌に載せただけで、大半はプリントも発表もせずにしまい込んでしまいます。なぜか。結果に自信がもてなかったからなんですね。この時期、彼はなにを撮ってもこれでいいのだろうか、という戸惑いばかりが先立って結果を世に問う自信がなかった。だから撮影はしても、仕上げずに投げ出してしまったのです。
これらの写真がプリントされて世にでたのは2011年、札幌で大規模な写真展がおこなわれたときです。そのときに、30年前に撮られた結果を見て、多くの人が驚きました。わたしもそのひとりです。本人がお蔵にしたのだから大したことないだろうと思っていたら、素晴らしくいいんです。どうしてこれに自信がもてなかったのかと、不思議なくらいですよね。
沖縄に来たのはそれより2年前の1976年ですが、そのときの写真にも今回はじめて展示されたものが数多くあります。北海道と同様に、その結果に大変びっくりしています。人間が写っているでしょう。男の胸や、人の横顔のアップとか、すごく元気いいですよね。人間にカメラをむけるだけの活力があったということですよね。気持ちが外に向いているし、自分に制限をもうけずに自由に泳がせている気がします。でもこれらの写真も、いくつかが写真集に収められたものの、これまで展示されたことはなく、全体像はわかりませんでした。
これらの写真は意識が外にむかってひらかれた状態で撮られていますが、それとは対極にある例を、ここで挙げてみたいと思います。おなじく70年代に撮られた「桜花」です。桜は写真にするのがとても難しい花なんですね。花の美しさも印象的ですが、みるみるうちに姿が変わり、時間というものを意識させるところが特異です。だからどう撮ってもホンモノを見ているときの感覚に追いつかない。実物を見ているほうがずっといいな、と思ってしまうんです。でもこの「桜花」はすごいですよね。桜の花が秘めている鬼気迫る雰囲気や、おどろおどろしさや、切迫感などが存分に引き出されてます。名作ですし、まわりの評価も高かったようです。
でも森山さんはこの写真については、発表はしましたが自分ではダメだししたんです。つまりこういう写真を撮っていては次にいけない、ということですね。様式性が強いから、同じパターンの繰り返しになる可能性があるし、自分の内部にあるイメージを表現しているので、内向してしまう危険があるわけです。かといって、沖縄や北海道の路上で気持ちを外にむけて撮ったスナップにも自信がもてなかった。シャッターを切っている自分の肉体と意識がしっくりとかみあわない。自分の行為を自分で認識できない、宙ぶらりんの状態です。
写真ではそういうことはよく起きるんです。自分が理解できていることだけが写真に現れ出るわけではないんです。未知の自分が引き出され、当人がそれに馴染めないということがあり得ます。
あたかも花火があがってピカっと光ったあとに音が届くように、知覚と認識のあいだに時間差が生じるのです。沖縄と北海道のシリーズは、その時差が見てとれるところが実に興味深いです。森山さんの著作に「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい」というタイトルの本がありますが、その言葉のとおり、人の意識する時間は直線的に進まずにぐねぐね曲がったり、行きつもどりつするんです。写真は人間のそうした面をあぶり出す装置だということです。
はじめに「地図を制作するような態度で撮られた写真」と「日記を書くような態度で撮られた写真」に大別されること、森山さんの写真は後者であることをお話しました。日記とは生きていく時間のなかで生じる出来事を記すものです。出来事、といっても大きなものばかりではありません。朝7時に起きた、というのも出来事にはちがいなく、生の時間は大小さまざまな出来事により成り立っているとも言えます。それらの出来事を写真という形式を使ってとどめていくこと、これが森山大道の写真です。
会場で上映されているビデオのなかで森山さんは、結局のところ自分は通過者なのだ、という話をしています。これは、生の時空間をカメラをたずさえ通過してきたということ、つまりは写真は生きていることと抜き差しならないということですね。こういう写真のありようというのは、欧米にはあまり見られないんです。今日は「地図を制作するような態度で撮られた」理念的な写真についてはお話しませんでしたが、むこうではそちらが主流なんです。教育現場でもそうしたタイプの写真を教えます。
日本はむかしから日記文学が盛んです。『土佐日記』、『更級日記』、『紫式部日記』、近代では永井荷風の『断腸亭日乗』など、多くの日記が文学として読み継がれてきました。そうしたことと森山大道の写真は、もしかしたら無関係ではないのかもしれません。日記のほかにも、短歌、和歌、俳句のように、日本にはこの国ならではの文学の形式があります。それが形をかえて現れ出たものが日本の写真なのかもしれない、とも考えます。日本人の自然観と、それは生命観でもあると思うのですが、日本の写真のあいだには浅からぬ関係がありそうな気がしています。今後、その方向にも考えを深めていければと思っています。ありがとうございました。
■「森山大道 終わらない旅 北/南」展 ※終了しました
会期:2014年1月23日(木)~3月23日(日)
会場:沖縄県立博物館・美術館 企画ギャラリー1・2
大竹昭子(おおたけ・あきこ)
ノンフィクション、エッセイ、小説、写真評論など、ジャンルを横断して執筆。トークと朗読の会<カタリココ>を各地で開催している。 著書に『この写真がすごい2008』(朝日出版社、2008)、『きみのいる生活』(文藝春秋、2006)、『眼の狩人』(ちくま文庫、2004)、短編集『随時見学可』(みすず書房、2009)、『あの画家に会う 個人美術館』(新潮社とんぼの本, 2009)、長編小説『ソキョートーキョー』(ポプラ社、2010)など他多数。
web: 紀伊國屋書店「書評空間」の同人。草森紳一記念館「白玉楼中の人」で「目玉の人」を不定期連載。